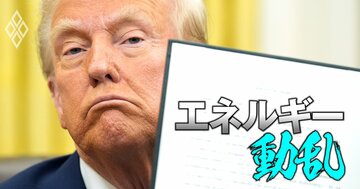トランプ政権で動き出すアラスカLNGj完成イメージ(アラスカガスライン開発公社(AGDC)ホームページより)
トランプ政権で動き出すアラスカLNGj完成イメージ(アラスカガスライン開発公社(AGDC)ホームページより)
米トランプ大統領は就任直後の大統領令で「国家エネルギー非常事態」を宣言。昨年1月にバイデン前大統領が行った新規LNG(液化天然ガス)プロジェクト認可停止を撤廃した。これにより、今後米国でのLNG開発には足かせがなくなり、米国での新規プロジェクトが進展する。折しも、欧州では脱炭素化に向けた水素やアンモニアなどの代替燃料計画が想定よりも遅れ、海運業もLNG燃料船の導入を計画。一方でアジアでは石炭火力代替としてのLNG火力へのシフトが進むなど、世界的にLNG需要が拡大傾向にある。それに伴ってLNGプラントや受け入れ設備の計画が増加し、日本のエンジニアリング大手、日揮ホールディングスは昨年に続き今年も海外LNGプロジェクトの受注を予定している。ただ、LNGプロジェクトも脱炭素化で変質を続けており、計画が増加したとしても、日本が誇っていたLNGプロジェクトの優位性が必ずしも担保されるというわけではなさそうだ。長期連載『エネルギー動乱』の本稿では、世界各国で動き出したプロジェクトの最新商談状況をリストアップし、課題を探った。(エネルギージャーナリスト 宗 敦司)
コストと規制遅れで
脱炭素案件が停滞
「待ったなし」のはずの脱炭素投資が想定ほど進んでいない。欧州ではオランダの水素パイプライン計画で当初2030年までに完成する予定だったものが、目標達成は不可能とみられている。その大きな要因は法制度の整備や許認可手続きの遅れ、そして計画を進めるあらゆる面での人的リソース不足が指摘されている。
さらに欧米全体では資機材価格の高騰といったインフレの影響で、導入拡大のスピードが低下している。IATA(国際航空運送協会)によると、SAF(持続可能な航空燃料)の24年の生産量は世界で年産130万キロリットルとなり、前年度の約2倍に拡大し、世界のジェット燃料生産量の0.3%に達したが、当初予想していた190万キロリットルに対しては大幅に下回る結果となった。
脱炭素燃料の供給価格もその要因とみられる。水素やアンモニアを本格的に市場に投じていくには、やはりその価格の高さが壁になる。脱炭素社会への移行は社会生活にも大きな影響を及ぼすため、供給価格があまりに高ければ生活ができない人々が多数発生してしまう。
価格を補填(ほてん)するにしても、大きな予算が必要となる。そのため脱炭素化投資においてもアフォーダビリティ(価格の手頃感)が重視され、脱炭素化投資の勢いを失わせつつある。この停滞を背景に、最も低炭素の化石燃料であり、大量供給が可能な天然ガス、LNG(液化天然ガス)の需要が拡大し、供給から受け入れまでのサプライチェーンで各種プロジェクトの動きが活発化しているわけだ。
ただし、実は、最近のLNGプロジェクトは質が大きく変化している。そして、これまで日本のエンジニアリング大手が持っていた優位性が失われる可能性がある。どういうことか。次ページでは、世界で進むLNGプロジェクトの一覧を示すとともに、日本勢の優位性が失われる要因を明らかにする。