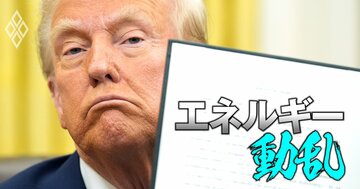写真提供:アクセンチュア
写真提供:アクセンチュア
世界のエネルギー政策・産業が大きな曲がり角を迎えているなか、日本のGX政策の方向性はおおむねブレてはいない。長期連載『エネルギー動乱』内の『脱・脱炭素の試練』の本稿では、GX推進での重要な役割が期待されている「ワット・ビット連携」の提唱者であり、日本の電力ネットワークのキーパーソンである東京電力パワーグリッド取締役副社長執行役員CTO(最高技術責任者)の岡本浩氏へのインタビュー前編をお届けする。(聞き手/アクセンチュア ビジネスコンサルティング本部マネジング・ディレクター 巽 直樹)
インタビューの「はじめに」
エネルギー情勢とGX推進の要を前説
世界のエネルギー情勢が日々刻々と変動するなか、日本のエネルギー政策の国際社会へのスタンスは以前から大きく変化してはいない。今年5月28日には改正GX推進法が参議院本会議で可決・成立した。CO2の直接排出量が3カ年の平均で10万トン(t)を超える企業に対し、排出量取引制度「GX-ETS」への参加を義務付けた。これまでのところ、米欧での方向転換が相次いでいるものの、このように日本は従来の方針を堅持している。
一方、GX推進において、原子力政策などで明らかな変化も見られる。時間がかかったとしても、日本のエネルギー安全保障や経済成長に合わせた軌道修正が、この先になされることを諦める段階ではないかもしれない。
経済成長と環境適合の同時成立は、現在の技術を前提にした場合、経済学的に困難であることは、これまで多くの識者から指摘されてきた。しかし、優先順位を考えて取り組めば、最終的にそれらを成立させることが、順を追って実現する可能性も見えてくる。
この道筋における最重要キーワードは「モア・フロム・レス」である。『プラットフォームの経済学 機械は人と企業の未来をどう変える?』(日経BP)などで有名なアンドリュー・マカフィーが著した同名の書籍『MORE from LESS 資本主義は脱物資化する』(日本経済新聞出版)で提唱した中心概念である。
この「モア・フロム・レス」の考え方を、日本でのエネルギー利用のみならず社会インフラ全般、ひいては社会システムのあり方全体に拡張するべく提唱されたのが「ワット・ビット連携」だ。早くもGX推進の要に据えられ、骨太方針とエネルギー白書でも矢継ぎ早に取り上げられている。
東京電力パワーグリッド取締役副社長執行役員CTO(最高技術責任者)の岡本浩氏へのインタビューを通じ、この動向の核心に迫る。