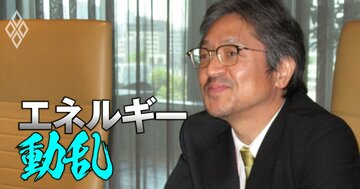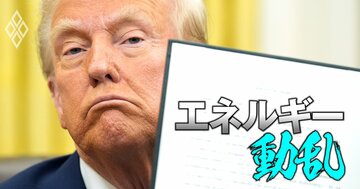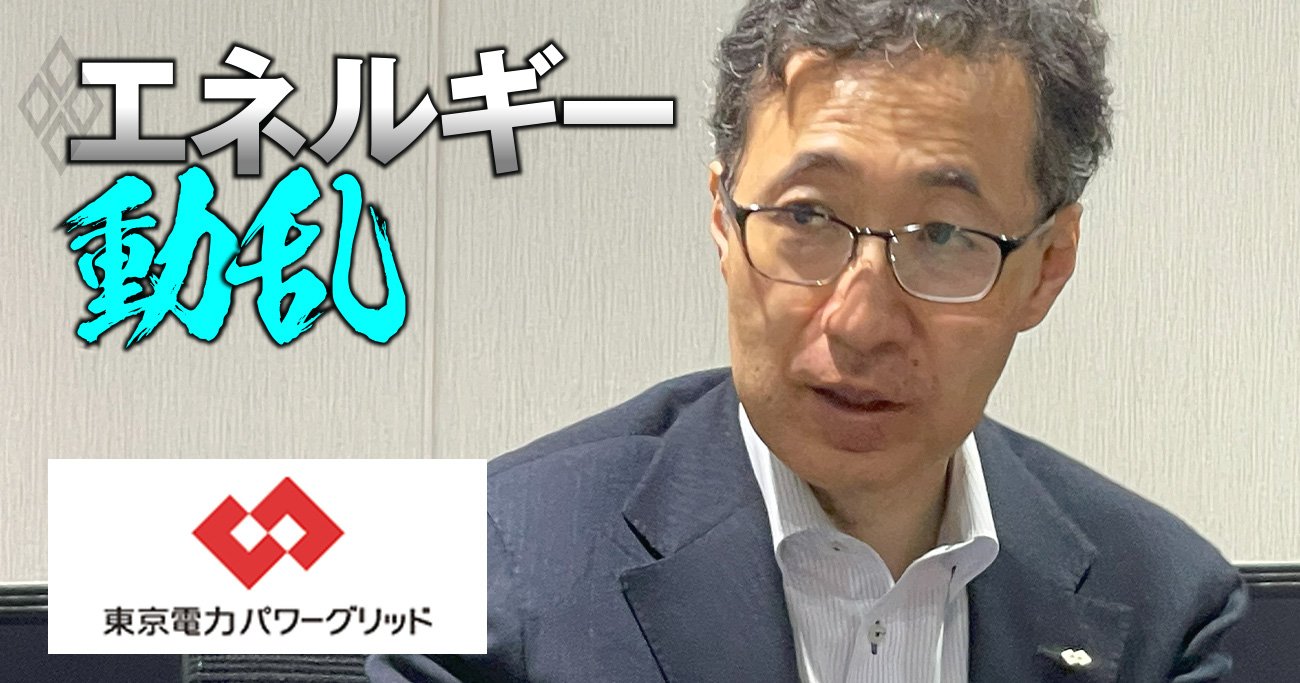 写真提供:アクセンチュア
写真提供:アクセンチュア
世界のエネルギー政策・産業が大きな曲がり角を迎えているなか、日本のGX政策の方向性はおおむねブレてはいない。長期連載『エネルギー動乱』内の「脱・脱炭素の試練」の本稿では、GX推進での重要な役割が期待されている「ワット・ビット連携」の提唱者であり、日本の電力ネットワークのキーパーソンである東京電力パワーグリッド取締役副社長執行役員CTO(最高技術責任者)の岡本浩氏へのインタビュー後編をお届けする。(聞き手/アクセンチュア ビジネスコンサルティング本部マネジング・ディレクター 巽 直樹)
「ワット・ビット連携」推進が
国の政策の中に次々と明記
――今年2月の「GX2040ビジョン」において「ワット・ビット連携」推進が打ち出され、3月より「ワット・ビット連携官民懇談会」での議論が始まりました。そして、6月には、「経済財政運営と改革の基本方針2025 ~『今日より明日はよくなる』と実感できる社会へ~」(骨太方針2025)に盛り込まれ、さらに「令和6年度エネルギーに関する年次報告」(エネルギー白書2025)にも記載されました。国の政策として明記されたわけですが、一連の流れをどのように受け止めておられるのでしょうか。
政府の取り組みとしては、総務省と経済産業省・資源エネルギー庁における4つの課が共同事務局となって主導する「ワット・ビット連携官民懇談会」が開催され、デジタル庁、文部科学省や環境省などの関係省庁もオブザーバーとして参加しています。歴史的に見ても、省庁間の壁を越えてここまで踏み込んだ連携が実現するのは、画期的なことだと思います。
さらに、懇談会の下には「ワット・ビット連携官民懇談会ワーキンググループ」も設置され、関係事業者における整備状況や計画の共有、DC立地の課題、効率的整備に向けた有効な方策などが議論されました。そして、約2カ月半後には「ワット・ビット連携官民懇談会 取りまとめ1.0」が公表され、その時はこれが反映されていけばよいと考えていました。
しかし、この取り組みのスピード感は非常に速く、政府の「骨太方針」や「エネルギー白書」にまで「ワット・ビット連携」が挙げられたことは予想を超えていました。我々はたいへん驚きましたが、これは政府の本気度の表れであると理解しました。MESH構想(ワット・ビット連携と電力システムのインターネット化)の実現に向けた大きな追い風になると感謝するとともに、今後の動向に期待を寄せています。
――ご著書(岡本浩・高野雅晴『経営に活かす生成AIエネルギー論 日本企業の伸びしろを探せ』〔日本経済新聞出版〕)を拝読しました。現時点で生成AIとエネルギーについて論じたベストの書であるとの感想を持ちました。読後に「ワット・ビット連携」がもたらす産業構造変化や地政学的含意を踏まえ、単なる技術論を超えた、統合されたインフラの再設計、ひいては社会デザインの再構築まで議論する必要があるとの印象も持ちました。