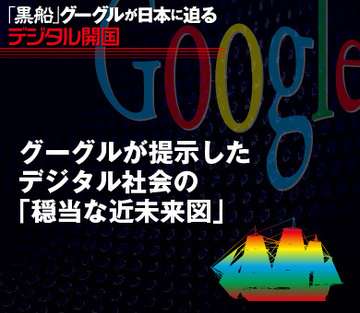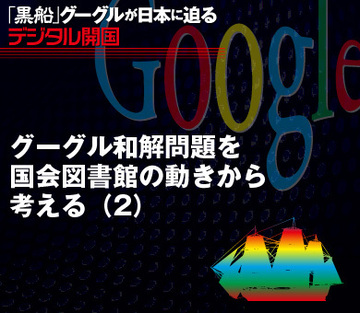前回書いたとおり、離脱期限が9月4日に延びました。これまでは、時間がない中で十分な情報もないまま、「グーグルの脅威」とか「一方的なやり方」とかいった、観念的または感情的な議論が先行していました。このコラムでは、グーグル問題への対応を通して、日本の出版界と著作権の問題を考えていくことにしていますが、意味のある議論をしていくためには、この和解案の内容を正しく理解することが必要です。
今回と次回、「和解によって権利者が得る利益」と「今後の具体的な運用」について説明します。どちらも細部に入り込んだ議論にならざるを得ませんが、我慢しておつきあいください。
権利者が得る利益について
前回は、この和解によってグーグルがスキャンした「本」をどのように使うつもりなのか、ということについて見てきました。もっとも和解が成立したとしても、グーグルがすべて「タダ」で使えるわけではありません。権利者には、グーグルが得た収入から一定割合が分配されることになります。また使われ方についても、権利者に異議を唱える権利があり、権利者の意向は基本的に尊重されることになっています。今回はその詳細を見ていくことにします。
権利者とは「著者」と「出版社」
和解案における「権利者」は、「著(作権)者」と「出版社」であるとされています。アメリカの著作権法は、著作権の譲渡または排他的な使用許諾をすることを「権利の移転」として定義し、権利付与期間が終了したときには権利が「復帰」するとしています。このためアメリカでは、著者と出版社との間では、期間を決めていわゆる「信託的譲渡」という形で著作権が著者から出版社に譲渡され、期間の終了などにより著者に復帰するという出版慣行があるようです。
日本における著者と出版社との間の契約は、アメリカでの出版慣行と異なる部分があるので、解釈によっては、アメリカの出版社が有している法的な地位を、日本の出版社は有しておらず、この和解案における権利者とはならない(出版社自ら著作権者となる場合は別です)という考え方も成り立つ可能性があります。
しかし、そのような結論はあまり妥当なものとは言えません。出版社を権利者として位置づける実質的な理由は、「本を読む」という行為について、グーグルによる「表示使用」であろうと、「本」を書店で購入して読むのであろうと、違いはないというところにあると考えられます。つまり読書マーケットにおいては、グーグルのサービスは「本」の販売と競争関係にある部分がある、ということなのです。この和解案は、出版社の権利を肯定したところで作られており、それは「表示使用」できる「本」は原則として「絶版」に限定されるというところに端的に表現されているのです。