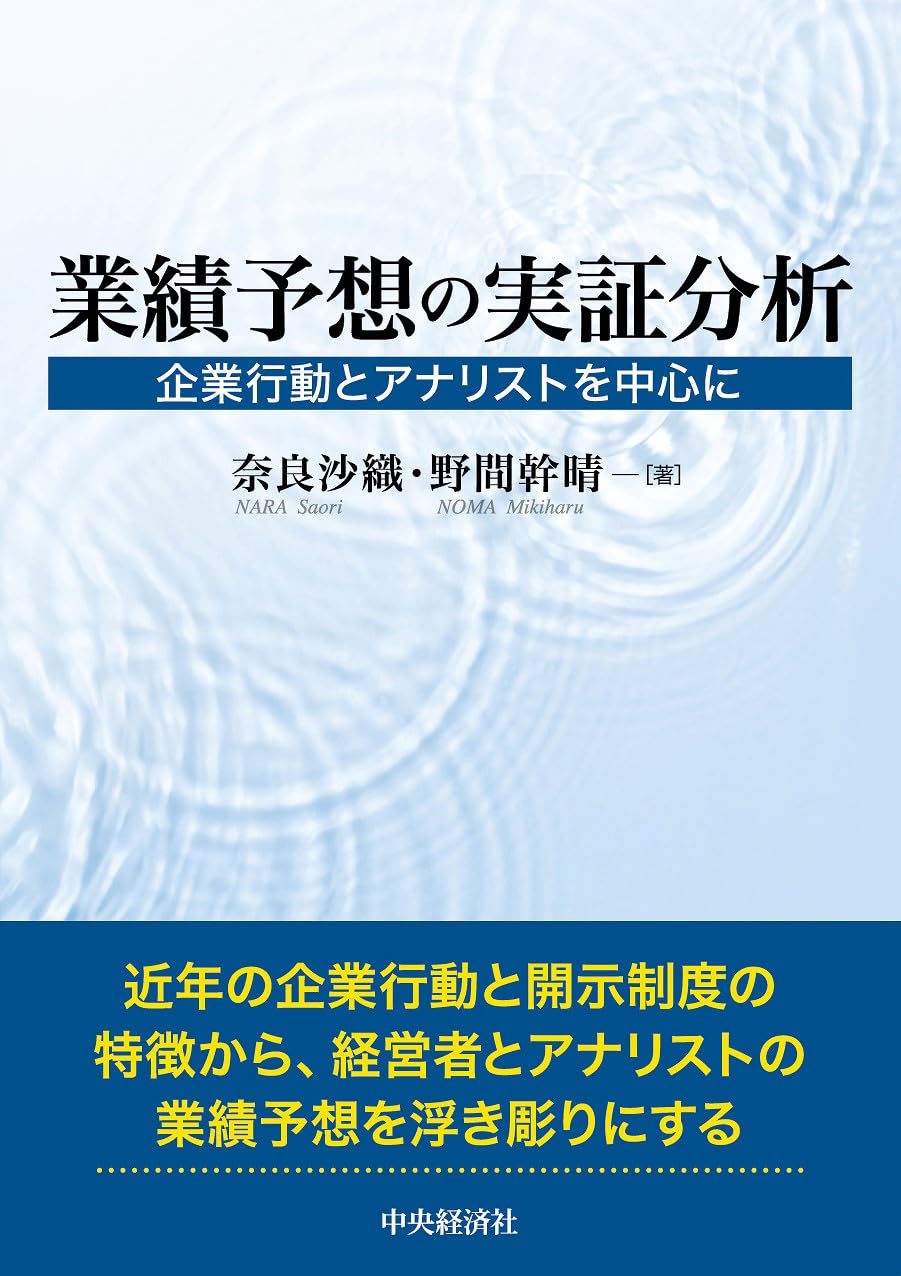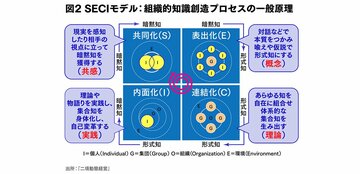経営者とアナリストの予想も
二項動態で進化を
――2024年発行の書籍『業績予想の実証研究―企業行動とアナリストを中心に』(奈良沙織との共著、中央経済社)でも、精緻な実証研究の結果が記されています。主に、企業の次期業績についての経営者予想とアナリスト予想の実態や企業価値との関係、関連する制度の影響等が研究対象です。通説を覆すというよりも、日本での研究事例が少ない分野です。この研究から考察されることも、日本企業の経営者が保守的・リスク回避的であることに通じます。
本書の主な目的は、「日本における業績予想とアナリストの役割と実態を明らかにする」「近年の企業行動の変化やディスクロージャーやガバナンスの強化といった制度変化が業績予想やアナリストに与えた影響を明らかにする」「日本におけるアナリストに関する包括的な研究を提示し、経営者予想とアナリスト予想の交錯を明らかにする」の3つです。
ほぼ全ての企業が一定のフォーマットに従って経営者予想を開示するというのは日本だけです。日米比較で言うと、米国ではアナリスト予想が、日本では経営者予想の影響力が大きいのです。実際の業績と予想の乖離は株価・企業価値に影響を与えますから、日本では経営者予想が保守的になります。
本書では、ディスクロージャーに優れた企業は、期初に保守的な経営者予想を開示し、期中に予想を小幅に上方修正することを明らかにしています。
――実感としては、まさにそうですね。
アナリスト予想について言えば、そのカバレッジが多いほど価値関連性が高いことを明らかにしました。企業規模で比較すると、小規模企業ほど経営者予想で、大企業企業ではアナリスト予想で、予想精度が価値関連性が高い。アナリスト・カバレッジが多いほど経営者予想の精度が高くなること確認しました。
経営者はアナリスト予想を僅かに上回る利益予想を公表することで、期待マネジメントを行なっています。経営者予想が公表されると、直ちにアナリスト予想が修正されることも実証しました。
そして、経営者はアナリスト予想を参照して予想を公表し、アナリストは経営者予想の公表・修正を受けて自身の予想を見直すなど、経営者予想とアナリスト予想は相互に影響を与え合っているのです。
2010年の論文との関連で言うと、アナリスト・カバレッジが多い企業ほど、ベンチマーク(期首の経営者予想や前年度利益など)達成のため、利益調整する傾向が強く、研究開発投資を削減していることも確認されました。
――「アナリストもステークホルダー」という記述も説得力がありました。
日本では、アナリストの重要性が米国に比べると低いですね。前述の通り、経営者予想が一般的になっているからでもありますが、直接金融の比重が大きい米国と、間接金融の比重が大きい日本の違いも反映しています。市場としてどちらが成熟しているという話ではありません。いわゆる経路依存性がありますので、制度を変更すれば実態がすぐに変わるというほど簡単ではありません。
要は、企業の経営実態や情報が公平かつ迅速に開示され、市場に伝わるようになれば良い。経営者予想とアナリスト予想の両方が共に進化していくこと、この点でも二項動態が求められます。
――お話を伺っていくと、日本企業の経営者がリスクテイク回避となる条件が重なっています。経営者は従業員の延長線上にあって株主スタンスではなく、巷間言われる通り固定的な任期の期間をつつがなく過ごすことが経営の動機になっています。
制度や歴史、社会構造などさまざまな要因が影響しています。前述した退職給付面から経営者が債権者スタンスに立つのは、その制度だけに依るものではなく、日本では企業を簡単には倒産させられないということも絡んできます。赤字が続くと銀行などの債権者から経営再建圧力がかかる間接金融では保守的な経営に合理性があるということも言えます。
企業に対する解雇規制が厳しい制度は、労働市場の流動性が低いことと裏腹の関係にあります。長期で働くほど退職金に対する税控除比率が大きくなる制度は、労働流動性の抑制という面から求められたものでした。
しかし今日、その制度は見直しが議論され始めていますし、転職市場は急成長しています。新卒一括採用を廃止する企業も出始めました。経済情勢に従って、いろいろな面で変化が見られます。日本人の思考も変化しつつあり、それに伴い、さまざまな制度が変革されてきています。