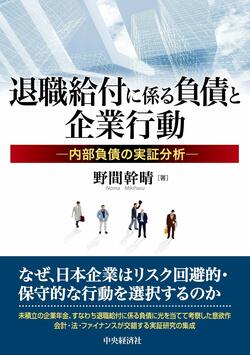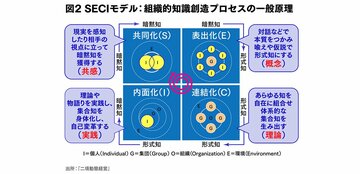日本を代表する経営学者・野中郁次郎氏の最後の著作となった『二項動態経営―共通善に向かう集合知創造』。野中理論の集大成であり、日本に向けた新たな提言の書となっている。日本企業に対する課題意識や想いを野中氏と共有し、知的コンバットを実践し、集合知を創造した共著者の野間幹晴・一橋大学大学院教授に、本書の読みどころや共同研究の経緯、野間氏独自の研究等について聞き、前後編でお送りする。後編は、野中氏と課題意識で通底した日本企業の過少リスクテイクについて野間氏の著書『退職給付に係る負債と企業行動』と『業績予想の実証研究』から考える。(取材・文/ダイヤモンド社 論説委員 大坪 亮、撮影/鈴木愛子)
日本企業の経営者は
なぜリスクをとらないのか
――前述(前編)の通り、野中先生が関心を持たれ、共同研究の契機になりました野間先生の論文「日本企業の競争力はなぜ回復しないのか」(『一橋ビジネスレビュー2010 年夏号』(東洋経済新報社)は、通説を覆すものでした。全上場企業で、「配当している企業の比率は、米国よりも日本のほうが多い」「研究開発投資を削減する企業の比率は、米国よりも日本のほうが多い」ことを実証しています。実は、日本は株主還元の意識は強く、業績赤字を回避する志向が強い一方、米国は赤字企業の比率が高く、配当ができなくても研究開発投資は維持する傾向が強い、という結論を導いています。そして、日本の経営者は米国の経営者よりもリスクテイクに消極的であると考察しています。
米国では赤字企業が多いとか上場企業の配当が少ないという研究はそれまでもあったのですが、上場企業全体で長期に日本企業と先進諸国の企業とを比較したのは、私の研究が初めてだと自負しています。先進諸国の中でも日本では、配当を支払う上場企業が多いのです。意外性をもって、この検証結果を受けとめた方が多かったかと思います。
また、日本企業が強い要因の一つは、長期的視野に基づいた経営で、業績に左右されることなく、研究開発投資を維持することにあると従来は考えられていました。米国のビジネススクールでもそういう論調が強く、私も学生時代の1990年代にはそのように学びました。
しかし、実証研究を行うと、この論文で示した通り、日本企業は研究開発投資を削減する傾向が先進諸国企業の中で最も強く、特に米国企業と比べると格段に強いのです。
この経営の違いの理由はなかなかわかりませんでした。ある会社の幹部研修でこの研究の一部を示して、「米国企業は赤字でも研究開発投資を維持している。日本企業ももっとリスクテイクすべきだ」と提言したら、出席された経営者から「現実の経営であなたの考え通りにリスクテイクするのは難しい」と言われました。それを聞いて、リスクテイクしないのは個別の企業や経営者の問題ではなく、構造的な問題なのだという思いを強くしました。
――構造的な問題をどのように検討したのですか。
例えて言えば、コロナ禍で欧米に比べて日本の感染者数が少なかった初期段階に、その要因となるファクターXがあるのかと検討されたのと同じです。日米の経営者の行動の違いをもたらすファクターXは何か、日米企業の違いをいろいろな面から考えました。その結果、企業年金をめぐる債権者保護に関する日米の制度の違いに気がついたのです。
――それが2020年に著された書籍『退職給付に係る負債と企業行動―内部負債の実証研究』(中央経済社)に結実するのですね。確定給付年金制度をとる日本企業で、退職給付債務が年金資産より大きく未積立の年金債務が多額の場合が多く、経営者がリスクテイクに消極的になっていることを実証しています。一方、企業が倒産しても年金給付保証公社が年金給付を保護する制度の米国では、経営者がよりリスクテイクしやすくなっていると分析されています。
企業破綻における日米の年金受給権保護制度を比較すると、公的な支払保証制度がない等の要因によって日本では債務者である企業が不利に、支払保証制度がある米国では債務者の企業が有利になっています。
この制度の違いは、イノベーションに影響を与えることが理論的に示されています。米国のように債務者に有利な制度では、企業が流動化しやすく、結果的に技術も流動化し、社会システムの中でイノベーションが活発化します。反対に、日本の場合は、企業内での技術の継続性は確保されやすいのですが、企業外への技術の流動性がなく、イノベーティブな社会にはなりにくいのです。