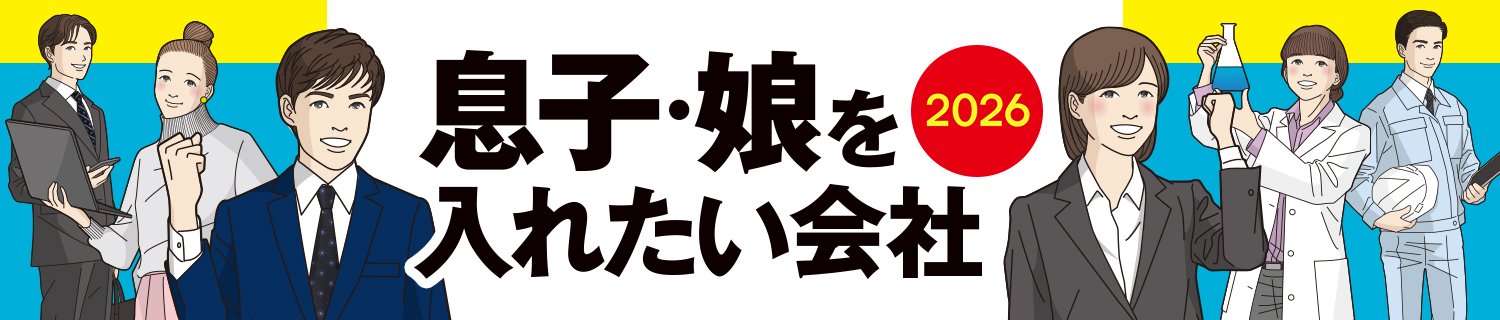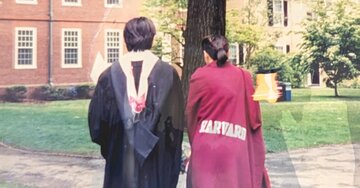太郎氏亡き後に見つけた「自分のやりたいこと」
 杉村太郎氏のハーバード大学行政大学院修了証書(左)と大学院在籍中に愛用していたネーム入りの椅子(右) Photo by Kuniko Hirano
杉村太郎氏のハーバード大学行政大学院修了証書(左)と大学院在籍中に愛用していたネーム入りの椅子(右) Photo by Kuniko Hirano
――「悔いのない生き方」は、まさに我究館のメッセージです。キャビンアテンダントから始まり、その後は異なる分野を歩いてこられましたが、全てが今の貴子社長の生き方につながっている印象を受けます。
杉村 自分の中では、そうですね。太郎さんが倒れて意識を失って息を引き取るまで、2週間ほどの時間がありました。私の思いの丈を伝え、親しい人たちの見舞いを受けたこの時間があったからこそ、私は太郎さんとの別れを受け入れることができたのだと思います。
人々の人生を輝かせるという太郎さんの夢を一緒に追いながら、また、自分なりのやり方で人々の人生を輝かせたいと思ってきた一人として、ようやく落ち着いて太郎さんがいない世界でどう生きていこうと考えられるようになったとき、彼が実現したかった世界を彼ではできなかった形で実現していくことが私の役割であり、自分が心からやりたいことだと思えたのです。
――杉村太郎氏には自身の我究館の将来像があったと思いますが、その夢と会社の経営を引き継がれて、今後どのようにしていきたいと考えますか?
杉村 太郎さんがいたらできたこと、でも太郎さんがいたらできなかったことというのは絶えず意識しながら、私だからできることを一つ一つしっかりと繰り上げていきたいと考えています。
太郎さんが追い求めていたもう一つの夢に「より良き社会の実現」があります。それは彼一人でできることではありませんから、そのために若者を育て、同志をつくり、夢に向かって一緒に走ってくれる仲間の輪を広げていくこと、それが我究館の使命の一つです。
新しく人を育て、また卒業していった方にとっても、誇りとなり、よりどころとなる教育の場というのを継続していくことはとても重要です。杉村太郎というカリスマがいるから成立するのではなく、2代目、3代目……と、経営者が同じ考えをしっかり承継していける組織づくりをまずは心掛けています。
その一つとして、我究館生と卒業生、そして我究館が三位一体になれるような、志を持った仲間が集まる盤石な礎として「我究館」という組織を育てていきたいと考えています。従来は、太郎さんがいることでまとまっていた組織ですから、難しくはあるのですが……。