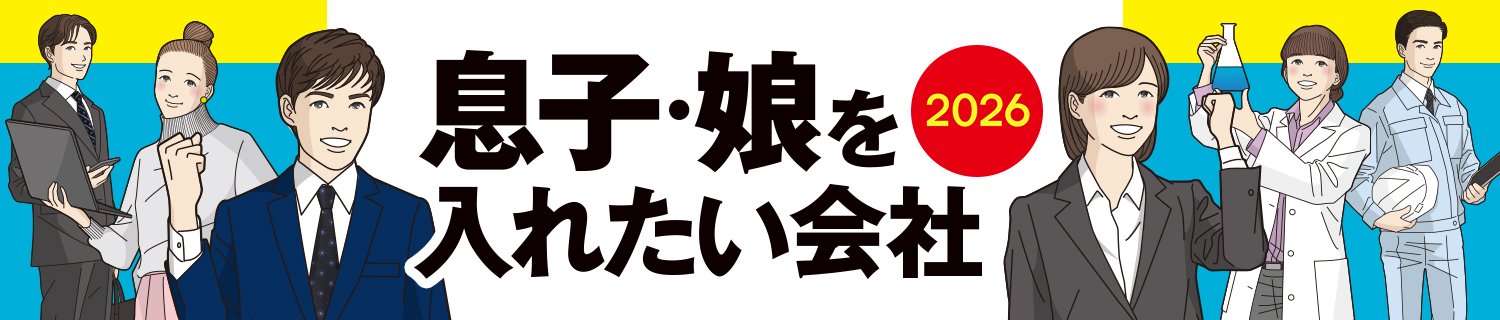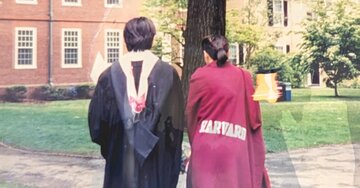シンクタンクの「何でも屋さん」で学んだ企業経営
――大和総研ではどのような仕事をされましたか。
杉村 大和総研には当時、投資調査本部、コンサルティング、システムの3つの部署があり、最初は調査本部のマーケットリサーチ専任アナリストとして入社しました。幅広いマーケットのリサーチに携わりながら、当時同社が提供していたCS放送の証券情報番組でエコノミストのインタビュアーやメインキャスターも務めました。
その後は、調査本部の経営企画、事業企画、新卒採用、人材開発、営業、広報と、本当にいろいろな業務に携わりました。
――経営者となった現在に通じる経験をされたのですね。
杉村 本当にそうなんです。新卒採用では、インターンシップのプログラム作成、2週間の実地引率、評価の方法、役員への結果報告から最終的に誰を採用するか、これら一連の業務を全てやっていました。
「やってくれる?」と言われたことに応えていった結果、ほとんどの部門の実務を経験して「何でも屋さん」みたいになっていましたね。だから、2011年8月に太郎さんが亡くなって今の会社が少し傾きかけたとき、自分も経営に携わって何とかしようと思えました。
――我究館にとって「杉村太郎」というカリスマがいない穴は大きかったでしょうね。
杉村 太郎さんが倒れたのは、2011年度の事業計画発表の翌日でした。彼が作成した事業計画を基に、とりあえず1年はうまくいったんです。でも2年目以降は彼の事業計画はありません。少しずつ経営が傾き始めたとき「放っておいたら、とりかえしのつかないことになる」という危機感を覚えました。
基本的に私は慎重な体質なので、何かを選択する際、その先にあるかもしれないネガティブな選択肢を考え、どの結果であれば許容できるかを考えます。
このときも、「自分が経営に参加して頑張った結果、会社がつぶれる」「完全に人に任せた結果、会社がつぶれる」、このどちらであれば受け入れられるかで悩みました。悩み抜いた末、後悔しない道として、経営に参加する選択をしました。
まず、太郎さんの後を引き継いだ新社長を支える役割として我究館に入りましたが、彼は本当に大変だったと思います。太郎さんから「絶対に会社をつぶすなよ」と言われていたそうで、家族としては「勝手なことを言ってごめんね」という申し訳ない気持ちでいっぱいでした。その責任は家族が背負うものと覚悟した次第です。