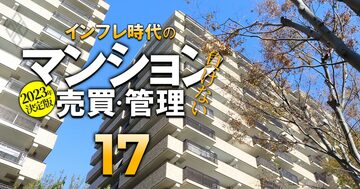Photo by Yoko Suzuki
Photo by Yoko Suzuki
湾岸タワマン、郊外内陸タワマン、外部管理者方式マンションと三つの種類が異なるマンションを渡り歩き、その二つで管理組合理事として活動、その後、戸建てに「転生」を選んだがすたま氏。さまざまな形態のマンション管理を見てきた同氏が実経験から「マンション管理のヤバさ」を寄稿で赤裸々に明かす寄稿の下編。特集『それでも買う!狂乱の市場に克つ! マンション 最強の売買&管理術』(全33回)の#22は内陸タワマンと外部管理者方式について取り上げる。(がすたま)
それ、詰んでない?廃墟リスク高めな
「郊外エリア×ペンシルタワマン」のコンボ
さて、今回は内陸タワマンのお話をしましょう。前回お話ししてきた、湾岸タワマンの運営の敵ともいうべき「アクティビスト」の存在よりもタワマン管理組合運営の観点からは、さらにマズそうなリスク要因を抱えるものが郊外にはあります。それが「郊外エリア×ペンシルタワマン」です。
私が現在居住する郊外エリアでは、駅前再開発とセットでタワマンが建築されるのがはやっています。マンションインフルエンサーが「駅前再開発タワマンは駅ナンバーワンで買い!」と取り上げるケースもよく見受けられます。
確かに後発のマンションでは得られないものがあるのは理解できます。しかし、私が気になっているのは、その手のタワマンって小ぶり、つまりペンシルなんです。そう、戸数が少ないのです。
なぜ戸数が少ないペンシルタワマンにはリスクが大きいのか。少し前に「湾岸タワマンが将来廃墟になる」説がまことしやかに喧伝されたことがありましたが、それとは少々異なるレベルの「ヤバさ」が内陸タワマンにはあるのです。それはいったい何なのか。次ページからデータと共にじっくり解説していきましょう。