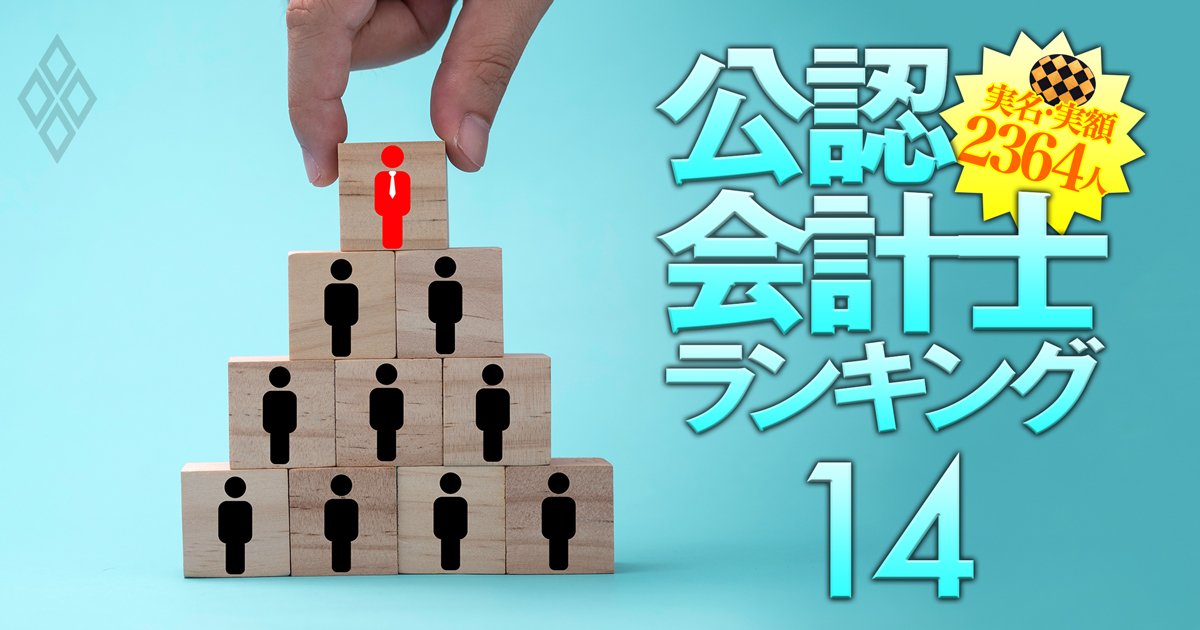これは放出備蓄米の9割を落札したJAのせいだという主張が巷に溢れている。JAはコメの価格が下がると販売手数料が減りビジネス的にはおいしくないので、「出し渋っているのでは?」と勘ぐられているのだ。
もちろん、JA側は否定して流通に時間がかかっているだけだと説明しているが、これから仮にJA以外の卸売業者が落札できたり、流通がスムーズになったとしても、コメの価格がすぐに安くなることはないだろう。
今回の備蓄米放出に「買い戻し制度」という奇妙なルールが設けられているからだ。
これは放出したコメを来年の新米収穫時に国が買い戻すというものだ。つまり、今回行われていることは「備蓄米放出」ではなく、正確には「国がコメを一時的に借した」とも言える。
つまり、これは来年の新米収穫時に「消えるコメ」なのだ。いくら21万トンが市場に行き届いたところで、卸売業者の頭の中には「どうせ来年はまたこれだけのコメが不足するんだな」という考えがあるので、品薄に備えてコメを手元にストックすることは避けられない。つまり、コメの取引価格が急に下がるということはないのだ。
そこで一部では「輸入米」が唱えられている。トランプ関税をめぐる交渉でも輸入米受け入れ拡大が検討されているという報道もあるが、もしこれを実行したら「減反政策にマジメに従ってきた農家」や、自民党の票田であるJAを完全に裏切ることになる。石破政権にそんな決断ができるとは思えない。
では、輸入米もダメ、備蓄米放出もダメとなると、普通に考えれば残された道は「減反政策の廃止」しかない。
これまで見てきたように日本のコメ農家が疲弊し、コメ価格が高騰していることの問題を辿っていくとは「減反政策」に辿り着く。なので、この政策を180度転換すればいい、という結論になるのは当然だろう。
どう考えても「減反廃止」なのに
農水省は絶対にやらない
つまり、コメの増産に力を入れる専業農家、大規模農業法人などを手厚い補助金で支え、国をあげてコメの増産に取り組み、輸出も拡大していくのである。
秋田県で減反政策に反対して「秋田の恥さらし」「闇米屋」などバッシングを受けた経験のある、大潟村あきたこまち生産者協会代表の涌井徹氏も、このように提言している。