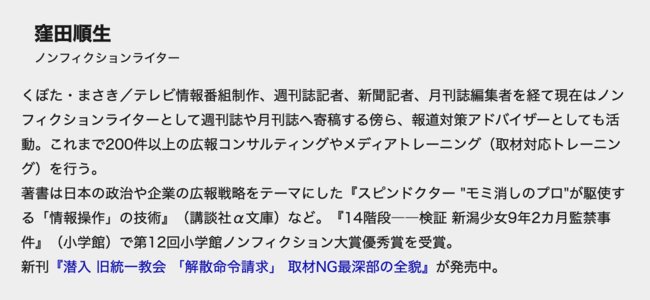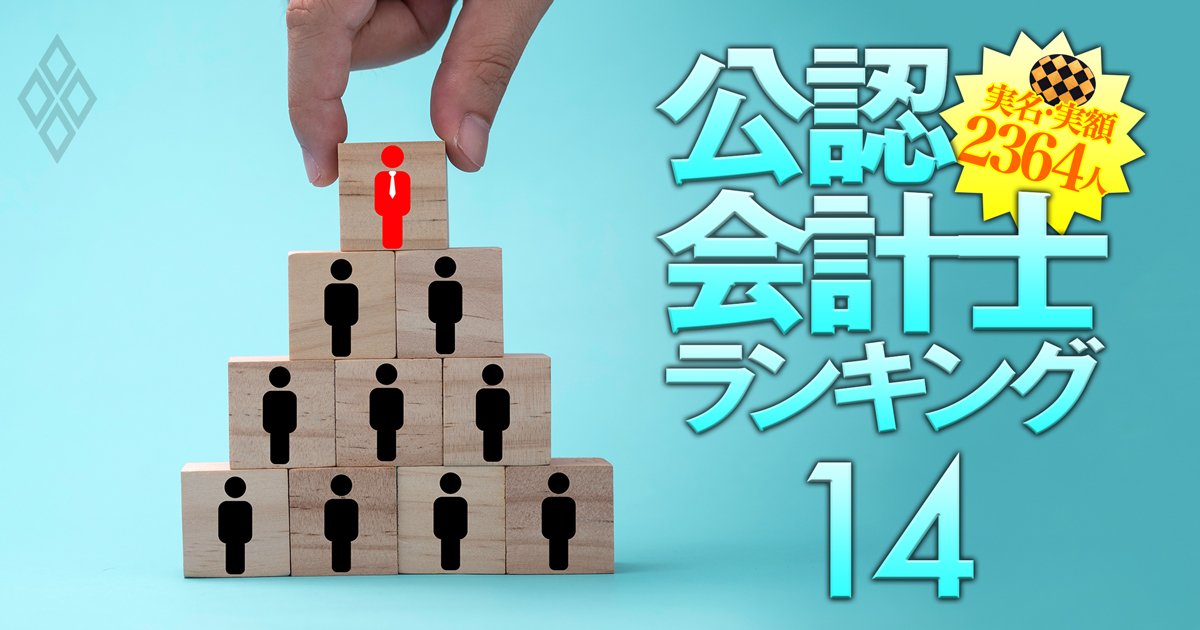この「詰み」という状態は、実は日本のあらゆる政策に当てはまる。代表は中小企業政策だ。
ご存じのように日本企業数の99.7%は中小企業が占めている。しかも、その約6割は社員が数名という小規模事業者だ。日本の労働生産性がOECD加盟38カ国中29位と低く、平均賃金が低いのは、中小企業の労働生産性と賃金が低いからだと指摘されている。だから、日本経済を上向かせるには、中小企業の生産性向上が必要不可欠ということを専門家も提言し、政府も認めてきた。
というわけで、成長する中小企業を積極的に国が支えていこうとなっているのだが、これがなかなかうまくいかない。一方で「成長しない中小企業も潰れないようにこれまでのように支えるべき」という声が多いからだ。
これまで50年近く、日本では「中小企業は国の宝」ということで、成長をしていなくても潰れそうな中小企業は補助金や優遇策などで支えてきた。そういう保護政策をいきなり打ち切るのは酷ではないかというのである。
成長する中小企業をどんどん応援したいが、成長しない中小企業の倒産を防ぐことも「平等」に力を注がなければいけない、となると結局、財源も限られているので、どちらも中途半端なままだ。だから、日本の中小企業の生産性はいつまでも向上しない。
この「詰み」状態はコメ政策も同じだ。今回のコメ高騰によってさまざまな問題が浮き彫りになってきて、国民の多くも「50年以上続いた減反政策」に何かしらの問題があると薄々勘づいてきた。
しかし、「50年以上続いた」ということは裏を返せば、この減反政策によって50年以上恩恵を受けてきた人々がいるということだ。減反政策によって家計を維持して、子ども育て上げて、老後の蓄えをしている人々が無数にいる。
そういう政策を簡単に「問題があるから転換だ」とはならない。特に政治家は選挙があるので票を減らす利権には手をつけられない。ああでもないこうでもないと論争をしても結局、稼げる農家も、稼げない農家もどちらも補助金を差し上げましょう、という「玉虫色の決着」に落ち着くはずだ。
よく「日本は変わらない」と言われる。そのことについては政治家が悪い、霞ヶ関官僚が悪い、と目の敵にされることが多い。だが、実は彼らがどうこうという以前に、我々国民の中にも「変わりたくない」を望む人たちがたくさんいるからでもあるのだ。
(ノンフィクションライター 窪田順生)