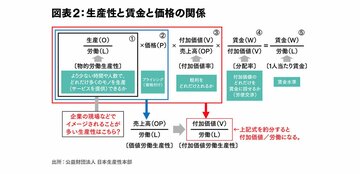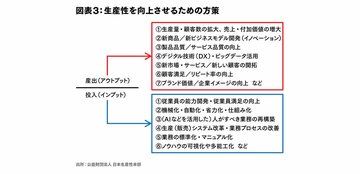誰もがデータを分析できる、デジタルドリブンカンパニーへ
大坪 DX(デジタルトランスフォーメーション)の実装が一段落し、これからは定着と深化のフェーズですが、それにはDXを使いこなせる人財の育成が不可欠です。どのように教育を進めていますか。
富永 700人のIT人財については、既にITのキャリアとスキルがあるので、現在の一番の課題は「使いこなす側」の育成です。今まであまりデジタルに触れてこなかった人を、どうやってデータ分析できる人にするか。そのためには「デジタルで課題が解決できた」という成功体験を積み重ねないと駄目だと思っています。デジタルだ、Eラーニングだ、という掛け声だけでは魂が入りませんから。
大坪 座学も大事にしつつ、現場での実践重視でやっていると。
富永 開発から販売まで情報を一気通貫させるモデルはここ4~5年で構築してきたものですから、さまざまなエラーもやはり起こります。こうしたミスを防ぐために、プロセスや権限管理の仕組みまできちんと見える化しようとしています。
また、いくら「Eコマースはロングテールだ」といっても、何でもかんでもごちゃごちゃと並べたり、セール品だけが目立ったりするようでは、ブランド価値が体験できません。どうすればブランドを訴求できるか。各地のベストプラクティスを見ながらより良くしていく。そうやってデータとは何か、オペレーションとは何かを社員全員が身に付けるようにしています。
マネジメント層も、何かにつけてダッシュボードを活用する習慣を身に付けようとしています。現地マネジャーとの1on1でも、こちらがダッシュボードを見ながら話しているのに、向こうが使っていないと話が擦れ違うので、都度、どんなデータを根拠に話しているかを明確にしながら対話しています。経営会議でも、世界に約600ある直営店のうち、今一番売り上げがいいのはここ、というような情報もパッと出せるようになり、議論の質が変わりました。
大坪 デジタルを活用する上で、今後の課題はありますか。
富永 バックエンドに関しては、在庫回転率の向上ですね。かなり改善してはいますが、まだ優位性があるといえるレベルではありません。ここはシステムだけじゃなく「人」が大事なので、昨年からCFO(最高財務責任者)の下にサプライチェーンマネジャー、需要予測担当者、生産計画担当者を付けて、データを活用しながら課題を一つ一つ解決している状況です。そして、成果が出たリージョンがあれば、ベストプラクティスとして全体に共有するようにしています。
フロントの部分も同様で、勢いのあるリージョンの役員レベルに「先頭を切ってチャレンジしてほしい」と積極的に伝えています。例えば、オーストラリアはマーケットシェアも非常に高く、優秀な社員がそろっているので尖った実験がしやすい。成果が出れば、それをうまく横展開していきたいと考えています。



 本社のある神戸で開催されたグローバルサミットの様子。ベストプラクティスの共有や、グローバルな視点から全体最適の議論をを行う 写真提供:アシックス
本社のある神戸で開催されたグローバルサミットの様子。ベストプラクティスの共有や、グローバルな視点から全体最適の議論をを行う 写真提供:アシックス
大坪 DXの導入フェーズでもそうでしたが「ベストプラクティスを共有して広げていく」というやり方が企業文化になりつつあるんですね。
富永 そうですね。年2回「グローバルサミット」という各リージョンのCEO(最高経営責任者)と日本の役員が集まって議論する場を設けていて、ここでさまざまなアイデアを共有しています。リアルに顔を合わせていると、それぞれが得意なことも分かってきますから「この人とこんなことをしたい」という共創が生まれる雰囲気になっていますね。