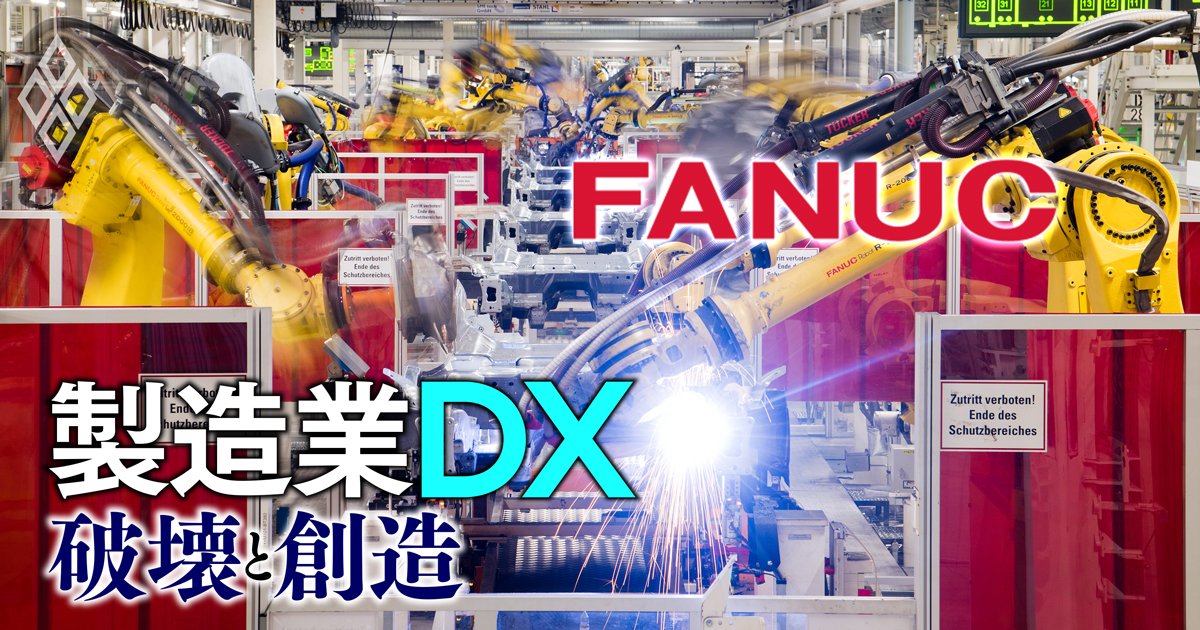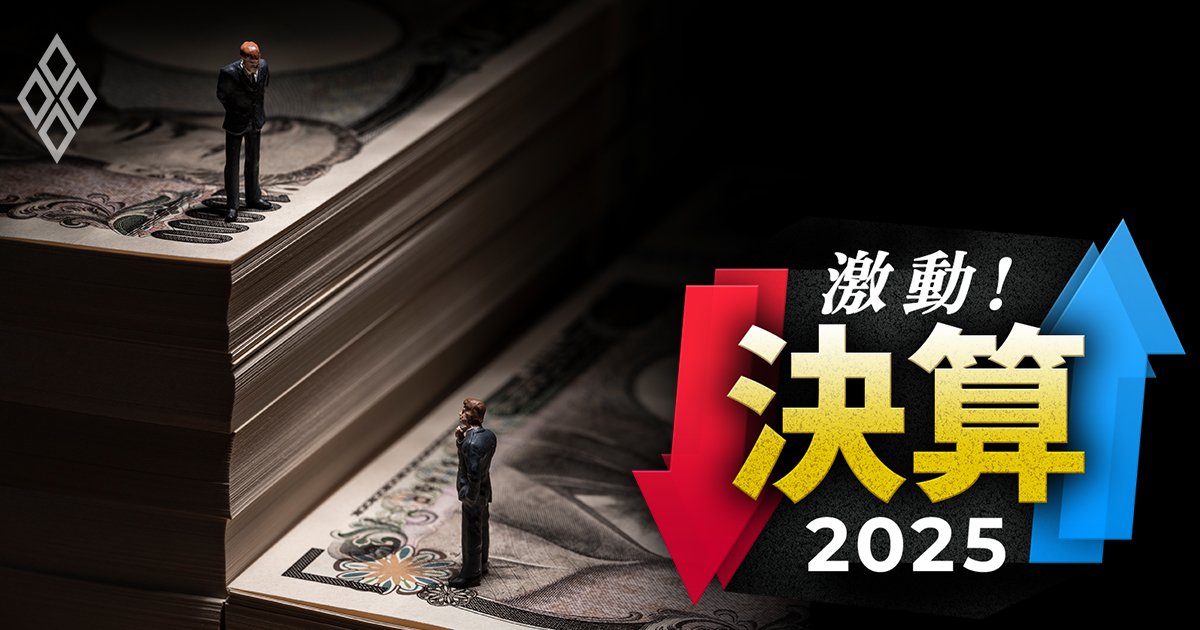新聞用紙の生産では国内4位の丸住製紙(四国中央市)が2月28日、負債総額約590億円を抱えて民事再生法の適用を申請した。愛媛県では過去2番目の大型倒産で、取引先や雇用への影響は小さくない。東京商工リサーチは丸住製紙の倒産前から取材を続けてきたが、4月以降、従業員の大規模な解雇や休止事業の再開延期など、再建の柱になるはずの事業からの撤退情報が駆け巡っている。「川之江の雄」と称された名門企業がなぜ行き詰まったのか。今後の再生計画はどうなるかを追いかけた。(東京商工リサーチ情報部 本間浩介)
事業環境が悪化
「私的整理」で自主再建を模索
丸住製紙は1919年7月、愛媛県金生町(現:四国中央市)で手すきの和紙業者として創業した。100年以上の歴史を背景に、紙の街として知られる四国中央市でも大王製紙と並ぶ企業として一目置かれる存在だった。戦後の1946年2月に法人化すると市内各地に生産拠点を展開し、ピークの2008年11月期の売上高は約743億3500万円をあげ、地方都市では大企業と認識させるには十分な存在だった。
その後、環境問題が注目され、ペーパーレス化が加速すると、2019年にペーパータオルやウェットティッシュなどの衛生用紙事業に領域を広げた。また、バイオマス発電や太陽光発電所を建設し、エネルギー事業にも進出した。ところが、コロナ禍での紙需要の落ち込みが想定以上に大きく、原材料高も直撃した。さらに、期待した発電事業もコスト高、石炭高騰で環境が一変した。
 丸住製紙の本社(TSR撮影)
丸住製紙の本社(TSR撮影)
丸住製紙は愛媛県を代表する1社だったが、最近は業績などの公表を拒否する姿勢を貫いた。ようやく窮状に陥っていた実態を口にしたのは、民事再生を申請後の債権者説明会だった。
経営の行き詰まりの発端は、石炭価格の高騰などで2022年11月期に約120億円の純損失を計上したことだった。2023年4月に借入先の金融機関16行に元本返済猶予(リスケジュール)を要請し、私的整理手続きに着手した。この私的整理手続に沿って、2023年11月に自主再建を目指し、リスケ型の事業再生計画案を策定した。この計画案は同年12月に借入先全員の同意を得て成立している。