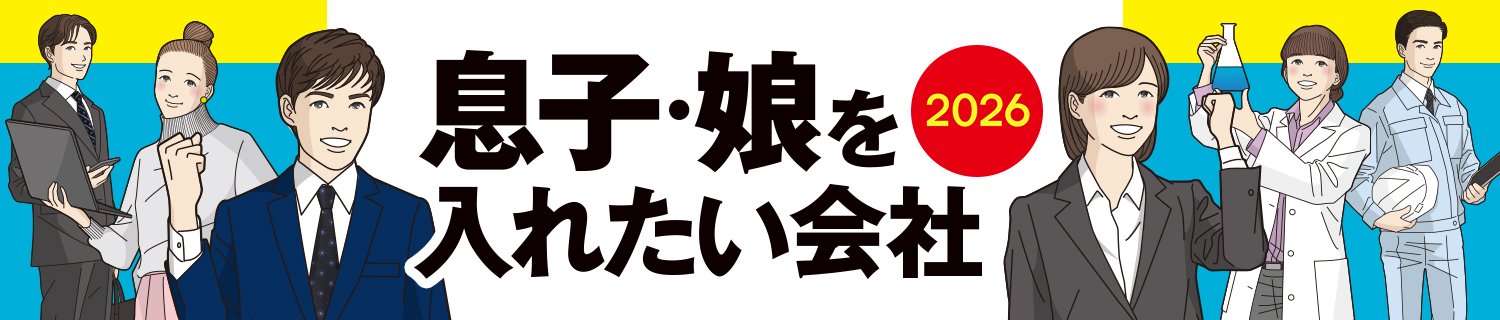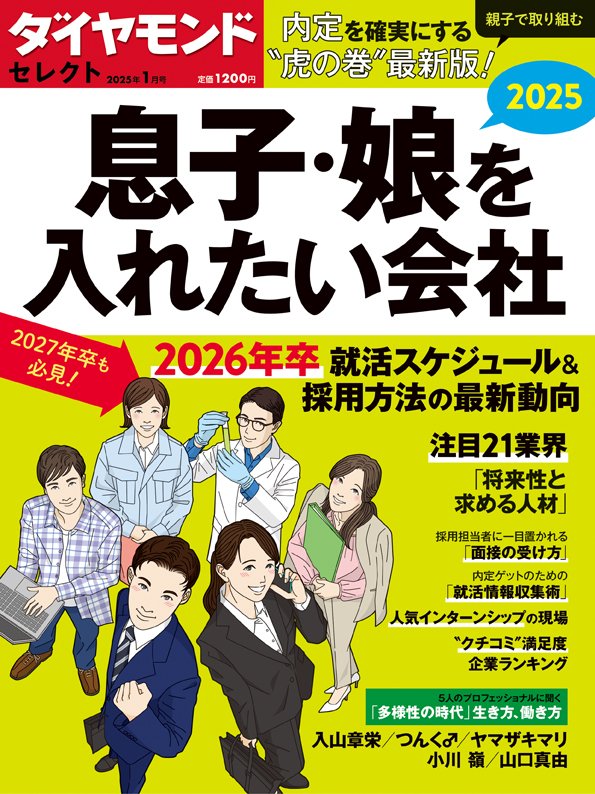マーケティングなどの
「文系人材」の需要が高まる
近年、自動車は「走る電子機器」と化し、EV(電気自動車)ではモーターやインバーター、バッテリーなどの電子部品を高効率に統合する「システムインテグレーター力」が求められている。
日本は個別技術に強みがある一方、欧州勢に比べてシステム全体の最適化では後れを取っており、今後は共通アーキテクチャを軸にしたプラットフォーム競争の時代に突入する。
かつて政府支援により急成長した日本のEV市場だが、現在はインフラ不足や高価格、航続距離不安に加え、製造・廃棄まで含めた二酸化炭素排出量の多さから成長が鈍化しているという見方もある。こうした背景から、ガソリンと電気の利点を併せ持つHV(ハイブリッド車)やPHV(プラグインハイブリッド車)が再評価されている。
注目市場はインドだ。人口は中国を超え、世界最大の自動車市場に成長する可能性が高い。日本ではスズキが強いが、現地戦略に優れたヒュンダイが急伸。特に同社は韓国の大学と連携してインド市場を徹底分析しており、マーケティング力に秀でている。これは、韓国市場が小規模なため海外志向が強く、戦略が洗練されていることに起因する。
一方、日本企業は国内で460万台が安定して売れることに甘え、海外戦略で後手に回る傾向がある。しかし、高齢化と人口減少による国内市場の縮小が避けられない中、海外展開は今後の成否を左右する重要な鍵となる。
海外勢では中国のBYDも存在感を増している。若年層や女性を中心に人気が高まり、ドイツ車出身のデザイナーを起用した欧州風の洗練されたデザインと価格の安さが支持の背景にある。
こうした業界構造の変化により、今後は技術者だけでなく、マーケティングなどの「文系人材」の需要が高まっている。EVやPHVの魅力をどう伝え、市場に浸透させるかはマーケティングの力次第だ。
グローバル戦略で成果を挙げているトヨタの例を見ても、現地適応力と戦略構築力が企業の明暗を分ける。自動車会社の提携は「競争から共創」への転換を象徴しており、今後の自動車業界は技術力のみならず、組織力とマーケティング力を総動員した総合戦に突入する。
*この記事は、株式会社大学通信の提供データを基に作成しています。
医科・歯科の単科大等を除く全国757大学に2024年春の就職状況を調査。561大学から得た回答を基にランキングを作成した。上位10位以内の大学を掲載。就職者数にグループ企業を含む場合がある。大学により、一部の学部・研究科、大学院修了者を含まない場合がある(調査/大学通信)