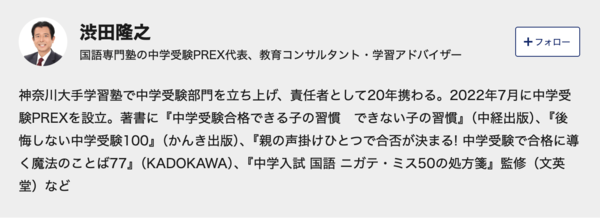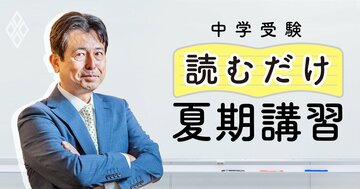Key Visual by Ayumi Ogawa / Photo:PIXTA
Key Visual by Ayumi Ogawa / Photo:PIXTA
「塾の季節講習に通わせているのに、全然身についてない気がする…」。そんな不安を感じたことはありませんか? 実は、夏期講習を“なんとなく受けている”だけでは、時間もお金もムダになることも。子どもの様子をちょっと見るだけで気付ける「夏期講習の落とし穴と対処法」を、受験指導のプロがお伝えします。(国語専門塾の中学受験PREX代表、教育コンサルタント・学習アドバイザー 渋田隆之)
夏期講習の失敗を防ぐ
3つのポイント
計画的に学習に取り組めば、志望校との偏差値の差を埋めるには十分な時間が夏休みにはあります。塾は夏休みに行う夏期講習のことを「受験の天王山」と呼びますし、この時期の勉強のやり方によっては、9月以降の成績に大きく影響が出ることも事実です。
しかし、夏期講習を上手に生かせない場合は、時間と費用を無駄にしてしまいます。時には挽回不可能になることもあります。今回は、「夏期講習の失敗を防ぐ3つのポイント」を紹介します。
(1)授業をしっかり受けられているか?
大手塾の夏期講習は、長時間であることがほとんどです。しかし、設定されたスケジュールになんとなく乗っかり、ただ塾に通えばいいというわけではありません。
「わが子がそんなに長い時間、集中し続けることができるか?」という懸念は持っていた方が良いでしょう。
特に、一番頑張って授業を受けてほしいはずの苦手科目の授業中に、ぼーっとしてしまう可能性があるからです。できれば、2回目の授業が終わったあたりで、テキストやノートの書き込みを見てみましょう。頭を使った形跡がないようであれば、早めに修正が必要です。
家に帰ってきてから「復習をしなさい」と言ってみてもなかなか子どもが動かない時に、「どこを復習したらいいかさえ分かっていない」という怖いケースもあるからです。
(2)担当の先生との相性は?
夏期講習は、ほぼ全学年の生徒が通塾するので、講師の数は普段より多く必要となります。通常授業の担当の先生がそのまま授業をする場合は問題ないのですが、講習は別の先生が担当するというケースもあります。
講師同士の連携が取れていれば問題ありませんが、子どもの普段の様子を知らない先生がいたり、特に算数や国語は教え方や解き方が変わることで理解の妨げになってしまうことがあります。
これは初回の授業が終わった後、子どもに「どういう先生に習っているか?」を聞いてみると良いでしょう。
また、講師にどうしても知っておいてほしい情報については、教室長を通じて伝えておきましょう。例えば、「眼が悪いので板書を大きな字で書いてくれないと読めない」といった小さなことでも、初対面の大人には自分から言えない子どもがいたりするものです。
(3)宿題の量は適切か?
塾には決まったカリキュラムがあり、配られるテキストは夏期講習中に消化するように決まっています。ところが、これは理解力のある最上位クラスの進度に合わせて作成されていることが多いため、基礎クラスでは“駆け足”になってしまいます。
本来なら、しっかりと理解してもらうために時間をかけてあげたいところですが、それだとカリキュラムが終わりません。手をつけない単元がたくさん残ってしまうと、保護者からクレームをいただくことがあるので、「残ったところは宿題でカバーする」というケースが散見されます。
解説が十分でないところの演習問題が宿題に出たり、他教科の勉強時間を圧迫するような量の宿題が出たりした場合は、塾に相談した方が良いでしょう。子どもの状況に合わせて、必ずやるべき宿題とそうでない宿題を指定してもらえることもあります。
夏期講習で現実的に起こりうる「怖い話」をお伝えしました。家に帰ってきてから、なかなか勉強に身が入らない子どもにヤキモキする前に、親が「夏期講習は、何をどんな風に習っているんだろう?」ということを気にするようにするだけで、夏期講習の成功確率が確実に上がります。
なお、大手塾の夏期講習のテキストは、全範囲がコンパクトにまとまっていますので、入試直前まで十分に使える素晴らしい教材でもあります。
夏期講習でやり切れなかったところ、理解が不十分なところがあるのは当然と考え、「ここは出来た、ここは出来なかった」ということが明確に分類できていれば、「本人オリジナル最強の教材」となります。