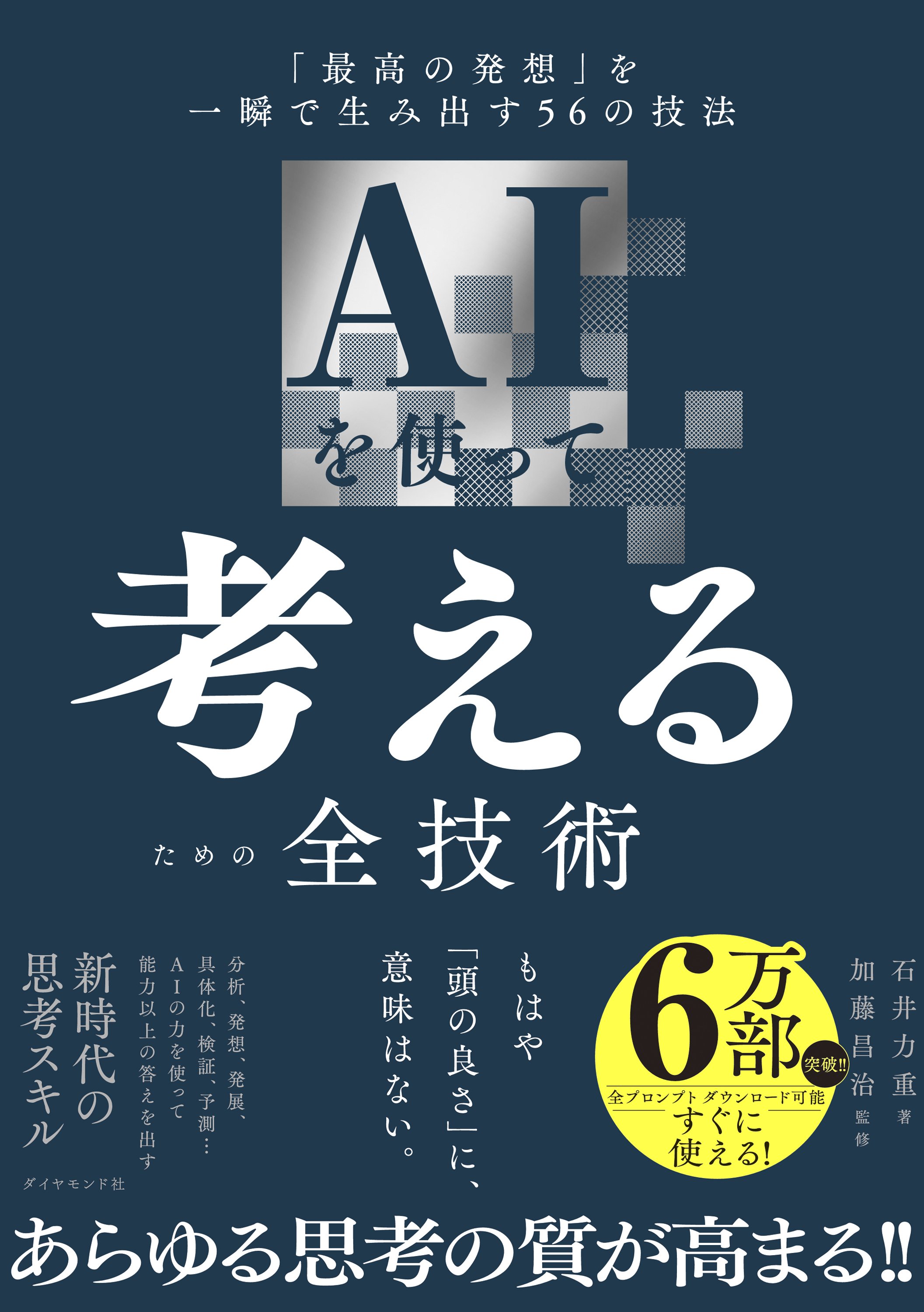大分県のみかん農家が始めた生みかん100%ジュースの通販事業における初期の顧客獲得戦略は、製品の魅力を最大限に伝え、潜在的な顧客にリーチすることが重要です。以下に優秀な起業家の立場から具体的な提案をいたします。
ストーリーテリングを活用したブランディング
みかん農家の歴史、農園の特徴、製品への情熱などを紹介することで、消費者に製品の背景を感じさせ、感情的なつながりを築きます。これはウェブサイト、SNS、パッケージング、プロモーションビデオなどで展開できます。
ソーシャルメディアマーケティング
Instagram、Facebook、X(旧Twitter)などのプラットフォームを活用して、製品の魅力や使用シーンを美しい写真や動画で紹介します。また、ハッシュタグキャンペーンやフォロワーとの積極的なインタラクションを通じて、口コミを促進します。
インフルエンサーマーケティング
食品、健康、地域活性化に関心を持つインフルエンサーと協力し、製品レビューや紹介をしてもらうことで、信頼性とリーチを増加させます。
サンプル配布や体験型イベント
地域のイベントやフェア、ファーマーズマーケットでのサンプル配布を通じて、直接消費者と接点を持ち、製品の品質を体験してもらいます。また、オンラインでの試飲イベントも有効です。
特別オファーと限定キャンペーン
初回購入割引、定期購入オプション、友達紹介プログラムなど、購入を促すための特別オファーやキャンペーンを実施します。
SEOとコンテンツマーケティング
オーガニック検索からの訪問者を増やすために、SEO対策を施したコンテンツ(ブログ記事、レシピ、製品情報)をウェブサイトに定期的に投稿します。
メールマーケティング
サイト訪問者からメールアドレスを集め、ニュースレターを通じて新製品情報、限定キャンペーン、製品の舞台裏など、魅力的なコンテンツを定期的に提供します。
地域コミュニティとの連携
地元のレストランやカフェ、ホテルと連携し、地域産品としてのみかんジュースを提供してもらうことで、地域住民や観光客にリーチします。
これらの戦略は相互に補完し合い、製品の認知度の向上、顧客基盤の拡大、そして売上の増加に寄与します。重要なのは、ターゲット市場を正確に理解し、それに合った戦略を選択し、柔軟に調整することです。
「インフルエンサーマーケティング」。有効な一手だと思いますが、そこだけを頼りにするのは危険ですよね。
「地域コミュニティとの連携」。ちょっと光るものを感じます。大分県は「おんせん県」と打ち出すほど、温泉を楽しめる環境があります。たとえば銭湯で風呂上がりに飲むフルーツ牛乳のように、「温泉から出たら、冷えたみかん100%ジュース」みたいな体験を提案するとか。通販で買えるものとは少し異なっていて、ご当地でしか飲めない(保存に向かない)フレーバーとかで希少性を出せたりすると話題になりそうです。そして、そのみかんジュースは通販でも買えます、とか。
このように参考にはなるのですが、他県のみかん農家でも実践できそうなアイデアではあります。もう少し「大分のみかん」という固有性を活かしたいところ。
ただ、AIは有名な案件についてのデータは持っているものの、そうでないニッチな案件については情報を保持していないこともあります。その場合、一般的な回答で終わってしまうことがよくあります。そんなときは、いったんAIに理解を深めてもらうようにしましょう。AIから適切な回答を得るために、こう聞いてみます。
「大分県」の「みかん」の特長や弱点としてはどんなものがありますか? また、このみかんをとくに好むファンはどういう人たちですか?
商品に関する情報を調べてもらうことで、いったんAIに「大分のみかん」のことを知ってもらいます。
大分県のみかんは、独自の気候と地理的条件に恵まれた地域で栽培されており、特有の特長と弱点があります。また、これらのみかんをとくに好むファンには特定の特徴があります。
大分県みかんの特長
・高品質:温暖な気候と肥沃な土壌が組み合わさっており、みかんの品質を高めます。糖度が高く、果汁が豊富で、甘味と酸味のバランスが良いことが特長です。
・独特の風味:大分県の特定の地域では、土壌の成分や気候がみかんの風味に独特の特徴を与えます。これにより、他地域のみかんとは異なる、特有の味わいを楽しむことができます。
・多様性:大分県ではさまざまな種類のみかんが栽培されており、早生種から晩生種まで、季節を通じて多様なみかんを楽しむことができます。
大分県みかんの弱点
・生産量の変動:天候による影響を受けやすく、とくに台風や長雨などの悪天候は収穫量に大きな影響を与えることがあります。
・流通の課題:地域ブランドとしての認知度が全国的にまだ低い場合があり、流通チャネルの確立やブランド力の向上が求められます。
・競合との差別化:全国の他地域でも高品質なみかんが栽培されているため、大分県のみかんが独自の特長を打ち出し、消費者に選ばれるための差別化が必要です。
このみかんをとくに好むファン
・健康志向の消費者:高い栄養価と自然な甘さを求める健康意識の高い人々は、添加物を使用していない自然な味わいの大分県のみかんを好む傾向にあります。
・グルメな消費者:独特の風味や品質を重視するグルメな人々は、特定の産地にこだわり、その地域特有のみかんを楽しむことを好みます。
・地域産品を支援する消費者:地元産品への支援意識が高い消費者は、地域の農家を支援し、地域経済に貢献するために、大分県産のみかんを選ぶことがあります。
大分県のみかんを市場に打ち出す際には、これらの特長を前面に押し出し、弱点をカバーする戦略を練ることが重要です。また、特定のターゲット層にアピールするマーケティング戦略を展開することで、より多くのファンを獲得できるでしょう。
大分のみかん、おいしそうですね。台風が多い九州では天候の影響を受けやすいのであれば、早生や晩生にシフトして、出荷需要以上の部分はみかんジュースに加工して出荷を安定させていくなど、産業の6次化は可能性があるのだろうと思います。
AIに「大分県みかんの固有性」を情報として保持してもらったところで、再度、顧客獲得について聞いてみます。
そうしたことを踏まえて、具体的な「初期の顧客獲得の方法」を考えてください。
継続したスレッドであれば、「そうしたこと」の一言で、ここまでの経緯を一括することができます。便利ですね。
大分県独自の要素を活かした初期の顧客獲得方法をより深く掘り下げて検討します。大分は温泉県としての知名度が高く、豊かな自然環境と地域文化があります。これらの特性を踏まえ、大分県のみかんとその100%ジュースの通販事業に独特の魅力を加えるアプローチを考えてみましょう。
温泉との連携
・温泉施設でのみかんジュース提供:大分県の豊富な温泉施設と連携し、温泉地の宿泊客に向けてみかんジュースを提供します。とくに、温泉後のリフレッシュドリンクとして、またはウェルカムドリンクとして提供することで、訪問者に特別な体験を提供します。
・温泉地限定パッケージ:大分の有名な温泉地をイメージした特別デザインのパッケージを制作。温泉地の土産店やロビーでの販売を通じて、訪問者に対する記念品としての魅力を高めます。
地域文化との融合
・地元の祭りやイベントでのプロモーション:大分県固有の祭りやイベントに参加し、みかんジュースの無料配布や試飲ブースを設置。地元の文化と結びつけることで、県民のみならず訪問者にも愛されるブランドを目指します。
・地元アーティストとのコラボレーション:大分県出身のアーティストやデザイナーと協力し、限定エディションのラベルデザインを制作。地域の芸術を支援するとともに、製品の独自性を高めます。
自然環境を生かした体験
・みかん畑のツアー:消費者を対象としたみかん畑の見学ツアーを企画。みかんの栽培方法や収穫体験を通じて、製品への理解と親しみを深めます。
・オンラインでの農園体験:農園での日常やみかんの収穫風景をライブ配信や動画で共有。遠方の顧客も大分の自然と農業に触れることができます。
独自性を活かした商品開発
・温泉水を使用したみかんジュース:大分県の温泉水を活用した、新しいタイプのみかんジュースを開発。温泉水のミネラルが加わることで、他では味わえない特別な味を実現します。
これらのアプローチは、大分県の独特な地域資源を生かし、みかんジュースの魅力を全国にアピールするためのものです。大分にしかない要素を通じて、消費者に新しい価値を提供し、ブランドの独自性と地域への貢献を強調することが重要です。これらの戦略を通じて、初期の顧客獲得と長期的なブランドロイヤルティの構築を目指します。
「温泉水を使用したみかんジュース」には大いに惹かれました。「100%はキツい」という方には、付属の温泉水ボトルでお好みに割ってもらえるようにするとか。話題性で初期の顧客を獲得するという点では検討するに値するでしょう。
他にも、大分に来た旅行者に強く訴求する案が多く出ました。宿泊施設とのタイアップなどもできれば、旅行中だけでなく自宅に帰った後も顧客化が可能かもしれません。
なおプロンプトに入力する情報のボリュームや濃度と比例して、AIがあげてくれる初期の顧客獲得戦略も変わってきます。また、経験値が少ないと自覚している分野での打ち手については「さらに具体的にして」とか「バリエーション案も出して」という指示をすると、さらなる具体策を手にすることができます。苦労しがちな初期の顧客獲得も、「安売り」して大量出血する以外の方策が見つかるはずです。
(本稿は、書籍『AIを使って考えるための全技術』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。この他にも書籍では、分析、発想、発展、具体化、検証、予測といった“頭を使う作業”にAIを活用する方法を多数紹介しています)