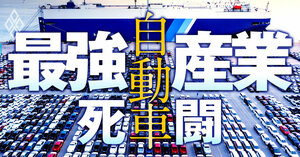「知識創造を促進するためにカオスを受け入れ、奨励する」
論文では、今日のビジネス環境が「絶えず動き、予測が難しい性質」を持っているため 、組織は「先が読めず、混乱した状況の中で、うまく知識を管理していかなければならない」と述べている 。
また、組織が持つ知識を効果的に活用する「知識管理」において、カオス(予測できない状況)がどのような役割を果たすのかを明らかにするために、3つの重要な点から議論を進めている 。
1つ目は、知識そのものが明確ではなく、あいまいな性質を持っていること。
2つ目は、会社やチームのやり方の中に、わざと「ごちゃまぜ」な状態や、何が起こるか分からないような要素を取り入れること。
3つ目は、常に新しいことを生み出すような、変化の多い会社で、知識をどう生かしてきたかという点である。
論文では、次のように記されている。
《知識は常に動き、発展し、変化する存在として定義されてきた 。個人が互いに、あるいは文書化された知識とつながるにつれて、この知識を開発し、変換し、自身の知識ベースに適応させる》
《創造のプロセスと創造性そのものは、実験が可能であり、型破りであることや規範に逆らうことが奨励される、開放的で柔軟な環境を必要とする 。知識創造における柔軟性と適応性の必要性は、イノベーションに関する文献で確立されている》
《知識マネージャーの役割は、知識創造を促進するためにカオスを受け入れ、奨励することである》(いずれも『創造性、カオス、そして知識管理』より)
京セラやKDDI、日本航空のように変化の激しい環境で成功を収めてきた企業が、いかにして混沌を管理し、知識創造を促進してきたかという稲盛氏の思想を、アカデミックな視点から裏付けるものと言える。
論文は、知識創造には柔軟で開放的な環境が必要であり、非正統的であることや規範に逆らうことが奨励されるとしている 。さらに、知識マネージャーの役割は「知識創造を促進するためにカオスを受け入れ、奨励すること」であると提言している 。