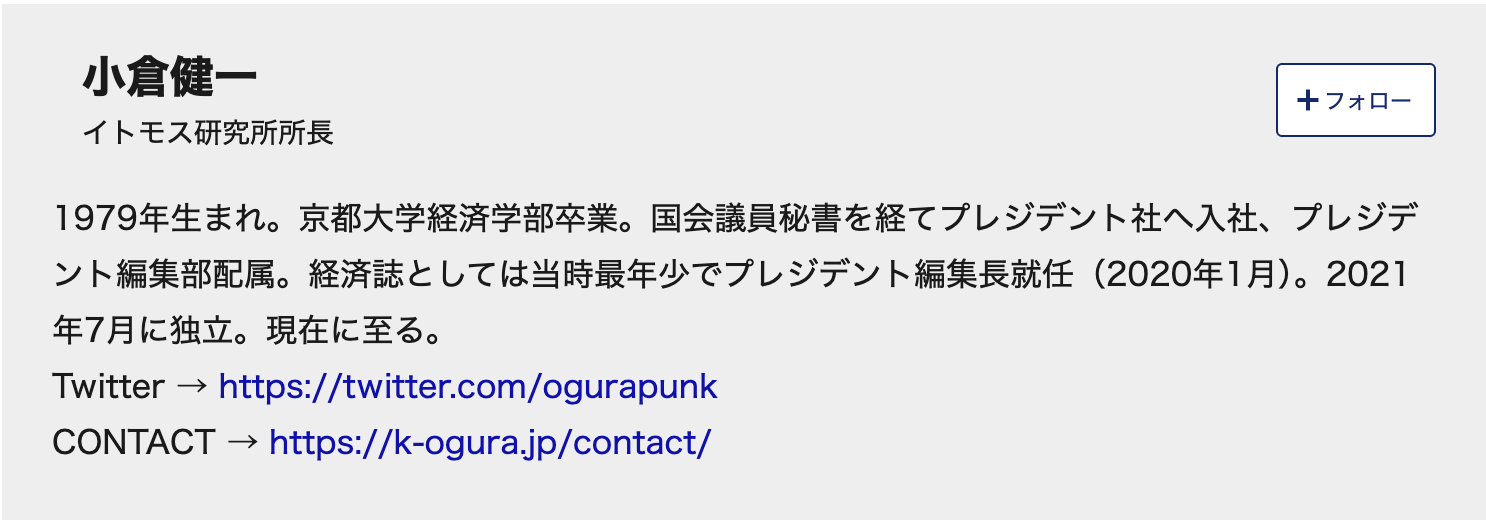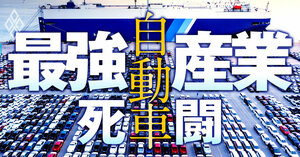メディアにも「朝令暮改」の精神が必要
デジタル化が進み、情報のライフサイクルが極めて短くなった現代において、メディア(もちろん、メディア以外の産業においても)はこれまで以上に「稲盛流 朝令暮改」の精神を必要としているのではないか。
読者のアクセスデータやSNSの反応など、読者の動向はリアルタイムで把握できる。これらを分析し、コンテンツの方向性やテーマを柔軟に調整していくことが求められる。
有料オンラインメディア、あるいは無料のオンラインメディアの歴史は、紙媒体に比べればごく最近のものである。しかし、この短い期間に驚くべき速度で変化し、成長してきた。
これらのメディアが成功しているのは、読者の「今、知りたい」というニーズに対し、速く、深く、そして多角的に情報を提供しているからである。彼らは、固定的な「ウェイ」ではなく、常に「最善の情報提供とは何か」を問い続けている。
少なくとも「我が社のウェイ」なるものは、一部につかんだ経験があったとしても、永久に完成されるものであってはならないはずだ。
過去の成功体験に縛られるのではなく、変化する読者のニーズと向き合い、データに基づきながらも、新たな価値やまだ見ぬニーズを掘り起こすための柔軟な方針転換こそが、新しい「道」を創造する力となる。
有料の読者を獲得できないと悩んでいるメディアは多いが、それは過去の道にとらわれているケースが多い。
固定された「ウェイ」にしがみつくことは、停滞を意味する。しかし、知のカオスこそが未来を切り拓くための強力な武器となる。稲盛氏の朝令暮改は、腹心によってこう解説されている。
《企業の経営は将棋を指すようなもので、社長は将棋の指し手である。その駒組(組織)と駒(人)の活用いかんによって勝敗が決まる。いつも同じ駒組では相手(外界の情勢)の変化によって敗れる。
相手をよく知り、最も自分の得意とする陣形で戦うように駒組しなければならない。朝令暮改、大いによろしいと言い換えねばならない。初めの考え方が浅かった割りは免れないが、その時点で最善と思い、決定したものが、現時点で悪くなったと思えば、素早く改めることが大事である。
稲盛は即決し、悪いと思えば、即改する。面子にこだわり、良くないと思いながら続けるようなことは絶対にしない。何十年も前に決められた政令がいまだ改められず生きているのとは、雲泥の差である。「朝令暮改」大いによろしい》(『心の京セラ二十年』)
企業の歴史は、常に消費者の興味や社会の動きに寄り添い、変貌を遂げてきた歴史でもある。
「変化への適応力」を、企業が、そしてメディアが意識的に実践することこそが、今後進むべき「ウェイ」を示す羅針盤となるだろう。