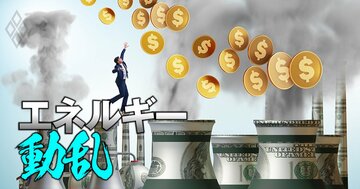関西電力の美浜原子力発電所 Photo:PIXTA
関西電力の美浜原子力発電所 Photo:PIXTA
原子力発電を巡り、関西電力は次世代革新炉の建設へ向けて福井県美浜町で地質調査などを再開すると発表した。一方、原子力規制委員会は北海道電力の泊原発3号機の再稼働につながる設置変更許可を交付した。長期連載『エネルギー動乱』の本稿では、二つの動きが持つ、真の意味について掘り下げる。実は、関電の動きはアドバルーンの域を出るものではない。その二つの理由を解説する。(国際大学学長 橘川武郎)
関西電力が次世代革新炉建設へ向け
福井県・美浜で地質調査を再開
日本では、最近、原子力発電を巡って、二つの大きな動きがあった。一つは、関西電力が、次世代革新炉の建設へ向けて、福井県美浜町で地質調査等を再開すると発表したことであり、もう一つは、原子力規制委員会が、北海道電力・泊原子力発電所3号機の再稼働につながる設置変更許可を交付したことである。これら二つの動きは、今年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画が強く打ち出した「原発回帰」の流れを具現化したものと広く受け止められており、一部にはわが国の原子力の未来を開くものと高く評価する向きもある。
しかし、本当にそうだろうか。本稿では、二つの動きが持つ、真の意味について掘り下げる。
関西電力は7月22日、福井県にある美浜原子力発電所の敷地内で、次世代革新炉への建て替えに向けて、地質調査などを再開することを、正式に発表した。
ここで、「再開」という言葉を使うのは、同社が2010年11月に、老朽化した美浜原発1号機の後継炉の設置に向け、地質や動植物の状況などの調査に乗り出したことがあるからである。しかし、その時の調査は、開始から4カ月後に発生した東京電力・福島第一原子力発電所事故の影響で中断されることになった。そして、美浜原発の1号機と2号機は、2015年4月に廃炉となることが決まった。
今回、関西電力が着手を発表した地質などの調査は、原発の新設に向けた最初のプロセスに当たる。もし、原発の新増設が実現すれば、福島第一原発事故以降、初めてのケースとなる。
関西電力は、7月22日の記者発表の際に、この地質などの調査の結果だけで次世代革新炉の建設を判断するものではないと強調している。また、同日、会見に臨んだ同社の森望社長は、次世代炉の運転開始時期について、「今の時点で申し上げることは難しい」と述べている。
それもそのはず、今回の関西電力の発表は、世論や関係者の反応を探る“アドバルーン”に過ぎないからである。そう断じるのには、二つの理由がある。