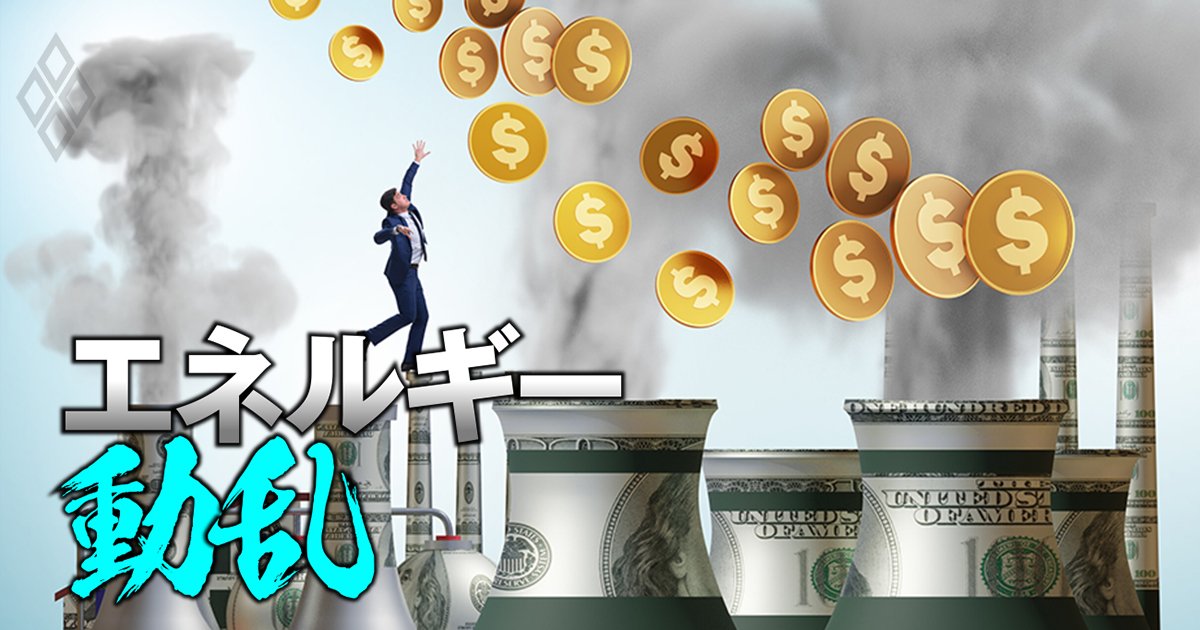 Photo:123RF
Photo:123RF
第7次エネルギー基本計画(エネ基)は、天然ガスに極めて高い位置付けを与え、「天然ガスはカーボンニュートラルの実現後も重要なエネルギー源である」とまで言い切った。だがどのようにすれば、カーボンニュートラルの実現と天然ガスの使用継続とは両立するのだろうか。長期連載『エネルギー動乱』の本稿では、第7次エネ基が内包する矛盾を解消するためのヒントを明らかにする。(国際大学学長 橘川武郎)
コペルニクス的な大転換
「CN実現後も天然ガス使い続ける」
2025年2月、第7次エネルギー基本計画(エネ基)が閣議決定された。この計画について、25年3月4日に本欄(DIAMOND online『エネルギー動乱』)で発信した拙稿『エネルギー基本計画はトランプ再選で「重大なアレンジ」が急遽加えられた…脱炭素後退で重要になるエネルギー源とは』では、(1)複数シナリオからなるベースシナリオよりも、単一シナリオであるリスクシナリオの方が、エネルギー業界の関係者のあいだでは「本命視」されている、(2)そのリスクシナリオでは、とくに天然ガスの役割が重視されている――という2点を強調した。
まず、これらのうちの(2)に関して、詳しく見ておこう。第7次エネ基は、天然ガスに極めて高い位置付けを与え、「天然ガスはカーボンニュートラル(CN)の実現後も重要なエネルギー源である」とまで言い切った。
具体的に言えば第7次エネ基は53ページで、「天然ガスは、熱源として効率性が高く、地政学的リスクも相対的に低く、足下、電源構成の約3割を占める。また、化石燃料の中で温室効果ガスの排出が最も少なく、再生可能エネルギーの調整電源の中心的な役割を果たすと同時に、燃料転換等を通じた天然ガスシフトが進むことで環境負荷低減にも寄与する。さらに、将来的な技術の進展によりガス自体の脱炭素化の実現が見込まれ、水素等の原料としての利用拡大も期待される等、カーボンニュートラル実現後も重要なエネルギー源である」と述べている。
もちろん、天然ガスから合成メタン(eメタン)への転換(=「ガス自体の脱炭素化の実現」)の重要性にも言及しているものの、この文章の主語はあくまで「天然ガス」それ自体であり、修飾語を加えた述語は「カーボンニュートラル実現後も重要なエネルギー源である」なのである。
第7次エネ基のこの文章の持つインパクトは大きい。なぜなら、これまでは、日本ガス協会が発表したロードマップにおいても、政府の公式文書(例えば、経済産業省「『トランジションファイナンス』に関するガス分野における技術ロードマップ」、22年2月)においても、カーボンニュートラルが実現した暁には、天然ガスは使われなくなるという見通しが示されてきたからである。
ところが、第7次エネ基はこの見通しを真っ向から否定し、「天然ガスはカーボンニュートラル実現後も重要なエネルギー源である」とした。「コペルニクス的」とまではいわないにしても、大きな転換であることには間違いない。







