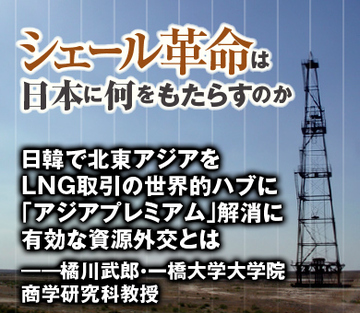橘川武郎
東京電力ホールディングスの「柏崎刈羽原発6号機」の再稼働を評価することはできる。しかし日本の原子力政策やエネルギー政策を「再起動」させるほどの、画期的な出来事だといえるだろうか。
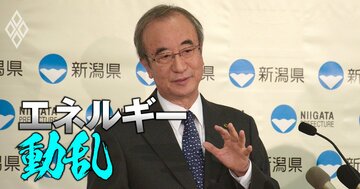
2025年10月21日、自由民主党と日本維新の会の連立政権として、高市早苗内閣が発足した。高市政権のもとで、日本のエネルギー政策は、どう変わるのか?本稿では、この論点を掘り下げる。

原子力発電を巡って、二つの大きな動きがあった。一つは、関西電力が次世代革新炉の建設へ向けて福井県美浜町で地質調査等を再開すると発表したことであり、もう一つは原子力規制委員会が北海道電力の泊原発3号機の再稼働につながる設置変更許可を交付したことである。本稿では、二つの動きが持つ、真の意味について掘り下げる。

日本ガス協会は新しい長期ビジョンとして、「ガスビジョン2050」を公表した。旧ビジョンではカーボンニュートラル実現後は天然ガスを使わないとしていたものを、新ビジョンではカーボンニュートラル実現後も天然ガスを最大50%まで使い続けると、大胆に方針転換したわけである。なぜこのタイミングで打ち出したのか。

第7次エネルギー基本計画は、天然ガスに極めて高い位置付けを与え、「天然ガスはカーボンニュートラルの実現後も重要なエネルギー源である」とまで言い切った。だがどのようにすれば、カーボンニュートラルの実現と天然ガスの使用継続とは両立するのだろうか。
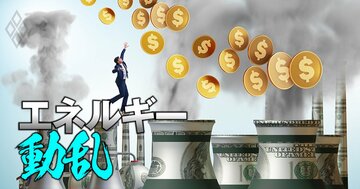
2025年2月、日本で第7次エネルギー基本計画(エネ基)が閣議決定された。実は、それは25年1月にドナルド・トランプ氏が米国の第47代大統領に就任したことと密接に連動している。この二つの事象が密接に連動していることを表す、エネ基に盛り込まれた「アレンジ」について解説する。また、国内の電力大手やガス大手などへの影響にも言及する。

#13
石油、化学、鉄鋼、電力の集積地であるコンビナートが岐路に立たされている。日本は2050年に向けて地球温暖化ガスの排出を実質ゼロとする方向にかじを切ったが温暖化ガスの9割を占める二酸化炭素(CO2)の4割は電力部門、3割は産業から排出されており、その過半が鉄鋼や化学などの産業を抱え、火力発電所を擁するコンビナートから排出されているからだ。特に化学産業はこの脱炭素対策に加え、過剰な設備投資を進める中国の大増産による需給悪化により、基礎原料となるエチレンプラントの稼働率が低迷し、採算が大幅に悪化。日本各地のコンビナートで能力削減の動きが進んでいる。しかしコンビナートは地域経済の担い手であり、日本のものづくりの根幹を成す基礎素材を製造している。脱炭素というチャレンジをチャンスに変えない限り、日本の産業は衰退するのみ。CO2排出を実質ゼロとするカーボンニュートラルの取り組みをコンビナートの再生に向かわせるウルトラCはないのか。コンビナート衰退の危機をチャンスに変える処方箋を探った。

第7次エネルギー基本計画(エネ基)の原案が、17日に資源エネルギー庁から発表された。事実上の複数シナリオの提示であると言わざるを得ない事態だ。「わざわざエネ基を作る意味がなくなる」と憤る理由を徹底解説する。

石破茂新内閣が発足した。エネルギー政策に深くかかわる経済産業大臣には、武藤容治氏が就任した。石破内閣の発足で、日本のエネルギー政策は変わるだろうか。特に原子力政策はどうなるか。

原子力規制委員会は7月下旬、日本原子力発電の敦賀発電所2号機について、新規制基準に適合していないと結論づけた。今回の判定を受けて、日本原電の存続を危ぶむ声がある。しかし、同社の事業継続は、十分に可能である。

わが国が2023年夏の電力危機を克服することができたのは、火力発電の貢献によるものである。中身を見ると、もちろんLNG(液化天然ガス)火力も重要な役割を果たしたが、LNG調達には不確実性が伴い続けた。電力危機克服に安定的な力を発揮し、日本国民に安心感を与えたのは、実は石炭火力であった。

最近、「GX」という言葉をよく耳にする。GXとはグリーントランスフォーメーションの略称であり、経済産業省によれば、「化石燃料をできるだけ使わず、クリーンなエネルギーを活用していくための変革やその実現に向けた活動」のことである。実は国内のGX拠点整備を巡り、地域間競争が激化しているのだ。

原子力発電所の立地が多い日本海側。今年元日の能登半島地震の影響で、原発再稼働への道筋に狂いが生じかねないのは、東京電力ホールディングスの柏崎刈羽原子力発電所である。

2024年のエネルギー業界では、「2035年」が強く意識されるようになる。25年秋に開かれるCOP30(国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議)までに世界各国は、35年の温室効果ガス(GHG)削減目標を明示しなければならないからだ。日本政府も、この日程に合わせて、第7次エネルギー基本計画の策定を急ぐことになる。
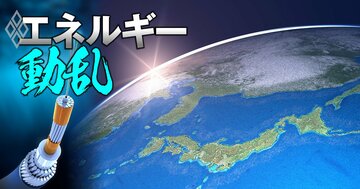
2年後のCOPC30では、世界各国が、2035年に向けた温室効果ガスの削減目標を持ち寄ることになっている。日本でも第7次エネルギー基本計画の策定作業が進むことになるが、何が焦点となり、鍵を握る企業はどこになるだろうか。

岸田文雄内閣は今年2月に「GX実現に向けた基本方針」を閣議決定した。だが、メディアが「GX実現に向けた基本方針の概要」を基に報道することで、「GX実現に向けた基本方針」は、「原子力の重点化」を最重要課題の一つとしているかのような印象が広く世間に流布している。基本方針のポイントに加え、方針に盛り込まれた原子力の位置付けを解説する。
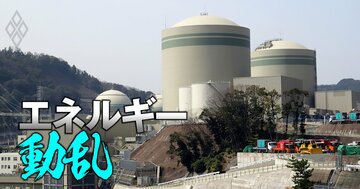
4月に先進7カ国のエネルギー・環境担当相会合が札幌で開催された。多くのメディアは「石炭火力廃止の時期が明示されなかった」「原子力が選択肢の一つとして認められた」「天然ガスも削減対象に含まれた」などと報道。しかし、これらの報道は、いずれも「的外れ」だと言わざるを得ない。

大手電力4社が絡んだカルテル事件や大手電力各社による不正閲覧問題など不祥事が相次ぐ電力業界。燃料価格高騰などで各社の経営環境も厳しい。電力業界は抱えるさまざまな問題をどう解決すべきか。“業界のご意見番”橘川武郎氏が業界再編の必要性を訴えた寄稿をお届けする。
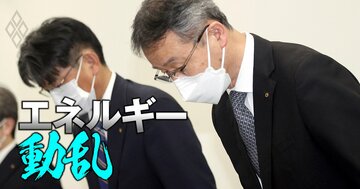
第2回
前回、シェールガス革命が切り拓いた新時代におけるLNG調達コストの削減策について論じたが、電力料金値上げを回避する火力発電用燃料コストの抑制という意味では、石炭火力発電の活用も、きわめて重要な意義をもつ。
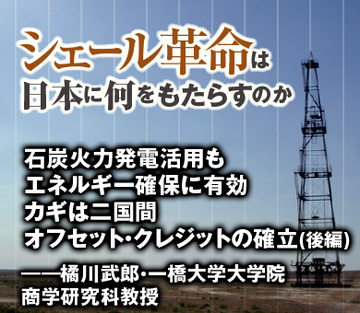
第1回
2013年の日本経済にとっての大きなリスク要因に、電力料金の値上げ問題がある。3.11後の原子力発電所の運転停止にともなう火力発電用燃料コストの急膨張によって、全国10社の電力会社中5~6社が料金引き上げを迫られているのだ。