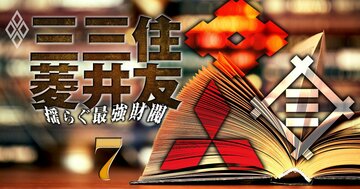写真提供:三菱重工業
写真提供:三菱重工業
三菱重工業の躍進が著しい。時価総額は3年半で9倍になった。脱炭素の潮流と新型コロナウイルス感染拡大によって、中枢事業の火力発電機器と航空機部品が大打撃を受けた数年前からは見違えた。現在の好況はバブルなのか、それとも実力で勝ち取った果実なのか。特集『重工バブルの真相』の#1では、直近3代の経営者がどんな環境で何をなしたのかを分析。歴代幹部の証言から、株価上昇の真因と、三菱重工の本当の実力に迫る。(ダイヤモンド編集部 井口慎太郎)
脱・脱炭素の動向を読んで
独シーメンス、米GEを逆転
三菱重工業が絶好調だ。時価総額は2022年4月から25年10月までに9倍に膨らみ、12兆円を超える。同期間の日経平均株価の上昇率が1.7倍だから伸び方は尋常でない。同じ重工業界の上昇率と比べてもIHIの6倍、川崎重工業の4倍を圧倒する。
押しも押されもせぬ成長株となったが、かつては「成長性が乏しい地味な銘柄」と見られていた。防衛装備品や発電機器、ニッチなところでは24年に撤退を発表した新聞輪転機など、公共性のある事業を多く手掛け、替えが利かない製品を担ってきた。
そのような製品を扱っていることから、利益を追うよりも、そこそこの利益を確保しながら事業を安定して継続することに重きが置かれていた。日本経済が成長基調にあった頃はそれで良かったものの、成長が頭打ちになった近年は変革を迫られた。
本格的に改革路線にかじを切ったのが、2代前の社長で13年に就任した宮永俊一氏だ。各地の事業所の権限が強く、意思決定が遅れがちだったところを、本社が主導権を握れるよう組織を再編した。財務体質の改善も課題だった。事業ごとに損益計算書と貸借対照表を提出させ、不採算部門を見える化して“どんぶり勘定”を改めた。
しかし、宮永氏が社長を務めた時代は三菱重工にとって冬の時代だった。豪華客船のコスト膨張による巨額損失、三菱スペースジェット開発の泥沼化、さらには三菱日立パワーシステムズ(現在は三菱重工に統合)の南アフリカ火力発電案件での損失負担――三つの逆風への対応に追われ、改革の成果を望むどころではなかった。宮永氏は社長を6年務めたものの脚光を浴びることなく、後任を泉澤清次氏に譲る。
ここで、三菱重工が何で稼いでいる会社なのかに視点を移したい。近年は防衛銘柄の代表として語られることが多い。実際に23年度も、24年度も防衛装備庁の契約実績は2位の川崎重工の2倍以上の金額で日系企業ではダントツだ。25年3月期の防衛・宇宙事業の受注高は1兆9000億円に迫り、23年3月期の3倍以上に膨らんでいる。しかしながら、現在の好調を、防衛のみで語ると不十分だ。
三菱重工の25年3月期の事業利益3831億円の半分以上は、LNG(液化天然ガス)火力発電に使われるガスタービンなどを含むエナジーセグメントが稼ぎ出している。発電量が安定しない再生可能エネルギーを補完する電源として火力発電機器の需要が近年爆発的に増え、同期の受注高は22年3月期の2倍を超えるまでになっている。
そして、三菱重工が足元の発電機器部門で大きな利益を上げられている理由、ひいては三菱重工が市場で評価されている要因は「撤退力」にあるとみることができる。
次ページでは、歴代幹部の証言から、躍進の決め手となった経営判断を分析する。さらに海外の競合との力関係を明らかにするとともに、直近3代の経営者がどんな施策を打ち、企業価値をどれだけ高められたのかを図表で示す。