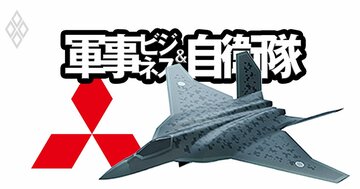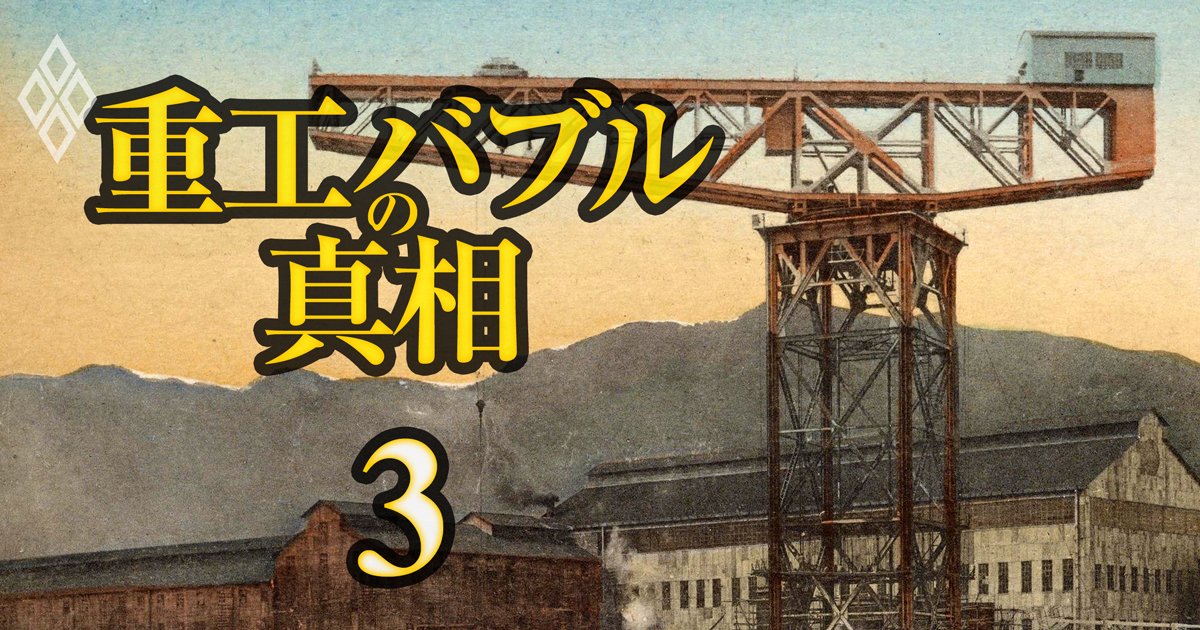 三菱重工業長崎造船所の大型クレーン。1910年当時をデジタル復元した Photo:Bildagentur-online/gettyimages
三菱重工業長崎造船所の大型クレーン。1910年当時をデジタル復元した Photo:Bildagentur-online/gettyimages
三菱重工業、川崎重工業、IHIの重工3社は、防衛予算の追い風を受けて好業績を収めている。いずれも明治時代から続くレガシー企業だが、そもそも重工業とはどんな領域なのか。実は3社の祖業は同じだが、150年の歴史でそれぞれの得意領域を磨いてきた。特集『重工バブルの真相』の#3の本稿では、重工3社のエース事業とお荷物事業をつまびらかにする。(ダイヤモンド編集部 井口慎太郎)
防衛銘柄として一躍、時代の寵児に
実は川崎重工が最も防衛比率が高い
「うちにしか担えない事業で国家を支えていた自負は持っていたけど、入社以来、株式市場からさほど注目されることはなかった。だから(防衛銘柄として株価が上昇した現状は)変な感覚ですよね」。三菱重工業のベテラン社員がつぶやく。
三菱重工、川崎重工業、IHIの重工3社がいま、かつてない脚光を浴びている。3社はいずれも2025年3月期は最高益となり、今期も好調だ。
最も強い追い風は防衛費の増額だ。23年度以降の各社の業績を底上げしている。政府は23~25年度の防衛費の総額を従来の1.6倍の43兆円に増やした。27年度には「GDP(国内総生産)比2%」の達成を目指している。
強化する防衛装備には、敵の攻撃圏外から撃ち込める長射程の「スタンド・オフ・ミサイル」がある。これには三菱重工が手掛ける「12式地対艦誘導弾能力向上型」が該当する。25年3月期の同社の防衛・宇宙事業の受注高は防衛費増額前の3倍超の1.8兆円にまで跳ね上がったから、恩恵は絶大だ。
川崎重工は実は、以前から売上高に占める防衛事業の比率が3社で最も高い。25年3月期は、大型輸送用ヘリコプター「CH‐47」の大口受注があり、受注高全体の約3割を防衛事業が占めるまでになった。IHIは哨戒機や練習機の航空エンジンを担い、26年3月期は防衛事業だけで70億円の増益を見込んでいる。
受注残も積み上がっている。三菱重工は10兆7000億円、川崎重工は2兆7000億円、IHIは1兆5000億円を超えている。
市場からの評価もうなぎ上りで、直近3年半で各社の時価総額は大きく伸びた。伸び率はそれぞれ、三菱重工は9倍、IHIは6倍、川崎重工は4倍に上る。この期間の日経平均株価の伸び率は1.7倍。3社ともに際立って企業価値を上げているといえるだろう。
地政学リスクの緊張が高まり続けていることが「重厚長大産業」の復権につながっている。ロシアのウクライナ侵攻やイスラエル・パレスチナ戦争は、防衛産業などにスポットを当て、投資資金が流れ込んでいるのだ。
ところで、重工業、と聞いてどんな製品を思い浮かべるだろうか。現在の事業を見る前に、過去の経緯に目を向けたい。重工3社はいずれも創業から150年ほどになるレガシー企業で、実は祖業は同じく造船だ。明治初期のものづくりの黎明期。当時の日本にとって、まず造らなければならなかったのが船舶だった。
日本の近代化をものづくりの面で支え、鉄道や航空機、原子力発電に火力発電用のガスタービンと事業の裾野を広げていった。潮目の変化は、祖業である造船で競争力を失ったことにある。1990年代以降に韓国勢、2000年代以降に中国勢が台頭した。
三井造船(現三井E&S)、住友重機械工業、日立造船(現カナデビア)も祖業が造船で、かつては重工3社と合わせて「総合重工6社」と称されていた。この3社は造船を縮小する中で事業を絞り込んだ。三井E&Sは船舶用エンジン、住友重機械は精密機械や建機、カナデビアはごみ焼却発電施設に特化している。
重工3社も、それぞれのエース事業を育て、三者三様の事業ポートフォリオを構築している。次ページでは3社の売上高と事業利益を部門ごとに分析する。