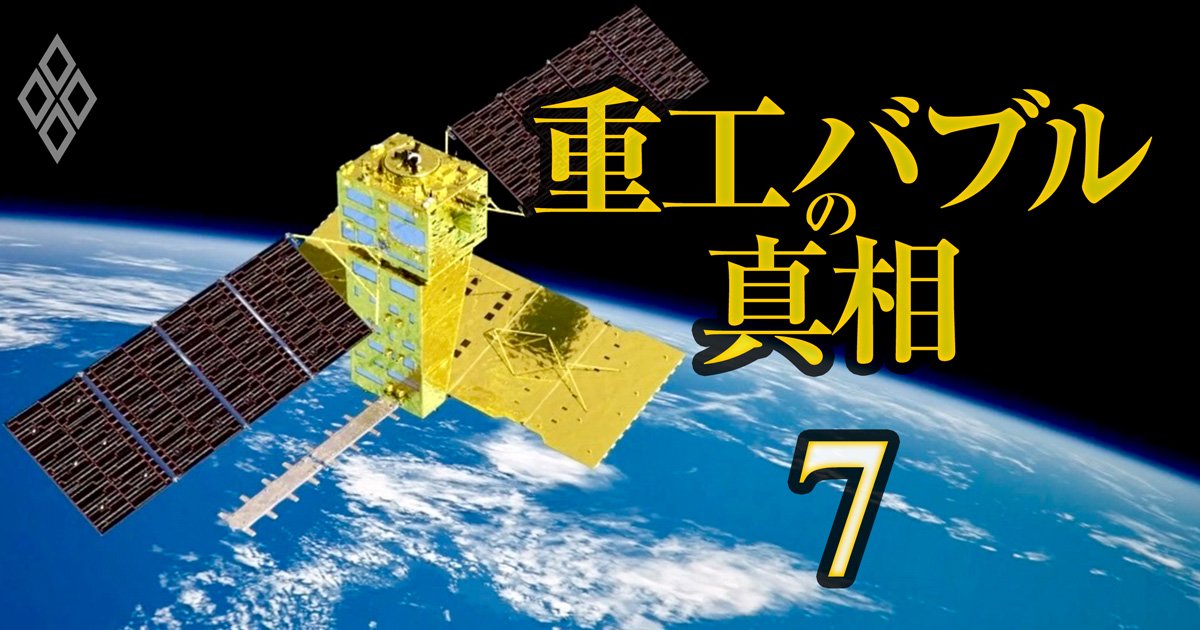 宇宙航空研究開発機構(JAXA)のレーダー衛星「だいち4号」。三菱電機が開発した(写真提供:JAXA)
宇宙航空研究開発機構(JAXA)のレーダー衛星「だいち4号」。三菱電機が開発した(写真提供:JAXA)
防衛において、三菱電機が強みを持つ「通信・電子機器」と「宇宙分野」の重要性が増している。三菱重工業が製造している長射程のスタンド・オフ・ミサイルにおいても、遠距離の目標を正確に把握する情報収集技術が不可欠だ。特集『重工バブルの真相』の#7では、犬猿の仲ともいわれる三菱重工と三菱電機の防衛部門の関係性を分析。さらに、三菱重工が防衛産業の“盟主”であり続けるために強化すべき役割も明らかにする。(ダイヤモンド編集部 井口慎太郎)
防衛装備の頭脳は「弟分」の三菱電機の領域
「兄貴分」の三菱重工に必要な改革とは?
「三菱重工業は防衛産業における通信プラットフォームを欲しているはずだ」。長年、防衛産業に携わる業界関係者はこのように見立てている。
陸、海、空、宇宙という全ての領域の防衛装備品をそろえている三菱重工だが、通信・電子機器や情報収集衛星は、弟分の三菱電機などにほぼ任せててきた。ところが近年、航空機や艦艇などは単体で使うよりも、複数の防衛装備が構築するネットワークを利用して、領域をまたいで運用をすることが重視されている。となると重要性を増すのが、センサーや通信機器、情報処理の技術だ。
日本、英国、イタリアの3カ国による共同開発が進められている次期戦闘機は「第6世代」と位置付けられ、無人機との連携を強化している。そこでも、重視されているのは通信や情報処理の技術だ。
そうした中で、政府が防衛力整備計画で七つの重視分野に挙げるうちの一つが、敵が日本に攻撃を仕掛ける前に射程圏外から攻撃できる「スタンド・オフ防衛能力」だ。これに該当する防衛装備品が、三菱重工の12式地対艦誘導弾改良型である。このミサイルは、2023年度の防衛費増額以降、三菱重工の受注高の増大に大きく寄与している。
同ミサイルは射程距離の長さが特徴だ。現在、陸上自衛隊で運用されている12式地対艦誘導弾の射程は約200キロメートルだが、改良型では約1000キロメートルとされる。このミサイルを運用するに当たって重視されているのが、情報収集・監視・偵察の機能だ。どこに敵がいて、どのように移動しているのかをリアルタイムで捕捉する必要があるためだ。
そこで人工衛星の活用が期待されているが、三菱重工は情報収集に使える衛星を自前では持っていない。対して、三菱電機は衛星分野に強い。「ミサイルも衛星も、使うのは防衛省だからメーカーは別々でも運用上はさほど問題はない。ただ、相互の技術をつなげることができれば開発におけるメリットは計り知れない」(前出の関係者)。
三菱電機は従来レーダーを強みとしてきたが、近年は衛星分野でも目標の探知や追尾機能を磨いている。防衛通信衛星「きらめき」シリーズの基幹部分である衛星バス「DS2000」を製造しているのも同社だ。
今後の活躍が注目されているのが、合成開口レーダー(SAR)を搭載した衛星(SAR衛星)だ。この衛星は、マイクロ波を照射し、地表からの反射波を解析して地表の情報を画像化するため、天候や昼夜にかかわらず観測でき、光学衛星では得られない情報を入手できる。宇宙航空研究開発機構(JAXA)の観測衛星「だいち4号」はこれに当たる。
三菱電機は24年、SAR衛星を手掛けるスタートアップ、Synspective(シンスペクティブ)に60億円を出資し、筆頭株主となった。
このように、三菱電機は新時代の防衛において枢要となる領域に積極的に投資している。では、三菱重工と三菱電機が互いに補うために接近することはあるのだろうか。日本の防衛産業では再編論がしばしば語られてきた。長年、利益が少ない上に多品種少量生産を防衛装備庁から求められる中で、防衛産業から撤退するメーカーが相次ぎ、存続のために合従連衡する構図には現実味があった。
しかし時代は変わった。ジリ貧といわれた防衛産業は、防衛予算の増額によって、利益率が良く、安定した仕事量が見込めるうまみのある事業に変貌したのだ。三菱重工でも三菱電機でも、手放すことなど考えられないエース事業になっている。
つまり、業界再編の機運はトーンダウンしている。では、通信・電子機器の重要性が増す中で、それを直接扱っていない三菱重工が果たすべき役割はどこにあるのだろうか。「犬猿の仲」ともいわれる三菱電機との関係性も併せて次ページで掘り下げる。







