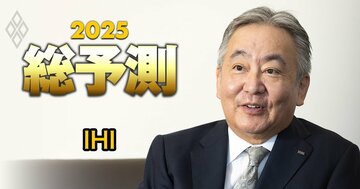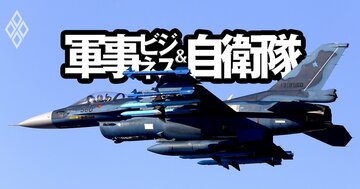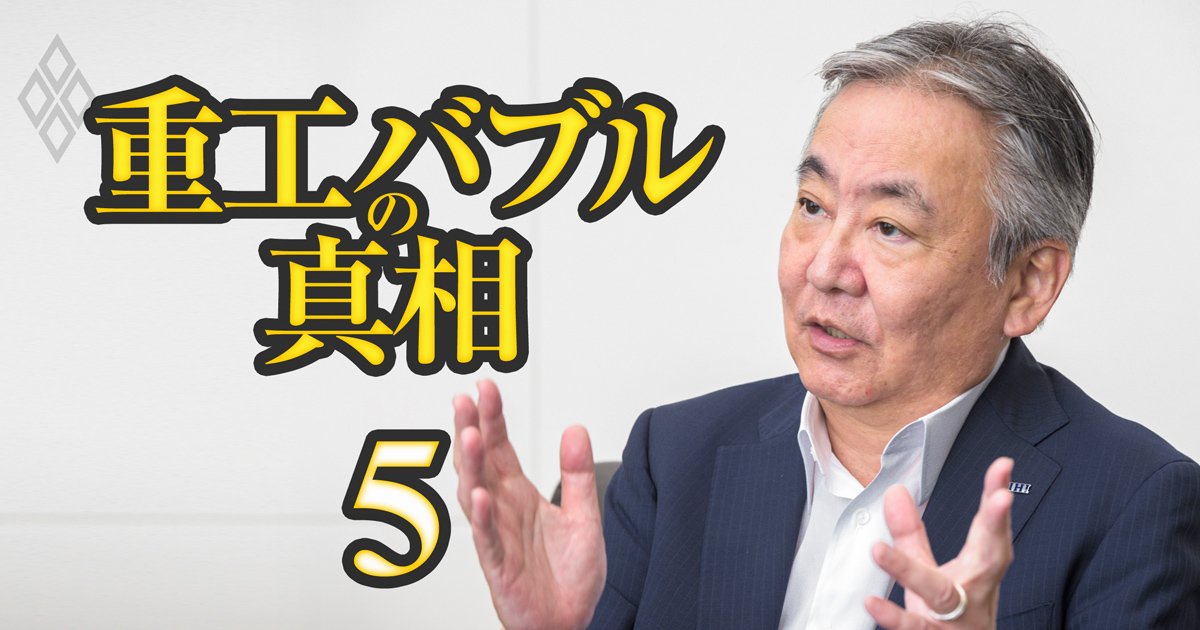 Photo by Tohru Sasaki
Photo by Tohru Sasaki
IHIは営業利益の8割以上を航空・宇宙・防衛部門が稼ぎ出しており、三菱重工業と川崎重工業に比べてもエース事業がはっきりしている。ただ、航空エンジンは品質問題の発生リスクや、事業環境の変動が大きいため、“第2の柱”が求められて久しい。特集『重工バブルの真相』の#5ではIHIの井手博社長に、さらなる事業再編の方向性や、現在の好況の真因を聞いた。(ダイヤモンド編集部 井口慎太郎)
米国トランプ政権の脱炭素政策見直しを受けた
アンモニア、原発関連事業の次の一手とは?
――中期経営計画では屋台骨の航空エンジンと並ぶ事業の創出を掲げていますが、現時点では「航空エンジン一本足打法」となっています。
航空エンジン事業はボラティリティが高く、2023年に発覚した欧州エアバスの主力狭胴機向けエンジンでの粉末冶金トラブルのような問題が発生すると、収益が大きく揺らぎます。
ショックを吸収できる体制を築くため、整備・修理事業を拡大し、30年代半ばまでにアフターマーケットの売上高を現在の4倍の800億円規模に成長させます。航空エンジンを全体として見たときに「一本足」にせず、製品の導入期から衰退期まで、各段階で収益を上げられるライフサイクル・ビジネスを確立することが重要だと考えています。これまでも民間需要が落ち込んだ際には、防衛部門への人材シフトで対応してきました。
――航空機需要は今後、座席数が100~200席の狭胴機への移行が加速すると考えますか。
狭胴機中心の時代になるとみていましたが、実際には座席数が多く航続距離も長い広胴機も依然として多く飛んでいます。太平洋・大西洋路線では、狭胴機だけでは輸送量が足りません。インバウンド需要の回復で、人の移動は想定を上回る勢いです。予想はなかなか当たらないものですね。
――国際共同開発中の次期戦闘機の航空エンジンで、英ロールス・ロイス、伊アビオ・エアロとコンソーシアムを組むことになりました。参加する利点と課題はどこにありますか。
戦闘機用エンジンは、戦闘機の性能や可動率を左右する最重要要素の一つであり、これをライフサイクルにわたって安定的に支えることができる生産・技術基盤は、国の安全保障上の重要なツールになり得ることに加え、他産業への大きな波及効果も期待できます。
さらにデジタルトランスフォーメーションの推進やパートナー国への海外移転などを通じた防衛産業基盤のより一層の強化にもつながります。また、グローバルビジネスで活躍できる人材や高度な技術を持つエンジニアの育成・輩出にも貢献できます。
言葉、習慣、文化が大きく異なるため、それらの違いを理解し合いながら進めるのは難しいですが、コミュニケーションを密に取り、文化の違いや疑問点について十分に話し合うことで、お互いの相違点について理解を深め合いながら進めています。
次ページでは、今後の事業再編や、米国のトランプ政権が脱炭素政策を見直す中でのエネルギー部門の方向性、さらに現在の好況の真因をどうみているかについて井手社長に聞いた。