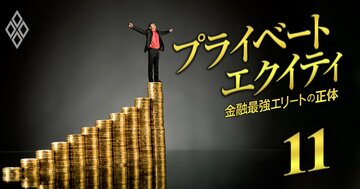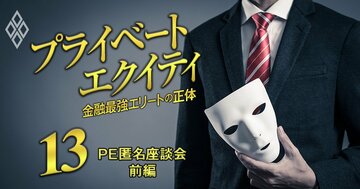Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
「とりあえずコンサル」という言葉が浸透するほど、コンサルティング業界は学生から高い人気を誇る。その理由は、若いうちから多様な業界・企業の経営課題に触れ、課題解決能力や論理的思考力を鍛えられる点にある。ただ、コンサルタントとしての経験を積んだ後、自身のキャリアに新たな可能性を求める若手ビジネスパーソンも少なくない。連載『コンサル大解剖』内の連載「コンサルキャリアの新潮流」の本稿では、「コンサル→事業会社」転職に焦点を当て、そのメリットと現実を徹底解説する。(コンフィデンス・インターワークス紹介事業部統括部長 金澤 渉)
「コンサル→事業会社」の転職は17%
メーカー、通信、金融が人気業種
近年の転職市場は活況を呈しており、IT、コンサル、製造業、建設、エネルギーなど各業界で採用意欲が非常に高いです。求人数も前年比で約10%増加しており、転職を考えるには絶好の機会と言えます。この活発な市場で、コンサル出身者は常に高い市場価値を持っています。
ハウテレビジョンが運営する転職プラットフォーム「外資就活ネクスト」のデータによると、転職者の3割が現職コンサルタントであり、彼らの平均年齢は28歳、平均現年収は972万円となりました。多くのコンサルタントが4~6年間の実務経験を積んだ後に最初の転職に踏み切る傾向が見られます。
コンサルからの転職先は、コンサルへの再転職が61%、金融プロフェッショナルが22%、事業会社が17%となっています。事業会社への転職は、大きく分けて大手企業に経営企画などで入社するパターンと、スタートアップに役員などの上位ポジションで入社するパターンがあります。
当社の2020年~25年9月までの実績データでは、企業規模別の転職先分布においてエンタープライズが5割、次いでSMB(中堅・中小企業)が3割、スタートアップが2割となっています。メガベンチャーはスタートアップに分類される傾向が強いですが、これは規模が大きくても変化が速く、自律的に動くマインドが求められるためです。
また、業界別では、メーカー、小売り、サービス、商社、金融、マスコミ、ソフトウエア・通信、官公庁・公社・団体など、多岐にわたる選択肢がありますが、特にメーカー、通信、金融の3業種への転職が目立ちます。
背景には、コンサル出身者の多くが、経営戦略の策定や業務プロセス改善の経験を持ってることがあります。それらはメーカー、通信、金融業界が抱える課題と親和性が高く、事業会社にとってはコンサル業界出身者に対して高い採用意欲を示すことになります。以下に業界別のコンサル人事採用ニーズが高い理由をまとめます。
メーカー:製品開発やサプライチェーンの効率化、DX推進など、コンサルタントが培った経験やロジカルシンキング、プロジェクトマネジメント能力を活かせる領域が多岐にわたる
通信:6GやIoTといった新技術の導入、市場の変化に対応した新たな市場参入や新規事業の立ち上げ、既存事業のコスト削減など、戦略的な視点での課題解決能力が求められる
金融:FinTechの台頭、法規制への対応、業務のデジタル化など、複雑な課題が多く、コンサルタントの持つ高度な分析力や課題解決能力が重宝される
一方で、職種別に見るとコンサルから事業会社へ転職する場合は、経営企画、事業企画、マーケティング、DX推進、財務、M&Aなどの経営に近いポジションが多いです。割合はそれぞれおおむね同程度ですが、経営企画や新規事業企画、DX推進のニーズが数としては目立ちます。
扱うトピックスとしては、サステナビリティー/ESG推進やグローバルビジネス展開支援などがあり、コンサル出身者の活躍領域は広がり続けています。近年、コンサルから事業会社への転職は、市場価値を高める戦略的な選択肢として増加の一途です。
これまで、コンサルから事業会社への転職は給与面がボトルネックになることが多かったが、足元では改善傾向にあるという。さらに、キャリアパスを見据え、戦略的に事業会社に転職するケースも増えている。次ページでは、「給料」「成長機会」「働き方」「評価・昇進」などの6つの項目で「コンサル→事業会社」転職の優位点などについて解説。また、ライフステージや価値観の変化に対応して「コンサル→事業会社」転職に踏み切った3人の実例を紹介する。