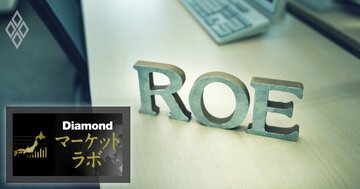史上初の5万1000円台で取引を終えた日経平均株価の終値を示すモニター=10月29日午後 Photo:JIJI
史上初の5万1000円台で取引を終えた日経平均株価の終値を示すモニター=10月29日午後 Photo:JIJI
「高株価」謳歌、日経平均は初の5万1000円台
ネガティブ要因置き去り、市場に広がる「油断」
高市早苗新政権が10月21日発足したが、早々に27日には、トランプ大統領が来日、初の首脳会談が行われた。
会談では、トランプ関税の見直し協議で合意した日本の「対米5500億ドル投資」の着実な履行や、中国の海洋進出などをにらんだ防衛協力強化や日本の防衛費増強などが改めて確認、合意されたが、株式市場などを見る限り、日米の間はある種の好循環のなかになる。
トランプ大統領が「相互関税」を発表した4月2日以降、世界の金融市場は大荒れの展開となったが、ベッセント財務長官が関税交渉の軌道修正を図ったおかげで相場は安定感を取り戻した。
その後も、米国主要株価指数は、FRB(連邦準備制度理事会)の利下げ再開とAI関連投資ブームによる成長牽引(けんいん)期待という二つの上昇要因が加わって、最高値を更新し続け、米国長期金利は4%台で低位安定、ドルも夏には下落基調から小反発へと切り返している。
7月から急騰したダウ工業株平均株価の10月24日には終値で初めて4万7000ドルを超え、28日には4万7706.37ドルと最高値を更新した。
米国株式市場の活況を受ける形で、日経平均株価(終値)も10月9日には初の4万8000円台となると、20日には4万9000円台、さらに27日には高市新首相の積極財政・緩和維持の経済路線への期待も加わって初の「5万円台」となった。
29日には、日経平均株価を構成する大半の銘柄が値下がりしたなかで、AI関連銘柄が突出して上昇し、終値で5万1307円65銭と、5万1000円を超え最高値を更新した。
だがこの間の米国市場は、トランプ減税恒久化による米国財政赤字拡大、トランプ政権によるFRB人事への直接介入、トランプ関税によるインフレ再燃リスク、厳しい移民流入規制による成長阻害、貿易戦争による中国のレアアース輸出規制、関税を巡る日欧など同盟国とのあつれき、中東でのイスラエルへの過剰な肩入れ、といったネガティブな材料はほぼスルーしてきた。
米国株も米国債も、この半年間は「良いとこ取り」の相場を堅持してきたといえる。
だが注意が必要なのは、このところ、FRBの追加利下げ期待とAI関連への熱狂的な投資という株価上昇を支える両輪に関しても、異論や疑問が提示され始めていることだ。
日米の景気減速に対する楽観論や「高市トレード」の活況もしぼむ可能性がある。