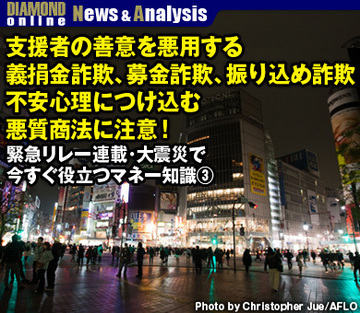「今さらもう読みたくない」と思う読者もいるだろう。ストーリーについて語るタイミングとしては、遅きに失したかもしれない。けれど、今だから、冷静に考えられることもある。
佐村河内氏がゴーストライターを使って作曲していた問題と、理化学研究所の小保方晴子さんらが発表した「STAP細胞」論文を巡る疑惑の数々。クラシック音楽と先端科学という、まったく違う分野で起きた2つの“事件”は、私たちが生きているストーリー消費社会のありようを浮かび上がらせた。
最初に断っておくが、個々の疑惑について論じたり、コトの真相を明らかにするのがこの原稿の目的ではない。それよりも、2つの事件がはからずもあぶり出した「ストーリー」の効用と限界について、述べたい。
情報化社会の今日では、誰もがストーリーの創作者となり、消費者になってしまう可能性がある。これは、私たちが暮らしている社会全体、あるいは現代資本主義が抱えている矛盾を指し示す出来事だ。
「メディア時代」を先駆けた芸術家
アンディ・ウォーホル
先の二人に関するニュースが流れ、それがインターネット上で拡散していく様子を眺めていて、ある人物のことが思い浮かんだ。20世紀後半を代表するアーティスト、アンディ・ウォーホルだ。
1928年、アメリカのペンシルバニア州に生まれたウォーホルはキャンベル・スープの缶をモチーフにした作品で一躍、時の人となり、1987年にこの世を去るまで、数多くのポップアート作品を遺した。
なぜ、キャンベル・スープの缶を描くのかと聞かれた時、彼は「毎日、それを飲んでいたからさ」と答えたという。今ではすっかり悪者イメージの大量生産も、当時は、富める人にも貧しい人にも等しく、「いいもの」を「より安く」届けるための手段として歓迎されていた。街に溢れるスープ缶は、豊かなアメリカの象徴だったのだ。