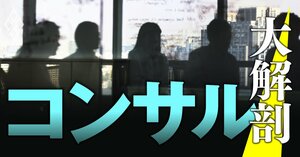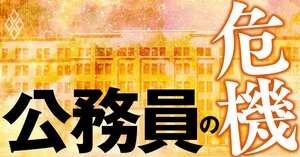2014 FIFAワールドカップブラジル大会が始まった。日本時間の15日朝に行われた日本代表の初戦は、残念ながらコートジボワールに惜敗したが、まだグループリーグは2試合を残している。なんとか立て直して、少しでも長く(できれば最後まで)ブラジルの大地でプレーを続けてほしい。
今回のワールドカップは、世界的にスマートフォンやSNSの普及が進んだ結果、試合そのもののクリップ映像も含め、ワールドカップに関連する様々な情報やコンテンツが、ネット上を駆け巡っている。ネットを介して、ここまでワールドカップを「空気のよう」に楽しむ状況は、前回・前々回には見られなかった。これは大きな変化だ。
また、ワールドカップを題材にした、通信や放送領域での新たな取り組みも、これまで以上に注目されている。例えばNHKは、4Kに続く高画質映像の8Kスーパーハイビジョンによるパブリックビューイングを行っているほか、NTTと共同で日本・ブラジル間のIP網による8K伝送の実証実験を行っている。
スポーツとICTは、もともと相性が良い。スポーツがコンテンツの中でも「強い」ものであるのと同時に、スポーツの楽しみ方やスポーツビジネスが、ICTによって一層強化されるからだ。さらにはソリューションの実験室として、より高度な技術を社会にアピールする好機でもある。
そう考えれば、2020年東京五輪は、私たち日本の経済社会が勝ち得た、デモンストレーションの絶好の機会ということになる。では私たちは2020年に向けて、どんな準備をしていけばいいのか。
実はそのヒントは、2010年に策定した、2022年FIFAワールドカップ日本招致構想に詰まっている。開催自体は残念ながらカタールに決まったが、ここで検討された内容は、いまでもまったく色褪せない。
実は私自身も、この招致委員会の中の人(ICTコンサルタント)として、構想のとりまとめをお手伝いした。そんなわけで、やや手前味噌ではあるのだが、ワールドカップの開催を踏まえ、改めてここでその内容をご紹介したい。