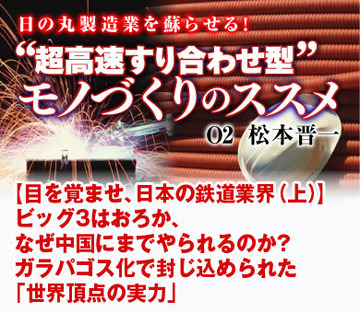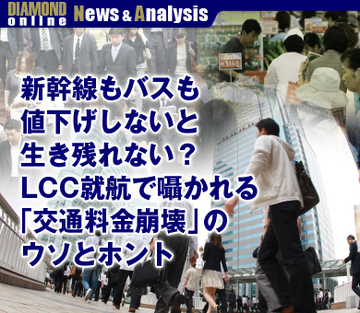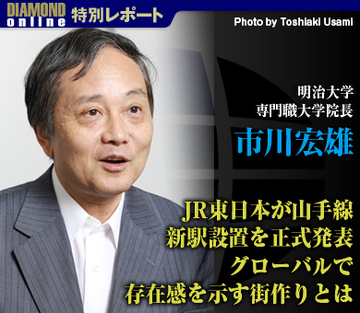日本のライフスタイルを変えた
新幹線の経済需要創出効果
「ピラミッド、万里の長城、戦艦大和に次ぐ、無用の長物」。建設費用は3000億円、当時の国家予算の1割にも相当する東海道新幹線は開業に当たり、世間から、このようにやゆされた。
しかし、1964年に開業すると、こうしたネガティブな声は吹き飛んだ。この50年間、死亡事故もなく、ビジネス、観光、地方経済に大きな影響を与え、日本人のライフスタイルのみならず、思考体系まで一変させたのだ。
新幹線登場前、ビジネス特急「こだま」は東京~大阪間を6時間50分で結んだが、新幹線の開業で4時間に短縮された。
節約された時間を基に、当時の賃金から試算された時間短縮の効果は年2500億円、つまり2年間で建設費のお釣りが出る計算だ。
50年間積み重ねるとその効果は天文学的数字になる。当時の平均年収は41万円にすぎないが、現在は9倍弱の350万円(国税庁民間給与実態統計調査)になっているからだ。しかも、今や東京~大阪間は約2時間半にまで縮まっており、時短効果はさらに上積みされる。
東海道新幹線の日本経済への貢献は、それだけでない。工場誘致など、開業時ですでに、経済需要の創出効果は9000億円発生したと国鉄は試算している。
今もなお新幹線誘致の声がやまないのは、この経済効果を期待してのことだ。小ぶりな北陸新幹線ですら開業10年で1300億円のGDP押し上げ効果があると推計されている。
ビジネス需要だけではない。お盆や正月など今では多くの日本人が帰省し風物詩となったが、これも在来線と自家用車と飛行機という選択肢しかなければ、少し違った景色になっていただろう。