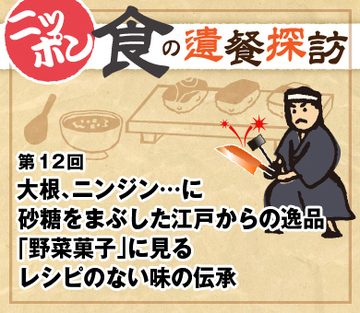北海道美瑛町『ビブレ(bi.ble)』のパン
北海道美瑛町『ビブレ(bi.ble)』のパン
本連載は基本的には日本の食文化の周縁を取材し、探訪記事にしている。その流れから言えば今回のテーマ「パン」は世間一般の常識からいえば〈日本の文化〉と思われないかもしれない。
パンは西洋社会の象徴的な食べ物。はるか数千年も昔、メソポタミアの頃から存在し、古代ローマ、ポンペイの遺跡から発掘されたパンの化石は製法的にも現在のものとほとんど変わりがないという。
キリスト教にとってイエス・キリストの肉とされるパンが重要であることはいうまでもない。パスツールが発酵のメカニズムを発見するまで、パンは神秘的な存在だった。生地がどうして膨らむのか、わからなかったからだ。
理由がわからなくても人々はパンを焼き続け、今では世界中で食べられているパン。
『パンの歴史』を著したスティーブン・L・カブランは同書のなかでこう語っている。
「パンは物質と象徴、経済と文化の交わるところに位置している」
アメリカからの小麦大量供給で
戦後、急激に日本へ浸透したパン食
日本人にとってパンは複雑な食べものだ。江戸時代にはポルトガルの宣教師から製造方法は伝わっているが、日本人には受け入れられなかった。そもそも日本で生産されていた小麦はタンパク質含有量が少なく、うどんなどの麺にはなってもパンには向かなかったのだ。
情勢が大きく変わったのは戦後、アメリカが食糧難の日本に小麦粉を大量供給したことだった。当時、アメリカで小麦は余剰作物になっていて、新たな輸出戦略が必要だったのだ。
アメリカから輸入された小麦を使ったパン食は給食にとりいれられる。「米を食うと頭が悪くなる」という意見がまじめに新聞に出たのもこの頃である。
輸入小麦に牽引されたパンの消費は増え続け、2012年の家計調査ではついに米の消費額を上回る。実際はパンの消費額が伸びたわけではなく米の消費量が下がっただけなのだが(おかずが増えたことなどによる)、大きな話題になった。