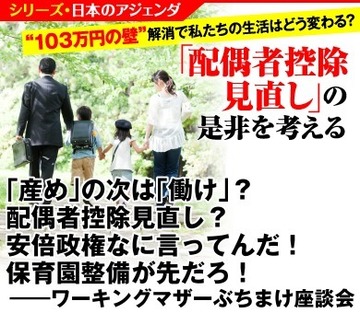政府の税制調査会は、11月7日に開かれた第12回会合で、配偶者控除の見直しについて5つのパターンを示し、国民的議論を呼びかけた。この問題はどのように考えればいいのだろうか。
配偶者控除とは何か
なぜ見直しが必要とされるのか
配偶者控除とは、例えば夫に扶養されている妻の年収が103万円以下なら夫の年収から38万円を差し引いて所得税を計算し、税負担を軽くする仕組みである。約1400万人がその適用を受けているが、これが女性の働き方を年収103万円以内に(自主的に)抑えてしまうという議論があり、以前から見直しが求められていたものである(いわゆる「103万円の壁」。もっとも、現実には妻の年収が103万円超141万円までの人には配偶者特別控除が導入されたので、税制上の103万円の壁は解消している)。
配偶者控除は、1961年(所得税。個人住民税は1966年)に導入されたものであるが、その背景には、冷戦構造下における「キャッチアップ型モデル」「人口の増加」「高度成長」という3点セットがあり(いわゆる1940年体制)、終身雇用の男性の雇用者と無職(もしくはパート)の妻からなる「片働き世帯」が「夫婦世帯」の典型かつ大多数を占める家族モデルとなっていたという特別な事情がある。
言うまでもなくこのような特別な状況は歴史的、世界的に見れば極めてガラパゴス的であって、決して普遍的なものではない。人間は動物であって、動物は成人すれば自分のご飯は自分で稼いで食べるのがごく普通の状態である。実際、世界のほとんどの先進国では、男性も女性も共に働くことが一般的であり、女性の社会進出が進むと出生率が高まるというデータもある。もちろん、そのためには、子育てをしながら安心して働ける社会環境の整備が必要であることは言うまでもない。
そして現在は、わが国のガラパゴス社会を支えていた冷戦構造は崩壊して久しく、また黄金の3点セットもすべてベクトルの方向が逆を向いている(現在は「課題先進国(キャッチアップすべきモデルはない)」「人口の減少(少子高齢化)」「低成長」が新しい3点セットになっている)。
加えて、家族モデルの変貌にも著しいものがある。2010年の国勢調査によると、かつての標準モデルだった「夫婦と子どものみ世帯」は27.9%と3割を割り込み、「単独世帯」が30.8%とトップに立った。続いて「夫婦のみ世帯」が19.8%、「ひとり親と子どものみ世帯」が8.7%、「(3世代世帯などの)その他の世帯」が11.1%となっている。即ち、配偶者控除を合理的制度とならしめた社会的・家族的要因は消失しているのである。そうであれば、見直しは必然であろう。