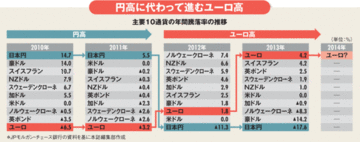さて12月はどうか。政策金利ではマイナス金利まで採用しており、残る手段はQEなどに限られている。だが、ECBが対象とするユーロ圏の国々は経済状況も財政状況も異なり、QEに踏み込みにくいという事情がある。それは何か。今年6月に「週刊ダイヤモンド」に掲載した記事「『日本化』するユーロ圏』が、そのあたりの背景と課題を余すところなく伝えている。これからのECBの行動を考える上で、非常に参考となるので、前回に続きDOL上で再掲してお伝えする。
6月5日の追加緩和パッケージで、いよいよ“弾切れ”に陥ったECB。最後に残されたカードは量的緩和(QE)だが、ECBにはこれに踏み込みにくい特殊な事情がある。
ポルトガルの首都リスボンの西に隣接する世界遺産都市シントラ。大西洋が望める山間の町でECB主催のフォーラムが催されたのは、追加緩和前の5月末のことだった。ヴァスコ・ダ・ガマによるインド航路開拓を決定したこの地を初の開催地に選んだのは、これからECBが突入するかもしれない“大航海時代(QEステージ)”を暗示しているからだろうか。
世界中からここに集まって議論を戦わせた中央銀行関係者や学者、エコノミストらの中で、ECBに対して“大航海”に出るべきだと主張した筆頭は、米プリンストン大学のクルーグマン教授だ。
「われわれは皆、日本が1990年代に直面したような状況にある」。同教授は、利下げカードの枚数がゼロになった後、停滞する経済をECBが傍観するだけにとどまるのはまずい、と懸念を表明した。
主催者のドラギ総裁も、傍観が招き得るリスクに理解を示した。「過度の低インフレがあまりにも長く続く状況を許すつもりはない」。日本ではこれが長引いたために人々のデフレマインドが定着し、デフレからの脱却を困難にした──中央銀行家の間では、そう認識されているからだ。
ただ悩ましいのは、一足先にQEという名の“海図なき航海”に出た米国や日本が、まだ無事に帰還していないこと。勇猛果敢に航海に出たはいいが、経済政策の運営当局である以上、“沈没”すればただの無責任である。
「QEは後戻りしない」。バイトマン・ドイツ連銀総裁は4月、そう言ってQE導入の期待をけん制していた。中央銀行が大量の金融資産を買い入れることで人為的に、かつ長期にわたって実質金利を抑えるというのは、効果はあるのかもしれないが、結局は出口の際に効果をひっくり返すほどのコスト(金利急騰や財政による損失補填リスク)を支払う可能性がある。
その本質は、政府の財務状況を悪化させて需要創出を狙うという点で、金融政策の範疇を超えた「財政政策」である。バイトマン総裁が「われわれの責務の限界も考慮しなければならない」と主張しているのもそのためだ。
もっとも日米とは異なり、ECBにはそもそもQEに踏み込みにくい特殊な事情がある。FRB(米連邦準備制度理事会)や日本銀行に対抗して通貨安を狙うなら「量」が勝負になるが、ことECBに限れば「バランスシート拡大競争に巻き込まれると弱い」(山脇貴史・JPモルガン証券チーフ債券ストラテジスト)のだ。