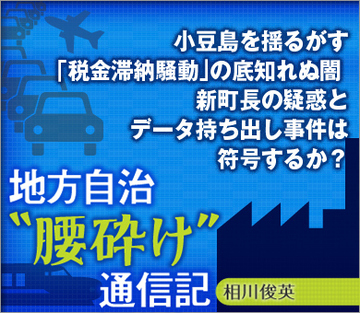1月17日、鳥取で尾崎放哉生誕130周年記念フォーラムが開かれた。東京大学名誉教授の上野千鶴子が「放哉の魅力」について講演し、その後それを語る座談会の司会を私が務めた。
種田山頭火と並ぶ放浪の俳人の放哉では、「咳をしても一人」という句が有名だが、私が最初に放哉の名を知ったのは学生時代である。当時入っていた学生寮(山形県庄内地方出身者のために東京駒込にあった荘内館)の寮監が「心の花」同人の佐藤正能という歌人で、俳句にも詳しかった。その先生は東京帝国大学法科卒だったが、同じ東京帝大法科出の放哉に親近感を持っていたのかもしれない。
卒業していく4年生のアルバムに、何か言葉を引くのに、ある先輩のそれに寮監は放哉の次の句を寄せたのである。
〇漬物桶に塩ふれと母は産んだか
東京芸術大学の学生だったその先輩は、母一人子一人で育った人だったが、それを読んで、「見透かされた」と言っていた。
その時のその反応とともに、放哉の名は私の胸に深く刻みつけられた。そして、後年、吉村昭の『海も暮れきる』(講談社文庫)と出会って、私の放哉熱は一挙に昂まる。もう四半世紀も前になるが、高松に行った際、作家の西村望に案内されて、小豆島に渡り、放哉の墓に参ったほどである。放哉は鳥取に生まれて小豆島で亡くなった。
旧制一高、東京帝大法科卒という
エリートコースからの転落
人はそれほど起伏の多い人生を送るわけではない。それだけに山の頂と谷底の双方を経験したような人に惹かれる。
羽目をはずすというか、枠をはずれた放哉に不思議にサラリーマンが共感するのは、サラリーマンが日々、束縛の多い人生を送っているからである。
すべてを捨ててしまいたい。しかし、捨てられない。その行ったり来たりの問答の中で、下へ下へと降りて行った放哉の存在が他人とは思えなくなってくる。
〇何がたのしみで生きてゐるのかと問はれて居る
こんな放哉の句に接したとき、ドキッとしないサラリーマンはいないだろう。