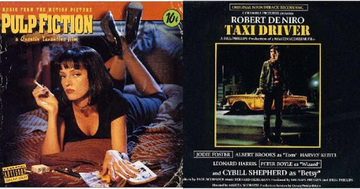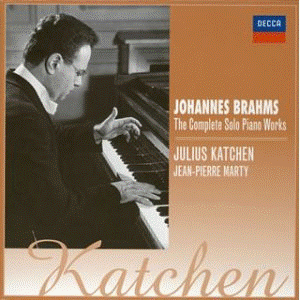音楽の授業で習うクラシックは現代音楽にも深く通じている?
音楽の授業で習うクラシックは現代音楽にも深く通じている?
世の中には、音楽が溢れています。ロック、ジャズ、ブルース、Jポップ、演歌・歌謡曲、レゲエ等のワールドミュージック、そしてクラシックまで百花繚乱。素晴らしいことですね。でも、クラシック音楽には常にある種の権威がつきまといます。中学、高校の音楽の授業は堅苦しく、歴史に残る名曲だからと聴かされても、即座に好きになれるようなサウンドではありません。
とは言っても、クラシック=古典。作曲されて100年、200年、更にはそれ以上の時間を超えて、今も演奏されている訳です。只事ではありません。そこに相当のチカラが宿っています。でなければ、単なる時代の所産として瞬く間に忘れ去られてしまったでしょう。
そのクラシック音楽をもっと等身大で親しみやすく紹介したいと思います。小栗勘太郎&ダイヤモンド流のクラシック音楽入門です。取り上げるのは、クラシック音楽の王道中の王道であるバッハ、ベートーヴェン、ブラームス。そう世に言う『独逸3B』です。
3Bは、今では権威の権化の如く扱われています。彼らの音楽の持つ強靭なチカラを考えれば当然かもしれません。しかし、彼らが生きた時代においては、彼らの音楽は時代の遥か先を行く前衛そのものだった、と言っても過言ではありません。であるが故に、時代を超えることができたのです。そのスピリッツにおいて、ロックやジャズの音楽家に近い感性を持っていたとも言えます。その証拠に、彼らの音楽は今も強烈に息づいています。
20世紀最先端ロックを彩ったバッハ
ピアノを本格的に習う人であればある段階で必ず「平均率クラヴィーア曲集」(写真はグレン・グールド盤)の中から数曲は弾くはずです。“第1巻、第6番ニ短調プレリュード”は、メランコリックな旋律が印象的な佳曲です。この曲はプログレッシブ・ロックの雄エマーソン・レイク&パーマー(ELP)の最高傑作「タルカス」(写真)に収録されている“オンリー・ウェイ”で登場します。教会のオルガン的な響きで幕を開ける荘厳な賛美歌的な雰囲気の曲ですが、途中ドラムとベースが参加して楽曲全体が加速するところで、バッハの平均率が顕れます。完全に曲に同化していて、賛美歌がロックに変貌遂げるのです。その上で、バッハの原曲を聴くと、そこにはリズムや旋律、更には転調を繰り返す和声の展開があり、ロック/ジャズ的なエネルギーが潜んでいることが分かります。ELP「タルカス」が発表されたのは1971年、バッハが平均率・第1巻を完成させたのが1722年です。250年を経て、20世紀の最先端ロックを彩った訳です。
余談ですが、ELPは、20世紀のロックとクラシック音楽を独自の視点で融合したバンドです。バッハに限らず、ムソルグスキー、バルトーク、コープランド、ホルスト、チャイコフスキー等々を引用し、音楽の本質を衝いています。代表作は「展覧会の絵」(写真)で、目から鱗の名盤です。
1685年生まれのバッハが作曲した数々の曲が現代にも使用されている例は枚挙に暇がありませんが、代表的な例を挙げます。