生き方(75) サブカテゴリ
第27回
「見とおし童児」(公開終了)
鹿児島県に伝わる民話に、「見とおし童児」という次のような話がある。「見とおし童児」はとてもよくできた話で、さまざまな味わい方があると思う。
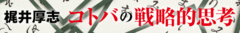
第24回
【島根県】 神様おわしますことが県民共通の誇り
全国で2番目に人口の少ない島根県ゆえに、島根県出身の人と知り合うことはごくまれである。だが近頃は、石見銀山が世界遺産に指定されたり、NHKの朝ドラの舞台になったりと、話題になる機会も多いようだ。

第4回
かつての会社員は、個人を殺し、上司や会社の理不尽にも耐え、職場に適応していくことが当たり前だと信じてきた。だが、近年では上司からの些細な心無い言葉、職場の冷め切った雰囲気、成果主義による確執をトラウマに、会社に出社できなくなった「引きこもり」社員が増加している。その背景にあるのは、個人の問題かそれとも企業の問題なのか。

第23回
【静岡県】 東のほうはのんびり 西はビジネスにシビア
今でこそ全国でも13番目に面積が広い静岡県だが、江戸時代までは3つの国に分かれていた。全体的には、温暖な気候の影響で穏やかでのんびりしているが、それぞれの地域で人々の気質も大きく異なっている。

第2回
社内恋愛は「あり」と思う女性が77.5% “ソフトな肉食系”男子が一番人気
「婚活時代」とも言える現代だが、さがしものは意外に近くにあるのかもしれない。「社内恋愛」することは「あり」だと思うと答えた女性が77.5%にのぼっている。同僚の男性を“恋愛対象”として捉えているようだ。

第8回
成果主義という人事評価システムが日本でも導入され、今日では多くの企業や組織でも用いられています。「タテ社会」の生んだ年功序列制の不公平感や理不尽さを払拭する合理的な方法として歓迎される一方、このシステムの問題点についても活発に議論されるようにもなってきました。生産率や効率性など「結果」を求めすぎて「質」を忘れがちになってしまっている人が多いようです。今回は、成果主義というシステムが人間の精神に及ぼすさまざまな影響について、掘り下げて考えてみたいと思います。
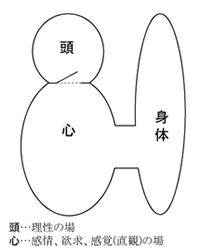
第1回
日本人はエコ・ブームに意外と冷静?エコ活動に消極的な「環境傍観派」が3割
環境意識の高まりやエコ政策の影響などで、環境に配慮した商品を購入する人が増えている。しかし、そうした商品を購入するにも関わらず、日常のエコ活動には消極的な「環境傍観派」が3割にものぼっている。

第44回
ペン
パソコンのおかげで字を書くことが減ったという話を聞く。字を書く場面においてはペンが欠かせない。子供の頃は鉛筆であったが、いつの間にかボールペンを使うようになっていった。
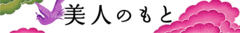
第22回
【滋賀県】 妙なプライドは持たず開放的で情報が早い
海がないとはいっても、海と見まがうほど大きな印象を与える琵琶湖があるせいか、滋賀県人は総じて開放的で気さくである。また、情報の早さという点では、下手をすると京都や大阪をもしのいでいた。

第21回
【佐賀県】 個を抑えて陰に徹し節約を旨とする
お笑い芸人の「はなわ」や映画にもなった「がばいばあちゃん」のおかげもあってか、近頃にわかにメジャーになりつつある佐賀県。しかし、それでもなお、全国的にはまだまだその名が知られているとはいいがたい。

第7回
マニュアルは覚えられるのに、マニュアルのないことにはお手上げ。最近、いろいろな組織の中で、「自分で考える」力のない人が増加していることが問題になっているようです。「記憶力が良い」=「頭が良い」と思われがちですが、このように偏った「頭」の使い方ばかりしているうちに、「自分がわからない」といった行き詰まりに陥ってしまったケースが少なからず存在します。そこで今回は、「人間らしい思考力とはどういうものか?」というテーマについて考えてみたいと思います。
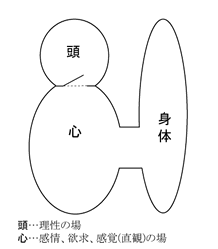
第43回
写真
写真好きな女性は多い。旅行中の女性を見ると、写真を撮るためだけに来ているのではないかと思えてしまう人がかなりいる。しかもあまり楽しそうではなく、義務感で撮っているように見える人もいる。
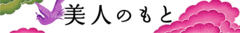
第20回
【埼玉県】 県民意識は薄く首都東京を隣で支える
「埼玉都民」という、言い得て妙な言葉がある。実際の話、埼玉県内に住んで就職・就学している391万人のうち28.8%、約3分の1は県外(ほとんどは東京)に通っているのだ。

第19回
【高知県】 旺盛な反骨精神 自由奔放で独創的
県民性を考えるにあたってのポイントにはいくつかあるが、私が重視していることの一つに「辺境度」がある。これは、その県が地理的な中心地からどれほど隔たっているかを意味している。

第42回
蓋
ペンの蓋を閉め忘れて服を汚してしまっている人を見かけることがある。かわいそうだ。大事な服を汚してしまっていることもかわいそうだが、たいていそういう人は美人ではないのだ。残念だ。
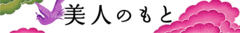
第30回
ずっと子供の頃から、イースター島って何となく無人島のように思っていた。でも実のところ人の世界観は、こうした淡い思い込みで形作られている。僕は自分の淡いイメージを書き換えた。
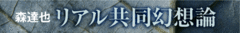
第6回
――私は、何をやっても長続きしないんです。若い世代を中心に、このような悩みを訴える方が少なくありませんが、特に自己愛(自分自身を愛すること)がうまくいっていない方たちによく見られる悩みでもあります。大概は、いわゆる「良い子」的な従順さと勤勉さの持久力を生んでいた「かりそめのモチベーション」であり、本人の意思に根差した「真のモチベーション」がつかめなくなってしまっているのです。
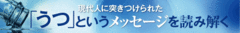
第26回
「三船の才」(公開終了)
詩・歌・管弦のいずれにも通じていることを、三船の才という。999年に藤原道長が催した舟遊びで、公任は和歌の舟にのり、名作をものにして絶賛された。
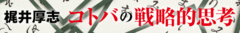
第41回
傘
天気予報を見ていると、時々、「午後は雨が降りだしますので、折りたたみの傘をお持ちください」と言うお天気キャスターがいる。なぜ、いちいち「折りたたみ」と言うのか。
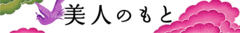
第18回
【群馬県】男も女もカラっと陽気で一本気
昔から「かかあ天下とからっ風」が上州の名物だとされている。「かかあ天下」だから、亭主は尻に敷かれっぱなしなのかと思われがちだが、そうではない。
