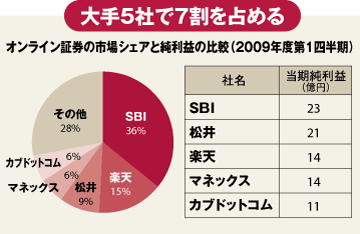週刊ダイヤモンド編集部
09/09/12号
政権交代にも大きな影響力!「新宗教」巨大ビジネスの全貌
民主党の圧勝と自民党の歴史的敗北で終わった衆議院選挙。実は、新宗教団体がこの政権交代の一因となっていたのをご存知でしょうか。今回の特集は、総選挙の明暗を分けた新宗教代理戦争の内幕をご紹介します。
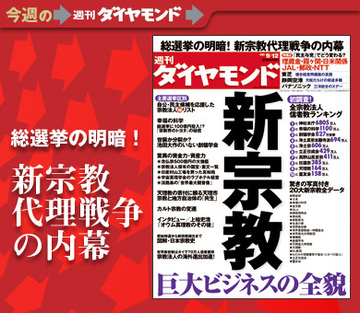
第368回
カーボンフットプリントって何?今秋にも登場する環境基準の狙い
「カーボンフットプリント」と呼ばれる環境関連の表示制度が今秋にも日本でスタート。経済産業省の試行事業だが、国際基準策定議論で日本に有利な基準づくりをリードしたいとの思惑もあり、普及に必死になっている。
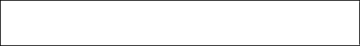
第84回
昨年5月、環境マネジメント研究所代表取締役の玉木康博は、賭けに出た。すべての事業をストップして、新製品開発に集中したのである。玉木が社運を賭けた新製品、それは「省エネの達人」(エネ達)である。

第92回
石井リーサ明理光を操り、夜を見せる
1999年、留学先のパリを拠点に選び、ノートル・ダム大聖堂のライトアップのリニューアルにかかわった。名前は明理(あかり)。照明デザイナーのパイオニアである母、石井幹子が名づけた。

第168回
セブン本部とオーナーの深まる溝チェーンに広がる不満と動揺
セブン-イレブン・ジャパンのフランチャイズチェーンに加盟するオーナー10人が24時間営業を強要されたとして本部を提訴した。また、弁当“見切り販売”問題も含め、本部とオーナー間のいざこざが続いている。
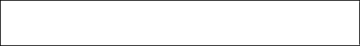
第367回
いまや世界の株価動向を左右中国株式市場の“構造的問題”
8月5日から19日までの2週間で、上海総合指数は20%下落した。4日、同指数は年初来85%上昇となる最高値を付けていた。日本の市場関係者は、今回の下落は一時的な調整にとどまるというのがおおかたの見方だ。
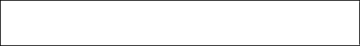
第167回
マツモトキヨシと業務提携ローソン店舗、競争力は強まるか
コンビニエンスストア2位のローソンとドラッグストア首位のマツモトキヨシホールディングスが8月24日、業態を超えて業務提携し、業界をにぎわせている。
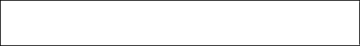
第19回
今春以降、国土交通省幹部たちは政府や金融機関はもちろん、日本航空との交渉案件を抱える企業の幹部たちに支援を訴え続けてきた。貨物事業の“結婚相手”として候補に挙がる日本郵船に対しても同様だった。
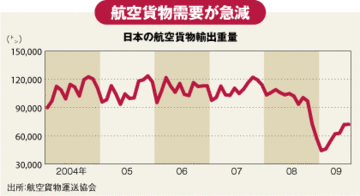
第166回
目玉サービスの利用抑制を顧客に要請した新生銀の評判
新生銀行の顧客が困惑している。ATMであれば、取引手数料が回数制限なく、無料で引き出せることを最大の売りにしていた「パワーフレックス口座」だが、新生銀行は引き出し回数を減らすよう求めているというのだ。
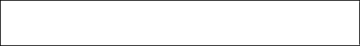
09/09/05号
限界集落化に歯止めをかけろ!「ニッポンの団地」を全解剖
日本人の「心の故郷」とも言える団地。かつて生活や文化の中心だった団地は、今や都会の限界集落と化しています。今回お届けする特集では、そんな団地の実態に迫りつつ、住宅政策のひずみについて考えます。
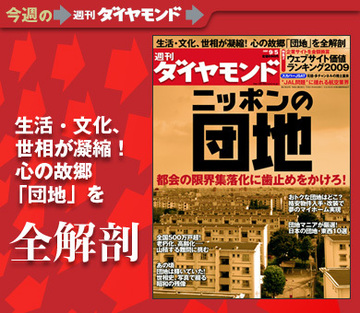
第58回
「濡れ手に粟」と言われてきた取引が米国市場から姿を消しそうだ。それは、取引所に入った注文を限られた業者にだけ一瞬早くオープンにするフラッシュオーダーだ。この仕組みを使う後出しジャンケンのからくりとは?

第91回
三浦皇成“未踏”の世界制覇に照準を定める
「武豊の再来」―。競馬学校時代からそういわれ続けた。2008年、武騎手の持つ新人最多勝記録69勝を21年ぶりに大幅に更新。武さんの本当のすごさは馬乗りにしかわからない。僕は一生追いつけないかもしれない。

第57回
感動を呼ぶサービスで世界の富裕層を魅了してきた超高級ホテル「ザ・リッツ・カールトン」。同業から異業種まで、世界各国でさまざまな企業やビジネスマンがこぞって学ぶ同ホテルのサービスは、未曾有の世界同時不況でも通用するのか。ラーニングエッジ主催のセミナー講演で来日したリッツ・カールトンの教育機関責任者、ダイアナ・オレック氏に聞いた。
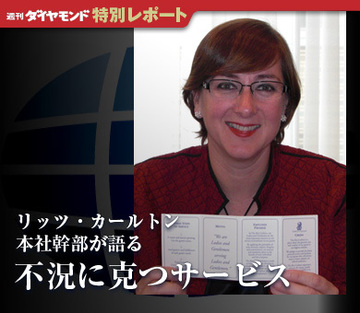
第165回
ニッセンが仕掛けるアウトレット消費者とメーカーの支持得て急伸
通信販売大手のニッセンが運営するインターネットアウトレットモール“BRANDELI(ブランデリ)”が好調だ。2009年度通期の売上高は、目標とする8億円(前年比2.1倍)を超える見通しだ。
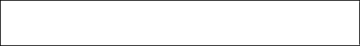
第83回
従業員数10人未満の町工場。ユビキタスエナジーの社員が油まみれになりながら、ところ狭しと並ぶ旋盤やフライス盤を止めたり動かしたりして、どの程度の電力を使用しているかを見極めていく。

第366回
緒戦は韓サムスン電子に軍配LEDテレビ新市場争奪戦
薄型テレビの覇権争いが新次元に突入した。火ぶたを切ったのは韓サムスン電子だ。今年3月、液晶パネルのバックライトに、CCFLの代わりにLEDを採用した「LEDテレビ」を投入した。
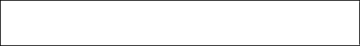
第164回
それでも単独では生き残れないサッポロ・ポッカ連合の次の一手
ビール系飲料大手のサッポロホールディングスは8月14日、飲料大手のポッカコーポレーションとの資本提携を発表した。だが、両社の提携を脅威と受け止める業界関係者は多くない。
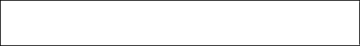
第163回
巨大化する三菱ケミカルHD難題は国内石化事業の再構築
三菱ケミカルホールディングスが、三菱レイヨンとの買収交渉を進めている。交渉が成立すれば、三菱化学をベースに、旧田辺製薬をグループに取り込むなど拡張を続けてきた“大三菱化学”がさらに巨大化する。
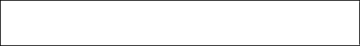
第56回
「日本の子供の学力が落ちた」として話題を呼んだOECD学習到達度調査(PISA)で、常に好成績のフィンランド。その秘密を、同国の教育庁参事官、マルヤ・モントネン氏に聞いた。

第18回
7月13日にオンライン証券大手の楽天証券が打ち出した株式委託手数料の値下げは、最大手SBI証券との熾烈な「手数料引き下げ競争」に発展している。7月14日、楽天証券の会議室内は異様な空気に包まれていた。無理もない。楽天は、前日に打ち出した株式委託手数料の改定で、業界最低水準を提示したはずだった。ところが同日中に、業界最大手のSBI証券が、楽天を下回る水準まで引き下げると発表したのである。その後、およそ1ヵ月のあいだに、楽天が5回、SBIが4回もの手数料改定を発表。両社がここまで最安値を競う背景には、いったい何があるのか。2社の手数料引き下げ競争の行方を追った。