
山崎 元
自民党総裁選で誰が選ばれようとも、実施を検討してほしい政策がある。候補者たちが訴える「格差の是正」「デフレ脱却」「年金の強化・効率化」を実現するならば、これ以上速やかに実行できて効果的かつ現実的な政策はない。それは、基礎年金保険料を全額国庫負担にすることによる、実質的な「ベーシックインカム政策」だ。この政策のすばらしさをぜひお伝えしたい。

自民党の総裁選で筆者が注目している政策は、河野太郎氏が提言した「最低限の年金を保障する案」だ。ぜひ実行に移すべきで、国民年金(基礎年金)の財源を全額税金負担にするところからスタートすれば、「いいことだらけ」といえる。その八つの理由を解説しよう。

サントリーホールディングスの新浪剛史社長が、「45歳定年制」の導入について提言したことが波紋を呼んでいる。この発言のどこが「ダメだった」のか、考えてみよう。そして、定年制を巡る問題の本質的な解決には、別の提案の仕方があると考えているので、そのアイディアもお目にかけたい。

菅義偉首相が自民党の総裁選に立候補しない意向を表明したことで、「次の首相選び」が始まった。この政局に絡んで評価を上げた人、そして下げた人は誰か。次の首相候補とされる5人の期待と心配な点も踏まえて、読者にも一緒に考えてみてほしい。

本稿では「経済がマイナス成長に陥っても資本主義は成立するのか?」を考えたい。筆者の結論は「成立する」である。また、資本主義は現在、格差や環境破壊などの問題と結び付けて論じられることが多く、「行き詰まり」を感じる読者もいるかもしれない。しかし、そうした問題は資本主義を捨てることではなく、手直ししつつ使うことで解決するのが、現実的・相対的に優れているように思う。それらの理由を説明しよう。
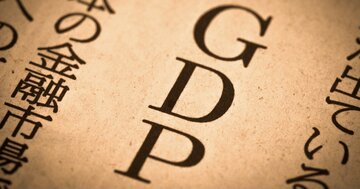
日本でも「SPAC(特別買収目的会社)」の導入に向けた議論が起こっている。米国ではSPACを通じたベンチャー企業の上場が流行している。しかし、筆者の率直な印象は「いかにもうさんくさい」。日本でのSPAC導入が実現しないことを切に願って、反対する三つの理由を述べる。このような矛盾した、しかも汚い仕組みは、日本の証券市場に必要ない。
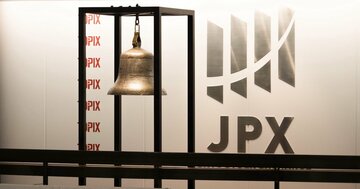
新型コロナウイルスの変異株「デルタ株」の感染が拡大し、世界中を不安と混乱に陥れている。しかし、われながら「強気」の意見とは思うものの、本稿で述べる三つの理由から、日本株投資に悲観的になる必要はないと考えている。その理由を解説する。

日本のインフレ率が上がらない理由として、「消費者物価指数は『貧乏人物価指数』である」という仮説を考えてみた。消費者物価に大きな影響を与えているのは、お金持ちから見ると相対的に「貧乏人」であるところの庶民(普通の人たち)だ。この仮説を突き詰めていくと、インフレ率2%を達成する鍵がお金持ちと貧乏人の格差解消であり、そのための秘策が「ベーシックインカム」であるという結論に達する。その理由を解説したい。

霞が関で進めようとしている「FAX廃止」に官僚たちが抵抗しているという。それなりに反対する理由はあるようだが、筆者は霞が関にこそFAX廃止を強く勧めたい。真面目に仕事をする官僚にとっては、国民の期待に応え、自分自身を守ることにつながるからだ。

2022年4月に東京証券取引所が市場区分を再編する。東証第1部などを含む現在の4市場から「プライム」「スタンダード」「グロース」の3市場体制へ移行するのだ。それを受けて、最上位市場であるプライム市場での上場を目指して苦心している企業があると聞くが、企業は「プライム落ち」におびえる必要はない。その理由とは?

東京オリンピックがまもなく開催する。もともと「開催反対」の意見が多かったことを考えると、大会の運営に一つでもミスがあると菅政権は強い批判を浴びることになるだろう。菅政権の現在の支持率を考えると、あと一つか二つのミスや不運で退陣が十分起こり得ると考えておく必要がある。そのときに株式市場として心配しなければならない二つの大きなリスクとは?

東京オリンピックは、おおむね無観客ではあるけれども開催されるようだ。そんな中で筆者は、アスリートにとってのオリンピックは、歌手にとっての紅白歌合戦に近いことに気が付いた。それを踏まえて、昨年の大みそかに無観客で開催された紅白歌合戦を東京オリンピックは手本とすべきだと主張したい。

東芝の後を追うように、三菱電機でも品質検査の不正という深刻な不祥事が発覚した。両社は共に「重電企業」と呼ばれ、どちらの不祥事も相当に「悪い」。しかし、投資判断においては、同じ不祥事企業でも評価が全く異なってくる。その理由をお伝えしよう。

6月25日、東芝の株主総会が行われ、取締役会議長を含む2人の取締役選任議案が否決される異例の事態に陥った。近年の東芝は「底なしに悪い会社」だ。本稿では、この東芝を巡る一連の不祥事から、一般市民及びビジネスパーソンにとって役に立つ「教訓」を七つ、いささかの皮肉と共に抽出したい。

本稿の結論から先に申し上げよう。「まん延防止等重点措置(まん防)」にあって課される、飲食店に対する営業時間と酒類提供、客の滞在時間に関する三つの制限(以下「まん防の飲食3制限」を撤廃すべきだ。数々の弊害があって、目に余る。

「2ちゃんねる(現5ちゃんねる)」の創始者であるひろゆき氏の発言から、「電話不要論」が盛り上がっている。筆者も電話によるコミュニケーションは大嫌いだ。不愉快で不適切であると考えている。その理由を五つご紹介する。

政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長が、東京オリンピック・パラリンピックの開催に警鐘を鳴らしたことで大騒動が巻き起こっている。それに対する政府の対応はお粗末なもので、政治家としての能力不足を露呈した。今回の問題は、政府が尾身会長の専門性と権威を自分たちに都合のいい内容ばかりに使おうとしていることにある。尾身会長の扱い方いかんで、「政府が使う専門家」の価値が大きく動くことになるかもしれない。

3度目の緊急事態宣言が2度目の延長を迎えた今、個人の経済生活で必要なことをあらためて確認しておこう。筆者は、コロナによって資産運用の方針を変更する必要はないと考える。一方で、コロナによる働き方の激変がもたらした「浮いた時間」の使い方は、ビジネスパーソンの個人差を広げるとみる。

日本酒「獺祭」の蔵元が、新聞の一面全体を使った意見広告を出し、飲食店を守ることの重要性を主張した。また、時短営業や酒の提供禁止など飲食店に課されている新型コロナウイルス対策の有効性にも疑問を呈した。本稿ではその意見広告へ全面的な賛成を示すとともに、飲食店向けの新たな六つのルールを提案したい。

「インフレ」が久しぶりに株式マーケットで注目を集めている。本格的なインフレが来ると見る向きは少ないだろうが、今後もインフレが市場の材料として登場することが少なからずありそうだ。そこでインフレと株価、および株式投資との関係を「方程式」を使いながら整理しよう。またその結果、投資家がインフレ懸念相場で何をすべきかを解説する。
