
山田 久
2022年は春闘賃上げ率が21年より上向きそうだ。人手不足感も強まると予想される。ただ、人手不足にもかかわらず長期失業者が増える懸念がある。それはなぜなのか。
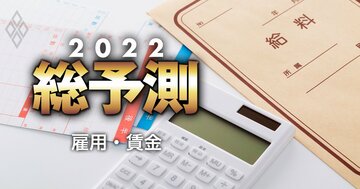
岸田政権の「賃上げ政策」の多くは、安倍政権で道半ばで終わったものだ。第三者委員会によるデータに基づいた賃上げ水準の設定や生産性向上の取り組みなど、成果を上げる新たな工夫が必要だ。

岸田新政権は「ウィズコロナの経済再開・再生」と「コロナ禍であぶり出された構造問題」に取り組む必要がある。具体的にはデジタル化やグリーンの推進、セーフティーネット再構築などが喫緊の課題だ。

21年春闘の賃上げ率は8年ぶりに2%を下回る見通しだ。コロナ禍や「官製春闘」の終わりによるものだが、このまま賃上げの勢いが弱まり“賃金下落時代”に戻らないためにも健全な賃上げ圧力を後押しする政策が重要だ。

#14
特集『総予測2021』(全79回)の#14では、日本総合研究所副理事長である山田久氏に2021年の雇用・賃金の動向について予想してもらった。景気が回復に向かっても、雇用のミスマッチが失業率改善の足かせとなりそうだ。産業間、部門間の格差もおおきくなっている。雇用情勢に厳しさが残る状況下では、賃上げも鈍く2%割れとなる公算が大きい。

コロナ禍が長引く中、政策運営は「医療・経済・財政のトリレンマ」のバランスをとる意識が重要だ。経済再開を着実に進める必要はあるが、「Go To」事業は対象を絞り込み需要喚起策から業界再生策に設計し直すべきだ。

リーマンショックを超える「大失業時代」がやって来る――。労働市場の問題に精通する日本総研の山田久副理事長は、コロナ禍の影響が雇用に跳ね返るのはこれからだと警鐘を鳴らす。山田氏がわかりやすく解説する全3回の動画特集「コロナ禍で大失業時代はやって来るのか」。第3回は、パンデミックで働き方はどう変わるのかを考えたい。テレワークやジョブ型雇用の課題に、どう取り組めばいいのか。

リーマンショックを超える「大失業時代」がやって来る――。労働市場の問題に精通する日本総研の山田久副理事長は、コロナ禍の影響が雇用に跳ね返るのはこれからだと警鐘を鳴らす。山田氏がわかりやすく解説する全3回の動画特集「コロナ禍で大失業時代はやって来るのか」。第2回は、コロナショックの影響を被った雇用を再生するためには、どんな政策が必要かを考えよう。

リーマンショックを超える「大失業時代」がやって来る――。労働市場の問題に精通する日本総研の山田久副理事長は、コロナ禍の影響が雇用に跳ね返るのはこれからだと警鐘を鳴らす。山田氏がわかりやすく解説する全3回の動画特集「コロナ禍で大失業時代はやって来るのか」。第1回は、コロナショックで我々の雇用はどこまで悪化するのかを考えよう。

コロナ後の日本経済の成長には、内需主導の成長と産業構造の転換を加速することが重要な課題だ。それを担うスガノミクスの成功は、持続的な賃上げと労働移動の円滑化を実現させる枠組み作りが鍵になる。

新型コロナ問題の長期化で、来年半ばまでには100万人の雇用喪失が見込まれる。数十兆円規模の「雇用安定化基金」を創設、企業の資金繰りや雇用維持支援、休業所得補償、働き方の変化などの構造改革を支援することだ。

日本では集団的労使関係は大手の正社員に限られ、企業内労働組合のため「一企業での雇用維持」にこだわる特異な労使関係だ。賃金を下げても不採算事業を残そうとするので、低収益・低成長・低賃金の悪循環に陥っている。

ほどなく「オリンピック・イヤー」が始まる。数十年後に振り返ったとき、2020年はどのような年として認識されるのか。そして、取り組むべき課題は何か。内外の経済で不透明感が続くなか、日本経済にかかる雲を吹き飛ばすための成長戦略の柱を考える。

今年の春闘は、アベノミクスの成否ひいては日本の行く末を大きく左右する正念場だ。企業に賃上げ余力はある。一方で先行き不透明感が強いなか容易ではないのも確かだ。賃金抑制による縮小均衡を脱し、好循環を実現する方策は何か。

日本経済の現状で懸念されるのは、所得面と支出面のギャップだ。このまま企業の慎重姿勢が変わらなければ、景気後退局面入りもあり得る。問題の背景には、政府の成長戦略に明確なビジョンとストーリーが欠けていることがある。

第6回
成長戦略の本丸は雇用分野の改革だ。その点「日本再興戦略」は、概ね妥当な基本的な課題認識を示したが、改革の本命ともいえる「正社員改革」については踏み込み不足。賃金抑制を狙う「賃金限定正社員」が増加する懸念がある。
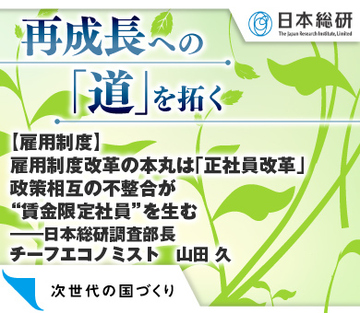
第2回
2014年を予想する上で、ポイントは何か。消費税増税の実施、緊張高まる東アジア外交……。経営者、識者の方々に、14年を読み解くための5つののポイントを挙げてもらった。第2回は日本総研調査部チーフエコノミスト・山田 久氏。
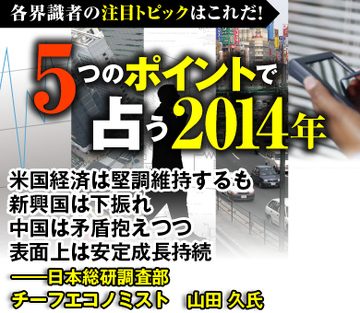
第9回・最終回
現段階でのアベノミクスは「未完の政策体系」である。成長戦略を効果的なものとするためには、従来型の供給力強化策が成長戦略の「前工程」であり、「後工程」として需要力強化策=家計所得増加策に取り組む必要があることを述べる。
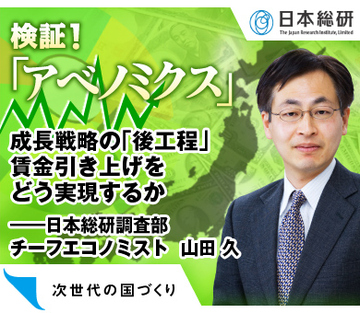
第1回
安倍政権の経済政策である「アベノミクス」は上々の滑り出しを見せた。だが、まだそれは「期待」を転換させつつある段階に過ぎず、政策体系としては未完成だ。本シリーズでは「建設的批判」の観点からアベノミクスの検証・提言を行っていく。

第8回・最終回
最終回となる今回は、社会システムにおける社会保障システムのあり方を論じたうえで、わが国で「市場主義3.0」モデルを実現するための、政治プロセスの改革について提言する。
