
山田 久
日本の賃金は長年停滞が続いたものの、ここ2年連続で高水準の賃上げが実現している。またコロナショックからの回復や働き方改革の進展もあり、人手不足が成長課題として浮上している。高賃上げは今後も続くのか。2026年の雇用と賃金の先行きと課題を展望する。

高市新首相は安倍政治の継承を掲げ経済政策も「積極財政・緩和維持」路線だが、アベノミクスの再現を狙うなら問題含みだ。当時と違い人手不足が深刻化しており、需要拡大は投資増に十分つながらずインフレを助長する。安易な労働時間規制の緩和も一部の働き手の過剰労働を深刻化させる懸念がある。

参院選大敗の石破政権の行方は不透明だが、どのような政権枠組みになっても経済政策の最優先課題は賃上げ継続だ。トランプ関税による企業収益圧迫や外需減少、円安による輸入価格上昇で実質賃金のマイナス拡大も懸念される。景気底割れを防ぐためにも来春闘は正念場だ。

トランプ関税はこれから本番の中小企業の賃上げにも影響が懸念されるが、それでも「高い賃上げ継続」で優秀な人材を確保することは重要だ。人手不足対応だけでなく、グローバル経済での生き残りを考えると米国を除いても自由貿易圏は十分な市場規模があり、競争力を持つ産業基盤を作る必要がある。

2025年春闘が始まったが、このところ大企業の賃上げ率は高いが、平均賃金の伸び率は中小企業が上回る。どちらも人手不足や人材確保競争の激化が背景にあるが、中小企業は賃上げ余力がない中で賞与などを増やして対応しているのが現状だ。日本経済の活性化には中小企業の賃上げ力をいかに高めるかが鍵だ。

#15
2024年は大手企業の春闘賃上げ率が33年ぶりの高さとなった。しかし労働需給の指標を見ると、有効求人倍率には一見不可解な現象が起こっている。その要因を探り、25年の雇用・賃金の見通しを分析した。
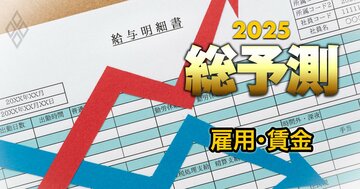
総合経済対策が閣議決定されたが、石破政権の経済政策の本丸ともいえる実質賃金プラス化を目指した「2020年代中の最低賃金1500円実現」や「103万円の壁」解消は疑問や課題があるうえ、実質賃金押し下げの原因の一つとなっている交易条件の悪化への対応は見過ごされている。

長く続いたデフレの「ノルム」は変わったのか。企業の価格転嫁や賃上げの広がりはあるが、今回のインフレ局面での価格転嫁率は米独の4~6割にとどまり、賃金上昇も世界的な供給構造変化や国内の人手不足に起因する。健全な物価上昇の前提になる生産性上昇を、大企業と中小企業の二重構造や雇用重視の労使関係、保護政策が妨げている構造は変わらないままだ。

長く続いたデフレの「ノルム」は変わったのか。企業の価格転嫁や賃上げの広がりはあるが、今回のインフレ局面での価格転嫁率は米独の4~6割にとどまり、賃金上昇も世界的な供給構造変化や国内の人手不足に起因する。健全な物価上昇の前提になる生産性上昇を、大企業と中小企業の二重構造や雇用重視の労使関係、保護政策が妨げている構造は変わらないままだ。

春闘の高い賃上げなどで賃金・物価の「好循環」実現が見通せるとして、日本銀行はデフレ時代からの金融政策の正常化に踏み出したが、賃金や消費は二極化し物価上昇も円安などが要因。バブル崩壊前とは賃金や物価、消費の構造は様変わりしており、格差社会の本格化がむしろ懸念される。

24年春闘の賃上げ率は昨春闘を超える3%台後半から4%になる見通しだが、中小企業やパートなどを含めた賃上げ率とは乖離がありマクロの実質賃金がプラスになるかは微妙だ。とはいえ賃金が経済の持続的成長の鍵になる中で春闘の成果を地域の中小企業にまで波及させる重要性は一段と増している。

#26
物価上昇と人手不足が続く中、2024年の雇用・賃金の最大の焦点は、春闘での賃上げ妥結率だ。30年ぶりの高水準となった23年実績を上回り、「物価上昇に負けない賃上げ」を実現できるのか。法政大学経営大学院教授の山田久氏に、24年の雇用賃金の状況を徹底分析してもらった。
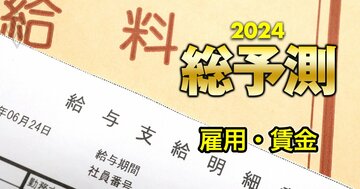
政府が経済政策で直視すべきは「2つの赤字」問題だ。とりわけ貿易赤字はいまの円安や物価上昇の要因でもあり、いずれ財政ファイナンスの不安定化を招き財政赤字と相乗的に日本経済を弱体化させかねない。

人手不足時代に活用が期待される生成AIだが、現状ではオフィス事務効率化には力を発揮するが、サービスや物流などの現場への活用は遅れている。深刻な現場の人手不足解消に役立たないどころか、オフィスで余剰を生み出しチグハグになりかねない。

「新しい資本主義」による「成長と分配の好循環」実現のカギは労働分配率と消費性向を同時に引き上げることだ。「骨太方針2023」は個別政策の寄せ集め感が強く、好循環実現のメカニズムやそれぞれの政策の位置付けや関連を明確にする必要がある。

23年春闘の賃上げ率は、29年ぶりに3%台に乗せる見通しだ。物価上昇への対応を経営側が意識したことが大きいが、逆に1年限りの盛り上がりで終わる懸念があり、経済の拡大均衡には来春闘での高い賃上げをすることがカギだ。

コスト高・インフレ経済へのパラダイムシフトと輸出競争力低下で「構造的円安時代」に入った。再生エネルギー推進や未来型輸出産業の育成、持続的な賃金上昇をセットで実現することが日本経済の重要課題だ。

日本企業は賃上げや値上げに慎重なノルムが根強く、社会的に賃上げ圧力をかけたり、適正な価格転嫁ができるような制度を整備したりして物価・価格体系のおだやかな上方シフトを促す仕掛けが必要だ。

世界はコストプッシュ型のインフレ経済に突入するとみられ十分な賃上げで実質賃金の低下を防がないと経済が縮小均衡に陥る。日本は財政再建の必要性を考えても賃金引き上げが経済活性化のカギになる。

今春闘で大手は軒並み「満額回答」だったが、ウクライナ問題などによる輸入原材料の急騰を中小企業が価格転嫁し賃上げができるのかや、賃上げ幅が物価上昇に追い付かず実質所得が増えないといった課題が残る。
