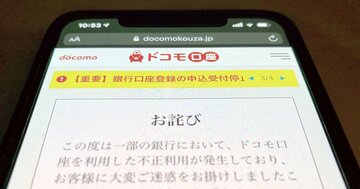加藤 出
2月13日夜に起きた地震で福島県と宮城県では震度6強が観測された。筆者が住む東京でも不気味な揺れが長く続いた。10年前の東日本大震災を思い出した人は多かったのではないかと思われる。

日本銀行がマイナス金利政策を開始したのは2016年2月16日だった。満5年となるが、この政策がインフレ率を目標の2%へ押し上げる効果は依然として表れてこず、出口は見えない状況にある。

日本銀行は3月の金融政策決定会合で、株式の指数連動型上場投資信託(ETF)購入額の柔軟化を発表すると思われる。しかし、同政策の出口政策は全く見えてこない。

「具体的なことはこれから点検しますので、先取りして申し上げるわけにはいきません」。黒田東彦・日本銀行総裁は1月21日の記者会見で、3月に公表を予定する超金融緩和策の「点検」についてそう語った。

「今はそれについて話す時ではない」。米連邦準備制度理事会(FRB)のジェローム・パウエル議長は、1月15日の討論会で今の超金融緩和政策からの出口についてそう語った。
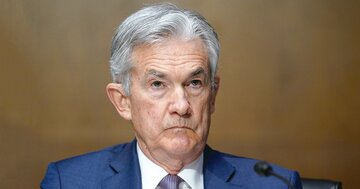
中国各地でデジタル人民元のテスト運用が拡大されている。江蘇省蘇州市では昨年12月、抽選で選ばれた10万人のスマートフォンに買い物で使える200元(約3200円)のデジタル人民元が配布された。

欧州連合(EU)離脱により、英国の国際社会における影響力は顕著に低下する恐れがある。

#15
特集『総予測2021』(全79回)の#15では、2021年の日米の金融政策の動向を予想した。マイナス金利は弊害が大きいと考えるFRBには効果ある追加緩和手段が尽きている。一方、コロナ禍対策で国債が大量発行される状況下で、日本銀行は現行の金融政策を引き締め方向には変更できないだろう。

キャッシュレス先進地域である北欧のスウェーデン・ストックホルムやデンマーク・コペンハーゲンでは近年、「現金お断り」の表示を掲げる小売店やレストランが増えている。多くの人々が現金を持ち歩かなくなっており、それでも事業に影響はない状態になっている。

11月の米国の非農業雇用者数は前月比24.5万人増だった。6月は478.1万人増、8月は149.3万人増、10月は61万人増だったので急減速している。最近の新型コロナウイルスの感染拡大を考慮すれば、この先はさらに厳しくなるだろう。

ジョー・バイデン次期米大統領は、副大統領時代の2011年8月に中国・北京を訪れた。習近平国家副主席(当時)との会談を終えた彼は、市内の大衆食堂「姚記炒肝店」で昼食を取った。

新型コロナウイルス対策のために日本政府は今年、財政赤字を急拡大させた。海外諸国と比べると、それはどういった規模感になるのか?

先進国の中央銀行の中で、リテール向け中央銀行デジタル通貨(CBDC)発行に最も近い位置にいるのはスウェーデンのリクスバンクだ。それ故、同行の動きには注目が集まりやすい。しかしステファン・イングベス総裁は最近、開発中のCBDC、eクローナについて過度な期待を抱かぬようけん制した。
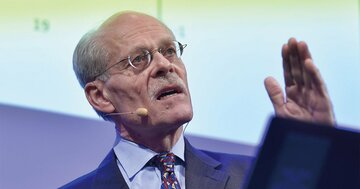
「ニューヨークに来て30年以上たつが、こんなことは初めてだ」。電話で話した友人が嘆いていた。彼のオフィスがある高層ビルの1階には多数のファッション店が入居しているが、米大統領選挙の週に暴動を警戒して店頭から商品を撤去した。

「もっと安価な貨幣をもっと大量にという圧力はつねに存在している政治的力であり(略)金融当局はそれに抵抗することがまったくできなかった」「政府が提供する貨幣を使い続けるほか選択肢がないという状況においては、政府がさらに信頼するに値する存在になるという望みはまったくない」。これはフリードリヒ・ハイエクが1974年にノーベル経済学賞を受賞した翌年に著した『通貨の選択』(『貨幣論集』収録)における記述である。45年も前の論考だが、現在の世界経済への示唆を感じた人も多いのではないか。
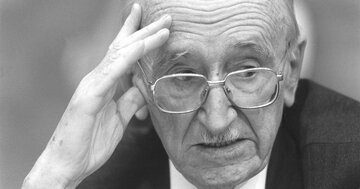
先日、3泊4日で四国旅行に出掛けた。「Go Toトラベル」キャンペーンを利用してみたところ、宿泊料が35%引きとなり、さらに15%分の地域共通クーポン(お買い物券)が配布された。大人4人だったので、それぞれの宿泊地で結構な額のクーポンを手に入れた。

10月9日に日本銀行、米連邦準備制度理事会(FRB)、欧州中央銀行(ECB)を含む7中央銀行は、中央銀行デジタル通貨(CBDC)の方向性を示す報告書を公表した。

10月11日開催のフォーミュラワン(F1)アイフェルグランプリで最速ラップを記録したのは、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンだった。ホンダは2021年シーズンを最後にF1から撤退すると発表したが、あと数年でチャンピオンに届きそうなだけに、レースファンとしては大変残念だ。

日本銀行は10月29日に先行きのインフレ率予想を発表する。2022年度まで見渡しても目標(2%)を大幅に下回る状態が続くことがあらためて示唆されるだろう。

ドコモ口座の預金流出事件が人々に不安を抱かせている。金融のデジタル化は利便性を向上させ、物理的な窃盗や強盗を減少させる。ただ、その代わりに電子的な窃盗や詐欺のリスクを台頭させる。