
加藤 出
円安とインフレによって国民の不満が高まりつつある。事態がさらに悪化し、政府・与党が狼狽するような状況になれば、日本銀行による「不意打ち」の政策変更リスクが高まる。本来、中央銀行が想定外の動きをすることは悪手だが、日銀にはそうせざるを得ない状況に追い込まれかねない苦しい事情がある。

ドル円相場が一時1ドル=126円台に達し、円安が止まらない。金融緩和の継続を誇示するたびに円を売り込まれる状況に、日本銀行のかじ取りは一層困難を極めている。この板挟みを巡る「最悪シナリオ」として想定されるのは、桁違いの金利上昇圧力だ。それは、3月末に1ドル=125円を突破するきっかけとなった、海外ファンド筋による10年国債の空売りによる圧力の比ではない。

ウクライナ情勢という波乱要因がある中でも、欧米の中央銀行は金融引き締めの方向に動いている。一方、日本にその気配はない。その違いを生んでいる最大の原因は、賃金の伸びの差にあると思われる。日米英独4カ国における賃金の推移を示したグラフと、米国で起きている賃上げなどの生々しい描写を基に解説していこう。

日本と同じくマイナス金利政策下にあるドイツでは、個人の預金口座にまでマイナス金利を課している銀行が555行に上っているという。そのことで預金者から各地で訴えられている金融機関だが、収益悪化に耐えられず、背に腹は代えられない状況に追い込まれている。このドイツの現状は、日本の近未来かもしれない。

世界的にインフレの足音が聞こえてくる中、2022年の主要な中央銀行の金融政策はどうなるか。FRB(米連邦準備制度理事会)が利上げに踏み切ることは確実。ECBと日銀は利上げに踏み切ることはなさそうだ。
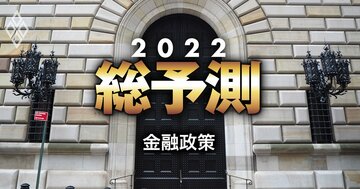
日本では「コロナ対策で一定のバラマキ政策はやむなし」という雰囲気になっている。ところが世界を見渡すと、来年から増税を実施すると発表した英国をはじめとして、早くも財政規律とのバランスを取り始めている。日本と世界の間に広がる衝撃的なまでの格差の実態をお伝えしたい。

原油や資源の価格高騰と円安が同時進行することで、輸入コスト増加を招く「悪い円安」に関する議論が活発化している。しかし日本銀行は当面、為替相場に対するスタンスを変えることはないとみられ、「円安阻止」に動くことも当面ないだろう。その理由は三つある。そして、その理由の中には、日銀が「バズーカ金融緩和」の出口に向かう際の急所が見え隠れしている。

岸田文雄氏が自民党の新総裁に選ばれた。政府・日本銀行による今後の財政・金融政策はどうなるのか?岸田氏の発言や現状分析に基づき、次期岸田政権の金融政策に対するスタンスを予想する。ポイントは大きく三つだ。

8月27日、世界の金融関係者が注目する経済コンファレンス「ジャクソンホール会議」が開催された。そこで米連邦準備制度理事会(FRB)のジェローム・パウエル議長は、量的緩和策の縮小(テーパリング)を年内に開始する方針をあらためて示した。では、その時期や規模感はどうなるのか。中央銀行ウォッチャーである筆者が、物価の日米比較やパウエル議長を含むFRB幹部の見解を基に読み解く。

2020年時点の「コロナとの戦い」では、米国は「負け組」、日本は「勝ち組」のような気がしたが、情勢は激変した。日米の実質個人消費の推移を比較すると、コロナ禍以降の回復度合いに激しい差が付いているのだ。さらに驚くべきは、コロナ禍前までの消費拡大のトレンドにも大きな格差があること。その背景には日本の賃金の伸び悩みがある。コロナ前から続く、日本と世界の「賃金・消費」の衝撃的格差の実態をご覧に入れたい。

米連邦準備制度理事会(FRB)が金融緩和策の縮小に向けた議論を近く開始することを明示した。それとは対照的に、日本銀行は超緩和策の継続を決定している。現在の日銀幹部は皆、その在任期間中に同政策の出口を見ることはないと内心思っているだろう。そんな彼らに伝えたいのが、時の政権との全面対決すらいとわずに自ら始めた金融緩和策の「落とし前」を任期中につけて去っていった、歴代FRB議長たちの美学だ。

前日本銀行総裁の白川方明氏は4月20日、英貴族院の公聴会に参考人として呼ばれた。英国の議員らは、なぜ日本では量的緩和策を続けてもインフレが起きないのかなど、日本の状況を知りたがっていた。イングランド銀行の量的緩和策の長期化は英経済に何をもたらすのかという問題意識からだ。白川氏の説明を要約するとともに、日本の現状に当てはめて考えてみたい。

日本銀行は3月に実施した金融政策の「点検」を経てもなお、マイナス金利の深掘りは可能だと明言している。仮にそれが実現すれば、欧州のように個人の預金にまでマイナス金利が課せられる状況が日本に到来することが現実味を帯びてくる。ドイツでは個人預金にマイナス金利を課す銀行がこの数年で急増。今や300行以上の銀行がそうなっているという。

国際通貨基金(IMF)が新しい世界経済見通しを発表した。そこで、経済成長と財政状況の二つの観点から、世界における日本の立ち位置を確認したい。その分析から見えてきたのは、日本の財政資金の使い方があまりに非効率だという実態だ。その証拠となるグラフをお見せしよう。

3月に行われた日本銀行による金融政策の「点検」において、上場投資信託(ETF)購入策について事実上の縮小が示された。そのことで、同政策の是非を巡って再び議論が活発化している。そこで、筆者が考える日銀のETF購入策の「四つの問題点」と、同政策の出口戦略を成功させた香港の事例に学ぶ、重要ポイントを解説する。

筆者は、出張や旅行の際に外食の価格をチェックするのを趣味の一つとしている。そこで今回は、B級グルメやご当地グルメ、名物スイーツについて、1999年から現在までの22年間の価格変化に関する日米の調査結果を発表したい。そこから透けて見えてくるのは、日本が「先進国における低賃金国」であるという事実だ。

日本銀行は現行の超金融緩和策に対する「点検」の結果を、3月の金融政策決定会合後に発表する(雑誌発売時には発表済みの予定)。

日本銀行は3月19日に現在の超金融緩和策に対する「点検」の結果を公表する。その内容を推測する上で大事な点を三つ挙げてみよう。

「パーティーが盛り上がってきたらパンチボウル(酒が入った大きな器)を片付ける」。それが従来の米連邦準備制度理事会(FRB)の基本姿勢だ。実はFRBはこの方針を昨年大転換した。しかし、金融市場にその意図がうまく理解されておらず、それが最近の米長期金利の急騰の一因になっている。

米国の10年国債金利(長期金利)は1.3%台へ上昇している(昨夏は0.5%台)。バイデン新政権の大型財政景気刺激策案がインフレ率を高めると警戒されているからだ。
