大津広一
LVMHの強烈な高収益体質をセグメント情報から読み解く
LVMHの連結セグメント情報をつぶさに観察することで、同社の事業モデルと目指す事業ポートフォリオ経営について、見ていくこととしましょう。

何度も危機を脱してきたNetflixから学べる脅威的なキャッシュの使い方
コロナ発生によって飛躍的に成長したNetflixについて、キャッシュフロー計算書から観察を進めると、多くの学びを得ることができます。

なぜZARAの営業利益はユニクロの約2倍も高いのか
もはやZARAとユニクロは、ビジネスモデルの優劣を競っているのではなく、優れた異なるビジネスモデルを確立した2社の間で、最終的に財務、非財務面における世界一の企業価値をどちらが獲得するかを競っているようにも思えます。

米国株投資家なら知っておきたい英語のBS(右側)で頻出する英単語21選
少しでも英語の決算書に触れる機会のあるビジネスパーソンは必見です!

米国株をやっているなら絶対知っておきたい英語のBS(左側)で頻出する英単語28選
少しでも英語の決算書に触れる機会のあるビジネスパーソンは必見です!

米国株投資家必見! 英語のPLでよく出る英単語21選
少しでも英語の決算書に触れる機会のあるビジネスパーソンは必見です!

「売上原価」の意味が一瞬でわかる超簡単な考え方
「売上原価」という言葉は、なんと難しい表現かといつも思います。会計アレルギーのある方に対して、日本語の会計用語には、ダメ押しのようにわかりにくい言葉がたくさん登場してきます。まるで「わかる人だけついてくればいい」とでも言うように。

「債務超過」から「16兆円以上の現金を保有」できるほどに成長したアマゾンの信念とは
Amazonは、2004年まで債務超過(Capital deficit)企業でした。何年にもわたって巨額の赤字を計上し続けたからにほかなりません。それでもAmazonが破綻しなかったのは、赤字を計上し続けるほどの大きな投資が、顧客層の拡大、売上の成長に着実に結びつき、これを信じた投資家たちに支えられてきたからです。

販売台数が8年で23倍! Tesla急成長の秘訣とは
Teslaの決算数値のすべてのベースとなる自動車の納車台数は、2016年12月期を100とすると、2024年は実に2347まで成長していることがわかります。いかなる優れた製品であっても、このスピード感のまま研究開発から製造、物流販売、さらにはアフターサービスに至るまで事業を拡大し続けることは、並大抵のことではないでしょう。

なぜ、日本の半導体メーカーはNvidia/TSMCに比べて利益にありつけないのか?
Nvidiaの顧客、たとえばAmazon Web ServicesがNvidiaから1億円で購入したものは、TSMCで1100万円で製造されていることになります。ここに原材料や半導体製造装置を収める日本のメーカーは、全体の市場の規模からすると、それほど大きな分け前にはありつけない構造(市場規模の11%のみ)にあることも確認できます。

なぜ、家賃も人件費も高いZARAが「営業利益率19%」を叩き出せるのか?
トレンドを見極めながら何を造って売るかをギリギリまで待って判断するのがZARAなので、広告宣伝にはほとんど費用を使いません。少々高価に見える人件費と場所代も、総利益率60%近くをたたき出すための、広告に代わるマーケティングコスト(ファッションのトレンドをいち早くつかむと同時に、店舗自体が広告塔の役割)と考えれば、補って余りある店舗への投資ととらえることができるでしょう。

難解になりがちな「ROICの考え方」を現場社員に伝えるためにオムロンがしてきたこと【書籍オンライン編集部セレクション】
オムロンによる、ROIC道場、伝道師、翻訳式といった一連の取り組みは、ROIC経営を社員一人一人が理解し、納得し、行動してもらうことがいかに重要であり、またいかに容易でないかを物語っていよう。

【エーザイ】価値創造レポートに見る人的資本など非財務資本と株式価値の融合
「知的資本」「人的資本」といった非財務資本と、経済的な株主価値との整合性に疑問をもつ方もいるだろう。そんな方にとって一見の価値があるのが、エーザイの価値創造レポートである。
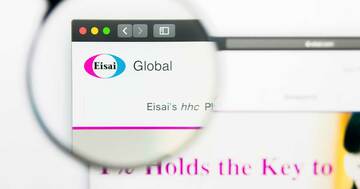
東証が開示好事例として取り上げるエーザイのROE
エーザイのROEは、2020年3月期時点で18.6%に達している。自社の株主資本コストについて「製薬企業はディフェンシブ銘柄であるものの、当社としては保守的に株主資本コストを8%と仮定している」というエーザイの考え方をさらに分析してみよう。

予測ROEを用いた3つの株価評価のアプローチ
ROEは株価に直結する指標であり、株価評価(バリュエーション)にも多用される。しかし、ROEが8%未満の水準では、いくらROEを向上させても、PBRが上がるのではなく、PERが下がるだけだ。

ROEの上昇は株価・配当の上昇に結びつくのか?
ROEが高くても株主が幸せであるとは限らない。株主が金銭的なリターンを得て幸せになるのは、キャピタルゲインとインカムゲインが得られたときでしかない――。たしかにROEが上昇しても株主は幸せにはならないが、この言説は本当だろうか?

【カカクコム】高ROE43.4%をブレークダウンして「総合力」を分析する
ROEは、株主のための指標であると同時に、企業の収益性や資産効率性、財務レバレッジという「総合力」を分析するうえでも大変有益な指標である。今回は、2020年3月期に連結ROEが43.4%と非常に高水準にあるカカクコムについて分析していく。

ソフトバンクがかつて重視した経営指標「EBITDA」の役割
EBITDAは現有する資産の稼ぐ力なのだから、売上高から効率的に稼げているか、有利子負債に見合った稼ぎ力か、そして株主までを含めた企業価値に見合った稼ぎ力かを判断するために、たいへん重宝する指標である。

ファーストリテイリングのROAが異常なまでに高いのはなぜか
ROAを高めるには、売上高利益率(収益性)と総資産回転率(資産効率性)の2つの数値を上げるのが理想だが、両者には一般に負の関係性が存在し、いいとこ取りの事業はそう簡単には存在しない。ところが、最近はそれを可能にする事業モデルが登場した。ファーストリテイリングに代表される製造小売業(SPA)である。

川崎重工業の失敗から見えるROIC経営への示唆とペンタゴンモデルの提唱
複数事業で大型プロジェクト損失を計上し、他の要因とも合わせた収益性低下でROIC他大半の数値目標が未達に終わった2017年3月期~2019年3月期の中期経営計画「中計2016」を振り返り、川崎重工業は「事業の『選択と集中』基準が不明確で実行スピードが不足」と結論付けた。
