臼井真粧美
#14
2021年度決算でゼネコンは資材高の逆風を受けて減益ラッシュ。対して不動産大手は増益ラッシュ。ゼネコンと不動産デベロッパーの間に「インフレ格差」が生まれている。

#11
外資大手投資ファンドは、溢れる運用マネーを投じる先を求めて国内であちこちに出没した。しかし、商業の超一等地である東京・銀座はあまり攻めなかった。そこには銀座ならではの事情がある。

#8
乗客数日本一の巨大ターミナル駅である新宿駅の再開発が始まった。事業規模1兆円を超えるとされる一大開発である。そこに食い込むゼネコン、不動産デベロッパー、鉄道会社の中には意外な顔触れがあった。

#6
大手ゼネコン5社のうち大林組は東京・銀座で影が薄く、他の4社に比べて受注が極端に少ない。同じ関西の地盤を持ち、「竹林戦争」と呼ばれる熾烈な戦いを繰り広げてきた竹中工務店は、しっかり受注しているのにだ。銀座における大手ゼネコンの力関係を明らかにする。
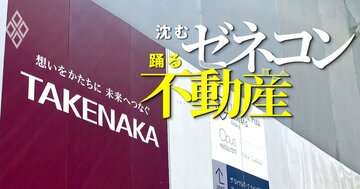
西武HDがプリンスホテルを大量売却!なぜ「破格の安値」になったのか?
西武ホールディングスがプリンスホテルなど国内31施設を外資系ファンドに売却した。これが「破格の安値」だった。ダイヤモンド編集部による特集『ホテルの新・覇者』では、安値の理由に迫った。

#8
西武ホールディングスのプリンスホテルや近鉄グループホールディングスの都ホテルなど電鉄系ホテルを大量に買収する外資系投資ファンド。その顔触れも、やり口も、かつてとは大きく変わっている。

#7
ホテル世界大手の米マリオット・インターナショナル、米ヒルトン、英IHGホテルズ&リゾーツ、米ハイアット ホテルズの4社が日本で勢いづいている。ホテルランキングでも上位は彼ら外資系ばかり。各社の幹部が日本攻略について赤裸々に明かした。

#3
ホテル御三家である「帝国ホテル 東京」「The Okura Tokyo」「ホテルニューオータニ」は互いがライバル関係にある。一方で現代のホテル業界の中心に立つ「令和の四皇」は、必ずしも競合しない。三井不動産しかり、彼らの間で手を組み、のし上がっている。

#16
ホテル不況のさなか、ウエディング業界大手のテイクアンドギヴ・ニーズが独創性の高い「ブティックホテル」の大量開業計画を打ち出した。世界の潮流として、「ブティックホテルのオリジナリティーは、大手ホテルグループのラインアップとの差別化にもなっている」と不動産サービス大手ジョーンズ ラング ラサール(JLL)の辻川高寛・ホテルズ&ホスピタリティ事業部長。確かにチャンスのある市場だが、新参者らしからぬ “自信”、そして “カネ”はどこから来るのか。野尻佳孝会長を直撃して疑問をぶつけた。
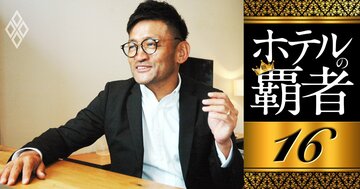
#8
日本のホテル業界の雄である星野リゾートは国内で開業ラッシュを仕掛けるのと並行し、米国本土進出を計画。これまでは漠然とした夢で語られてきたが、実は出店候補地を三つに絞る段階まで進んでいる。星野佳路代表がその全貌を赤裸々に明かした。
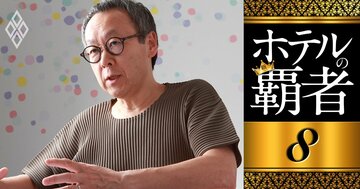
#6
三菱地所が米ヒルトンの最上級ブランドである「コンラッド」を冠したホテルを2026年に名古屋で開業する。三菱地所はリニア中央新幹線開業を控える名古屋駅前に不動産を持ち、そこを活用すれば成功必至のはず。しかし、実際の開業場所は名古屋駅前ではなく、栄エリアだった。

#12
不動産大手は増益ラッシュの好決算。対して、ゼネコン大手は軒並み営業減益となった。ゼネコンの体質、不動産会社など発注者との主従関係が「請け負け(うけまけ)」を生んでいる。ゼネコン大手は今期どう動くのか。

#3
JR東海、JR東日本に続き、JR西日本、JR九州、JR北海道も“勝負どころ”のホテルで外資系のマリオット・インターナショナルと手を組んだ。JR独自のブランドを冠するホテルですら、実は提携を結んでいる。

#1
西武ホールディングス、近鉄グループホールディングス、小田急電鉄など電鉄大手が相次いでホテル売却に動き、外資系投資ファンド勢はこぞって買い姿勢を見せる。にもかかわらず、西武グループによる31施設の大量売却は、売却価格がつり上がるどころか「破格の安値」で決着した。

#1
ANAホールディングスと日本航空が大赤字なのに対し、日本郵船と商船三井は大黒字。コロナ禍における格差は今後、投資余力の格差につながっていく。格差が連鎖する残酷な実態に迫る。
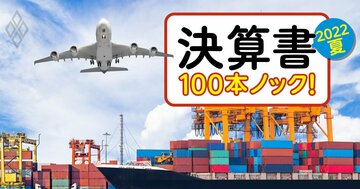
#7
チケット販売大手のぴあは、不動産大手の三菱地所と業務・資本提携を結んでいる。ぴあはここに「希望の光」を見た。

#6
コロナ禍でどん底に沈んだ市場が回復を始めた中で、ウエディング最大手テイクアンドギヴ・ニーズとリクルートの結婚情報誌「ゼクシィ」は次なるビジネスに目を向けている。目指すものは同じ。意外なかたちで2社がライバル関係になる。
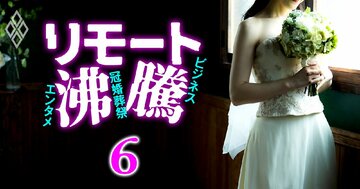
#5
高齢社会で死亡者数が増え続けるのを見越し、葬儀業界は新規参入に沸いてきた。ところが目下、およそ300社がM&A(企業の合併・買収)に身を投じたといわれている。大再編が巻き起こる業界の内情に迫る。

#4
医師らが集う学会でオンラインを使った開催が相次いでいる。医師からは定着を望む声もあり、そうなると打撃を受ける筆頭はどこなのか。製薬会社ではない。ホテルや航空会社が「三大危機」を抱えている。

#3
小田急電鉄が保有するホテル「ハイアット リージェンシー 東京」のチャペルは今、閉鎖されている。結婚式・披露宴の営業をひそかに終了していたのだ。理由はコロナ禍ではない。やめる決断を下したのは、それよりも前だった。
