岡田兵吾
第26回
名著と呼ばれる自己啓発本を読んでも、そこで得た知見を行動に移せない。そんなビジネスパーソンは多いだろう。それは何故なのか。何かを成し遂げるためには、吉田松陰のような「正しい狂気」が必要ではないと筆者は思う。

第25回
新たな目標を胸に1年のスタートを切っても、あとで振り返ると「結局、三日坊主だった」という人も多いだろう。「一年の計」はまず確実に挫折する。コツコツやることが美徳ではない。夢を掴むには「本気の三日坊主」も必要だ。

第24回
人より努力をしているはずなのに、あまり目立たないために、周囲から仕事を評価されないビジネスパーソンは多い。コツコツ英語力を磨いているタイプなどは、その典型例だろう。仕事を正当に評価される方法」をお伝えしよう。

第23回
筆者は「誰とでも仲良くなる」ことが得意だ。それは過去にいた会社で1年以上売り上げゼロが続いた筆者自身の苦しみの経験から生まれた処世術である。仕事で人生を逆転させる「最強コミュニケーション術」を紹介しよう。

第22回
あなたはプレゼンが得意だろうか。実は日本人のプレゼンは海外ではわかりづらく、「なんじゃこりゃ?」と言われることもしばしばだ。筆者ががむしゃらに学んだ、グローバル時代に必要なプレゼン力の身に着け方を教えよう。

第21回
安保法案成立、五輪エンブレム問題、新国立競技場問題――最近、日本で物議を醸している「お家騒動」について、外国人の意見を聞いてみた。彼らの反応を見て、改めて気づいた。外国人が今の日本に求めているのは、「武士道」ではないかと。

第20回
今年8月、シンガポールは国を挙げてのかつてない大イベントに沸いた。50周年となる建国記念日だ。愛国心むき出しでお祝いしている光景を見聞きし、自己肯定感は愛国心からも生まれるのではないかと思った。何より国際競争力を高めるためには自己肯定感は必須だ。

第19回
同じような仕事をし、同じような多忙さの中にあって、何かを成し得る人は何が違うのか。「何かを成し得る」には、グローバルですでに「法則化」されている原理が存在している。今回は、その原理に照らした「リーゼント式目標達成術」をご紹介しよう。

第18回
大阪都構想の是非を問う住民投票で、都構想は否決される結果となった。大阪の変革を願っていた筆者にとって、残念な結果だった。そこでふと思ったのが、日本人には革新を恐れない「吉田松陰マインド」が足りないのではないかということだ。

第17回
10年後には7割の仕事がなくなるという衝撃的なニュースが世間を賑わせている。そんななか、過酷な将来を生き抜くための「21世紀型能力」が提唱され始めた。筆者がこれまでに学んだ、生き残るための「ビジネス筋トレ術」をお伝えしよう。

第16回
各所の卒業式も終わり、4月から多くの「新人上司」が誕生する。そこで、ふと思う。日本の上司の何パーセントが、「良い上司」「良いリーダー」だろうか。先日亡くなったシンガポール建国の父・リー・クアンユーの生き方を教訓に、考えよう。
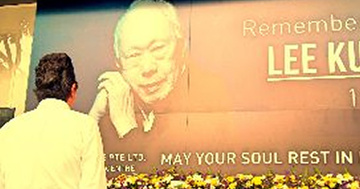
第15回
筆者がローカル小学校に子どもを通わせているというと、よく驚かれる。確かに両親ともに日本人で、子どもをローカルに通っている家庭はとても珍しいからだ。今回は、「子どもの学校選び」「教育」について、グローバルな視点から語ろう。

第14回
筆者は、シンガポールに赴任後の12年間で両親と一緒に正月を過ごすことが3回しかできなかったという、親不孝ものだ。最近、年をとった両親と正月を一緒に過ごせないことに対して、心が痛むようになった。今回は、親孝行のススメを考えよう。

第13回
「男の中の男」だった高倉健アニキ、菅原文太アニキの逝去の報を聞き、筆者の心には隙間風が吹きまくっている。景気が足踏み状態にあり、大義なき衆院選に揺れる日本に、真のリーダーシップは残っているか。両アニキ亡き今、それを論じたい。

第12回
日銀の「バズーカ砲第二弾」で円安が続く日本には、いつ何時「青い目の買収者」がやって来るかわからない。ある日突然、あなたの会社の公用語が英語に変わることもある。そんな時代を生き抜く「グローバル会話術」の要諦を、今から学ぼう。
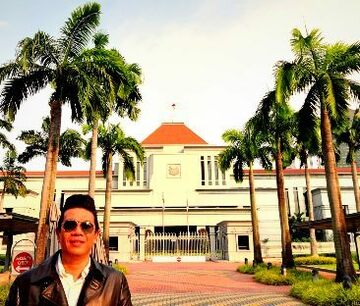
第11回
日本のグローバル教育は遅れているのではないかと言われるが、今さら焦っても仕方がない。日本の子どもたちが外国人とのコミュニケーション能力を高めるには、どうしたらいいか。実は英語力だけではなく、グローバル会話力こそが重要なのだ。

仕事の肩書きを取ったら、あなたは何と名乗りますか? そう聞かれて困る人は多いだろう。今回は、自分の人生に付加価値をつけるための「副業」について考えたい。日本ではまだ馴染みの薄い副業だが、グローバルでは当たり前となっている。
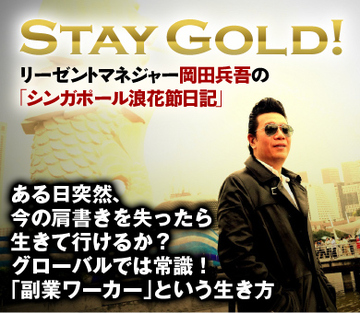
第9回
成長戦略にも掲げられた「女性活用」に、今いち現実味が感じられない日本。翻って、アジアにおけるグローバルの象徴であるシンガポールは、なぜ「女子の自立天国」たり得たのか。前回に続き、驚くべき「働く女性のカカア天下ぶり」をお伝えしよう。
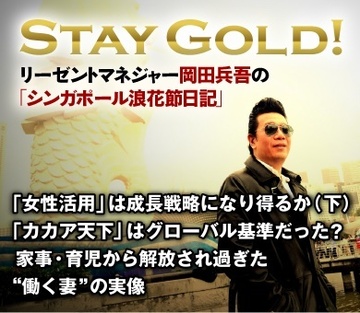
第8回
アベノミクスの成長戦略の1つとして「女性の活躍」が謳われているが、世の中には実現不可能という懐疑的な見方もある。背景には、女性の社会進出に対する「壁」の存在がありそうだ。翻ってシンガポールでは、日本人には想像もつかないほど女性が活躍できる土壌がある。
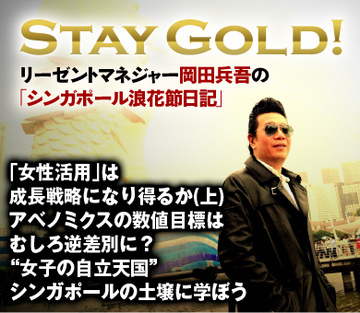
第7回
仕事とMBAの勉強を両立させようと奮闘し、自分史上最悪の忙しさに陥ってしまった僕。しかし周囲の外国人たちは、どんなに忙しくてもプライベートの時間を重視していた。僕はそれを見習って、仕事圧縮の極意を身に付けることができた。
