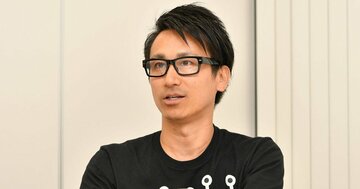酒井真弓
読者の方から、新規事業開発について「うちの会社がヤバいんです」というお悩みをいただいた。新しい事業の開発に失敗する企業もあれば、成功する企業もある。失敗する/成功する企業それぞれの特徴を知れば、成功に生かせるのではないだろうか。これまでの取材を思い出しながら、失敗の法則について考えてみた。

業務に使用するソフトウエアなどを開発するのに、外部の企業に外注するのではなく、社内での内製化に取り組む企業が増えている。先日行われたGoogleのクラウド開発者向けイベント「Google Cloud Next '22」で、3社に実情を聞いた。

トレンドマイクロの調査によれば、DX推進担当者のうち35.2%がサイバーセキュリティインシデントを経験し、9割以上がDX推進におけるサイバーセキュリティ対策に懸念があるという。さらに、自社にサイバーセキュリティを踏まえてDX推進ができる人材がいると回答したのは14.3%となった。DXに乗り出したばかりの企業に潜むリスクとは? そして、社内のセキュリティ体制を強化する方法とは? 某大手銀行グループでインシデント対応や人材育成に従事し、現在、サイバーセキュリティの人材育成に取り組む宮内雄太さんに聞いた。

DXに取り組んでいるエンジニアは、血の通った人間だ。だからこそ人材採用が重要だが、優秀なエンジニアは引く手あまたで、中途エンジニアの採用は年々厳しくなっている。そんな中、三菱UFJ銀行、日揮、ファーストリテイリングをはじめ、DXに力を入れる非IT企業の間で、新卒エンジニア採用がじわじわと活発化している。非IT企業が新卒エンジニアを振り向かせるにはどうしたら良いのだろうか。『ゼロからわかる新卒エンジニア採用マニュアル』の著者で、約7万人に及ぶエンジニア学生の就職活動を支援してきたサポーターズ CEO 楓博光さんに、採用広報から用意すべき年収額まで、ざっくばらんに聞いた。

2020年12月、東北大学病院は新型コロナウイルス感染症の第3波と戦いながら、ホテルなどの宿泊療養施設で使用するレントゲン・採血・心電図などの検査連携システムを開発していた。さらに紙での患者管理を電子化し、大幅な業務効率化を果たした。特筆すべきは、極限状態でこれらを内製、つまり自分たちの手で実装したことだ。過酷な医療現場で医師とIT責任者が二人三脚で挑んだ、命を守るDX。その裏側を聞いた。

DXを進める切り札として、クラウド活用を推進する専門チーム「CCoE(Cloud Center of Excellence)」を設置する企業が増えている。国内でも比較的長い歴史を持つ富士フイルムビジネスイノベーションのCCoEは、IT部門ではなくユーザー部門に設置されている。その意図とは?

コロナ禍の2年半で、ZoomやTeamsなどのテレビ会議システムを使ったり、スマートフォンのテレビ電話を使ったりする機会が激増した。言い換えれば距離の制約を越えて「バーチャルで会う」ことを経験した人が世界中で激増したわけだが、便利さを実感する半面「リアルに会うのとは違う」と思うのもまた事実。今回インタビューした阪井祐介さんは、あたかも同じ空間にいるような自然なコミュニケーションを可能にする「窓」の開発者だ。阪井さんが窓を「どこでもドアのようなもの」と表現する理由とは。

ソースコードの記述をせず、アプリやWebサービスなどのソフトウエアを開発することを「ノーコード開発」と呼ぶ。プログラミング経験がなくても誰でもアプリが作れるというわけだが、実際にはプログラマー以外でアプリやWebサービスを開発したことがある読者はほとんどいないだろう、しかしLIXIL(リクシル)では、幹部全員を含む従業員4000人がノーコードでアプリ開発に挑戦し、業務を効率化するアプリを1万7000個作ったという。そんなにアプリを作って、LIXILは一体何がしたいのか?仕掛け人に取材してみた。

郵政創業は今年151年目を迎える。全国約2万4000の郵便局を有し、40万人以上が働く巨大組織である日本郵政グループが今、デジタルによって大きく変わろうとしている。変革をリードするのは、ダイソン日本法人社長や楽天アメリカ法人社長を歴任し、2021年に日本郵政グループCDO 兼 JPデジタルCEOに就任した飯田恭久さん。そして、郵政一筋20年のDX推進室 室長 兼 JPデジタルCOO 大角聡さんだ。外から来た飯田さん、生え抜きの大角さんのコンビは日本郵政をどう変えようとしているのだろうか。

株式会社G-gen(ジージェン)の杉村勇馬さんは、Google Cloudの認定資格11個をコンプリートし、アマゾンのクラウドサービスであるAWSの認定資格を9個持っているというクラウド業界のトップエンジニアだ。そんな杉村さんの前職はなんと警察官。IT未経験でエンジニアに転身し、自身を「異世界転生もの」とたとえる杉村さんに、どんな学び方をしてきたのかを聞く。

大手紳士服店「洋服の青山」が、顧客であるビジネスパーソンとの共創コミュニティによって変わろうとしている。クールビズにテレワークの浸透、右肩下がりの紳士服業界にあって、希望の光となるだろうか。コミュニティで活躍する人たちが一堂に会する「コミュニティリーダーズサミットin高知(CLS高知)」で、青山商事 リブランディング推進室の平松葉月さんが語った。

「武闘派CIO」を名乗り、それぞれの企業や社外の人とも一緒にDXに取り組む人たちがいる。先日、さまざまなコミュニティで活躍する人たちが一堂に会するイベント「コミュニティリーダーズサミットin高知(CLS高知)」が開催され、3人の武闘派CIOが登壇した。筆者が司会で行ったパネルディスカッションの内容が面白かったので、今回はそのダイジェストをお伝えしたい。

日本のDXが進まないと言われて久しいが、一般企業以上に進んでいないのが行政のDXだ。行政のDXを妨げる要因はどこにあるのか。「役所は遅れている」と批判する前に、自治体を取り巻く閉塞感の正体と、私たち住民ができることを考えてみたい。
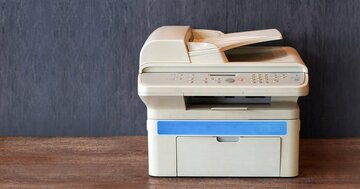
日本の役所には「自分たちは間違えてはいけない、間違わないために前例を踏襲する」という考えが浸透している。実際には日々テクノロジーの進化によって、より良いモノや手法が生まれているのに、「間違ったことをしてはいけない」という概念にとらわれすぎて、前例踏襲主義から抜け出せない。そんな行政を変える動きが、少しずつだが生まれている。

オンラインで開催されたイベント「技育祭」(ギーク祭)に登場した、元2ちゃんねる管理人のひろゆき(西村博之)氏。一問一答セッションでは、エンジニアを目指す学生たちからたくさんの質問を受けていた。ひろゆき氏のアドバイスとは……?

オンラインで開催されたイベント「技育祭」(ギーク祭)に登場した、元2ちゃんねる管理人のひろゆき(西村博之)氏。一問一答セッションでは、エンジニアを目指す学生たちからたくさんの質問を受けていた。ひろゆき氏のアドバイスとは……?

オンラインで開催されたイベント「ギーク祭」に登場した、元2ちゃんねる管理人のひろゆき(西村博之)氏。一問一答セッションでは、エンジニアを目指す学生たちからたくさんの質問を受けていた。ひろゆき氏のアドバイスとは……?

多くの日本人にとって“勤勉さ”とは、朝早く出社し、真面目に机に向かい、しっかり残業することだったのではないだろうか。しかしこれが原因で成果が出せない、躍進するアジア諸国に置いて行かれているのだとしたらどうだろう?

九州のホームセンター「グッデイ」は、DXに成功した地方企業として、他社からも注目される存在だ。しかし同社には7年間の“暗黒期”があったという。暗黒期を抜け出すきっかけになったのは、ある2つのITサービスを使い始めたことだった。

KDDIは2020年、クラウド活用を推進する専門組織を発足させた。その成果としてコンシューマ向けのサービスでクラウド活用が進む半面、クラウドが使われていることを知らない部門も存在したという。また、通信インフラを担う会社であるだけに、セキュリティを担保するためにはクラウドなんてとんでもない、という声もあった。こうした組織でどのようにクラウド活用を進めたのか、リーダーに話を聞いた。