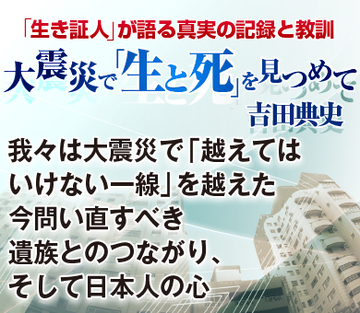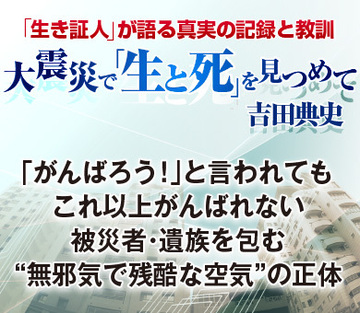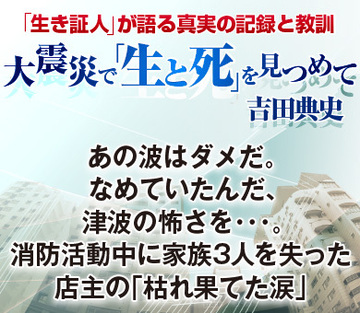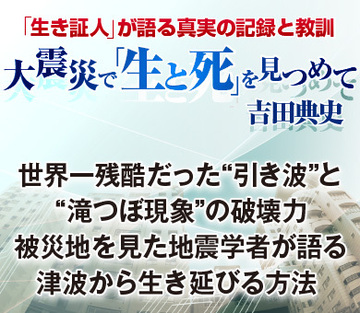今回の震災で死亡したり、行方不明となった消防団員は、総務省消防庁が9月に行なった調査で253人になる。内訳は、岩手県が119人、宮城県が107人、福島県が27人。
消防団員は、普段は自営業を営んだり、農林水産業に従事している。火災や地震などの自然災害があれば、いち早く現場に駆けつけ、人命救助や消火、復旧作業などを行なう。
東北3県で犠牲になった消防本部の職員は27人であるのに対し、団員は253人。団員は非常勤特別職の地方公務員であるが、1人につき年間で数万円の報酬しか支給されない。災害や火事などの1回の手当は、1500~3000円ほどだ。
彼らが3月11日、命をかけて行なった災害救助活動の後には、さらなる試練が待ち構えていた。今回は、消防団員の活動やその課題を採り上げることで、「大震災の生と死」を考える。
津波が来ることはわかっていた
だが、逃げることはできなかった
 迫り来る津波を前に、消防団員たちが命がけで閉鎖作業を行なった水海水門。写真は大震災前のもの。(写真提供/NPO法人環境防災総合政策研究機構)
迫り来る津波を前に、消防団員たちが命がけで閉鎖作業を行なった水海水門。写真は大震災前のもの。(写真提供/NPO法人環境防災総合政策研究機構)
「おい、これはどうすんだ?」「操作手順のマニュアルを早く見ろ!」「わかんねぇ」「早くしろ、急げ! 津波が来るぞ」
3月11日午後2時46分の地震直後、岩手県釜石市(人口3万8000人)の中心から北に4キロほどにある、高さ12メートルの水海(みずうみ)水門の上。水門は、両石湾に面し、湾の奥には漁村がある。周辺には、漁業などを営む数百人が生活をしていた。
水門上の機械室で、救命胴衣すら着ていない消防団員らの大きな声が飛び交う。その1人、大森秀樹氏(43)は訥々とした口調で振り返る。
「実は、4人は水門を手動で閉める訓練をしたことがなかった。津波が来るんじゃないかと思い、水門を閉めようと焦る。だけど、操作を知らなかった」