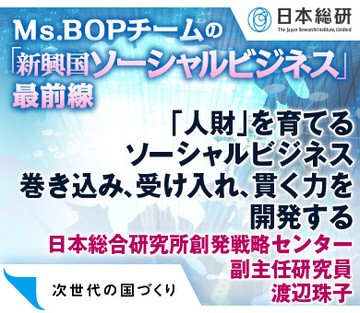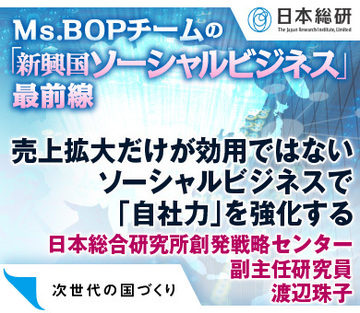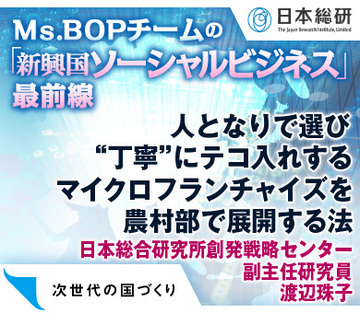前回プロローグでは、ソーシャル・ビジネスを日本で語る際に見落とされがちなポイントを説明した。今回は、日本の読者(多くは日本の企業で働く方々)が、自分のビジネスと新興国・途上国のソーシャル・ビジネスを繋げて考えて行くための最初の一歩を、社会インフラ事業の例を通して提示したい。今回は「アハ・モーメント」を体感する手前の心構えについてだが、一つ一つ深淵へと歩いて行くための一歩として捉えて頂きたい。
「ソーシャル・ビジネス」は色々
一義的に定義する必要はない
前回ソーシャル・ビジネスの代表例として、ムハンマド・ユヌス氏のグラミン銀行を例にあげたが、実はこれは使い古されてしまった事例の一つである。(非常に分かりやすく明快なビジネスモデルであるため使われやすい)。それゆえ、ソーシャル・ビジネスと言えばグラミン銀行を思い起こす人も増えているようだ。だが、ユヌス氏のソーシャル・ビジネスの考え方は、多様な考え方の一つにすぎない。ユヌス氏独自の思想、バングラデシュという国独自の背景を持っており、他の地域や産業、組織でも必ずそのままうまく行くとは限らない。
例えば、彼のソーシャル・ビジネスの考え方の根本には、投資家との関係において事業に投資した投資家に対し、配当を行うべきではなく、事業からの収益は新規の社会的事業に投資される。それがソーシャル・ビジネスに投資する投資家のリターンである、という考え方を打ち出している。だが、違う考え方もある。例えば南米地域のソーシャル・ビジネスは、より収益性についての追求が厳しく、その代わり多様な金融機関や投融資を行う団体が社会的投資に乗り出している。
ユヌス氏の考え方はマイクロファイナンスの立役者として、マイクロファイナンスの歴史を見守って来た中で主張しているスタンスであり、南米地域のアクター達の考え方は、地理的に近いアメリカからの社会的投資の流れとの強い関係の中で培われてきた。またアフリカにはアフリカの土壌や生態系(事業を行う上での環境)があり、また異なった考え方がある。つまり、ソーシャル・ビジネスの考え方は多様であっていいのだ。