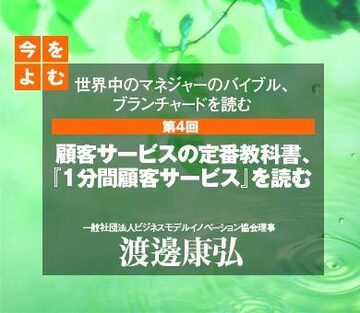「寡占化」と「多様化」を分けるものとは?
――「意味がある」市場では多様化が進む
以上がフランクとクックによる「勝者総取り」の発生メカニズムの説明なのですが、いささか考察の目が粗いと言わざるを得ません。
というのも、それぞれの市場にはそれぞれの特性があり、いくら限界費用が下がったとしても、すべての人々が同じものを欲しがるような市場ばかりではないからです。
実際には、個別の市場に応じて「寡占化が発生しやすい市場」と「寡占化が発生しにくい市場」とがあります。では、どのような市場特性が「寡占化」と「多様化」を分けることになるでしょうか。
ここでフレームワークを用いて考察してみましょう。このフレームでは、顧客に提供している2つの価値軸に沿って市場を整理してみます。2つの価値軸とは、すなわち「役に立つ・立たない」という軸と「意味がある・ない」という軸です。
1つ目の「役に立つ・立たない」という軸は、古典的なマーケティングの用語で言えば「機能的便益の有無」ということになります。
一方で2つ目の「意味がある・ない」という軸は「情緒的便益の有無」あるいは「自己実現的便益の有無」ということになります。
結論から言えば、勝者総取りが発生するのは以下の図の「1の象限」ということになります。なぜなら「1の象限」では、評価関数が発散せず、収斂してしまうからです。

たとえば、わかりやすいのがICチップです。ICチップの評価は極めて単純にコストと計算能力で決定されることになります。
「ロゴの色合いが絶妙だ」とか「本場ブルゴーニュで作られている」とか「イタリアの職人が精魂を込めている」といった意味的な属性はここでは製品の評価にまったく組み入れられません。グーグルもアマゾンも同様にこの象限に含まれることになります。
人がこれらのサービスに求めているのは機能的便益であり、情緒的で意味的な価値が競争に介在する余地はほとんどありません。結果として、GAFAのような企業による勝者総取りという事態が発生するわけです。
「役に立つ」市場では勝者総取りが発生する一方で、「意味がある」市場では多様性が生まれることになります。これを身近でわかりやすく示しているのがコンビニエンスストア(以下CVS)の棚です。
皆さんもご存知の通り、CVSの棚は極めて厳密に管理されており、商品を棚に置いてもらうことは簡単なことではありません。だからハサミやホチキスなどの文房具はほとんど1種類しか置かれていません。しかし、それで顧客が文句を言うことはありません。
一方で、そのように厳しい棚管理がなされているCVSにおいて、1品目で200種類以上取り揃えられている商品があるのですが、なんだかわかりますか?
タバコです。ハサミやホチキスは1種類しか置かれていない一方で、タバコは200種類以上が置かれている。なぜそういうことが起きるのかというと、タバコは「役に立たないけど、意味がある」からです。
ある銘柄が持つ固有のストーリーや意味は他の銘柄では代替できません。マールボロを愛飲している人にとってマールボロという銘柄は代替不可能ですし、セブンスターを愛飲している人にとってセブンスターという銘柄は代替不可能なのです。人が感じるストーリーや意味は多様なので、銘柄もまた多様になるわけです(*3)。
これが「役に立つ」と「意味がある」の市場特性の違いです。ハサミやホチキスなどの文房具は「役に立つけど、意味がない」という市場に生息しています。つまり評価関数が収斂する市場で戦っており、したがって定番商品を置いておけば誰も文句は言わず、それを買ってくれるということです。
このような二極化が進行する世界において、すべての企業は「役に立つ」という市場において、生き残りをかけて熾烈な戦いに身を投じるか、「意味がある」という市場で独自のポジションを築いていくかという選択を迫られることになります。
この2つのうち、どちらを選ぶかはなかなか難しい問題ですが、ただ一つだけ指摘できるのは、従来の定石に囚われすぎてしまい、深く考えることもなく「役に立つ」市場でスケールを目指そうとするのは、間違いなくオールドタイプの思考様式だということです。
なぜなら、グローバル化が進めば進むほど「役に立つ」市場の頂上は「高く、狭く」なり、ごくごく少数の「グローバル勝ち組企業」以外は生き残ることができない「真っ赤っかのレッドオーシャン」になるからです。
一方で、なんらかの「意味」にフォーカスを絞ることで独自のポジションを獲得するニュータイプは、「グローバル×ニッチ」という「爽やかなブルーオーシャン」を自らの居場所にすることになります。
(注)
*3 他にも「役に立たないけど、意味がある」という商材を考えて議論してみると面白い。たとえば、音楽やアートや文学やワインなどもそのような商材として考えられるが、これらはことごとく極めて多様なブランドによって成り立っている。典型例がバーのカウンターに並ぶボトルの数々で、これを眺めているとつくづく「役に立たないものこそ多様なんだな」ということがよくわかる。