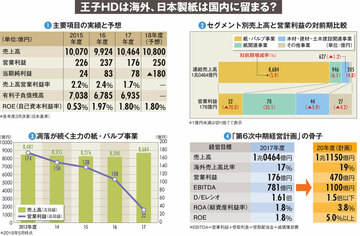日本の近代産業史上で、「製紙王」と呼ばれる人物は2人いる。大川平三郎(1860年12月7日~1936年12月30日)と藤原銀次郎(1869年7月25日~1960年3月17日)である。
大川は、13歳で親戚に当たる渋沢栄一に玄関番(書生)として仕え、渋沢の発意で設立された国内3番目の製紙会社、抄紙会社(後に王子製紙に改称)に16歳で入社、職工となって腕を磨いた。勉強熱心で、製紙技術を学びに米国に派遣される経験にも恵まれ、技術部門の要職を務める。木材パルプでなく、わらを使った製紙技術を日本に導入したのは大川である。
しかし、当初は思うような紙の製造ができず、王子製紙の経営は厳しかった。同社は、設立にこそ渋沢の思いが深く込められていたが、渋沢自身の出資は10%。最大の出資者は三井財閥だった。三井は王子製紙の経営強化のために追加出資をするとともに、渋沢と技術部門担当の専務取締役だった大川の追い出しにかかった。
1929年5月1日号に掲載された大川のインタビューでは、この経緯について詳しく触れ、「私がいては渋沢の勢力を除かれないというので、私を追い出しにかかった」とはっきり述べている。
王子製紙を離れた大川は、国内各地にとどまらず、中国・上海や日本領だった樺太に製紙会社を立ち上げる。一時は富士製紙や樺太工業をはじめとする大川の経営する製紙会社群で、国内シェアの45%を握っていたという。
一方、前述した三井財閥の下で王子製紙を再建したのが、富岡製糸場支配人から転じてきた藤原だった。大川は、このインタビューの中で「後年になって藤原銀次郎君が私と三井の連中とを和解させた。それについては私は藤原君を徳としています」と語っている。すでにわだかまりは消えていたようだ。
2万字に及ぶ長文記事なので上中下の3回に分けてお届けする。「上」は、渋沢家の玄関番となり、製紙技術者として腕を上げていくまでの出世譚である。
あらかじめ述べておくと、3回目の「下」で大川は、当時入れ込んでいた樺太工業に懸ける思いを熱く語っている。しかし実際は、経営悪化によって、この記事が掲載されて4年後の1933年、大川の富士製紙と樺太工業は、王子製紙に吸収合併される。藤原が社長を務める新生・王子製紙の国内シェアは80%を超え、「大王子製紙」と称された。
かくして藤原も「製紙王」と呼ばれることになる。これが、日本に2人の製紙王が存在するゆえんである。 (敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)
議論好きだった幼少時代
油屋の主人と上京の経緯
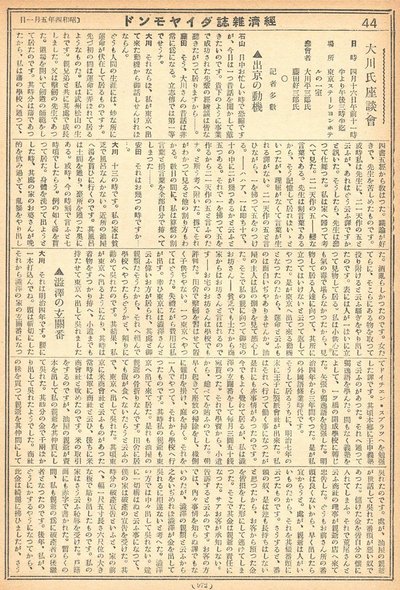
1929年5月1日号より
――日中お忙しいときで恐縮ですが、今日は一つ昔話を聞かせていただきたいのです。貴下のように事業で成功された先輩の経験談はみんな聴きたがっておりますから……。
藤田 そう、大川さんの昔話は非常にためになる。立志伝では第一等でしょうな。(編集部注:同席した藤田好三郎・樺太工業専務。後にとしまえんを創業する。以下、カッコ内はすべて現在の編集部による注釈)
大川 それならば、私が東京へ出てきた動機からお話ししなければならん。
どうも人間の生涯には、妙なところに運命が伏在しているものですな。
まず初めの間は運命にもてあそばれているようなものだ。私は武州松山の生まれです。親兄弟と共にそこで成長しました。父は撃剣の先生であった。道場を開いて剣道の師範をしていたのです。その時分は藩であったから、私は藩の学校へ通って、四書五経から教わった。議論が好きで、先生を苦しめたものです。
あるとき私は先生に、「二一天作の五というが、あれはどういう訳ですか」と聞いた。そうしたら、先生は参ってしまった。私は家へ帰って考えてみた。(この後大川自身の説明があるが、旧式珠算で用いた「割り算九九」の“割り言葉”。現在は「掛け算九九」が一般的だが、昭和10年代までは割り算も歌のようにして覚えていた)
「二一天作の五」――変な言葉である。先生は割り言葉であるから、そう記憶していればいいと言ったが、理屈がなくて言葉が生まれる訳がない。二一天作の五と言いながら、一を払って五を乗っける。ハハァ、一はすなわち十で、十の中に二が幾つあるかというと五つある。それで一を払って五を作るから二一天作の五というのだな、とこう考え付いた。さて、それが分かってみると他の割り方も分かる。数日の間に、私はそろばんの割り言葉と掛け言葉を全部自分でこしらえてしまった……。
──それはお幾つのときですか……。
大川 13のときです。私の家は貧乏で風呂なんかない。近所の油屋へ湯をもらいに行くのです。その風呂は土間を通り、台所を通った奥にある。あるとき、今の時刻で言うと7時ごろでしたろう。例のごとく湯をもらっていた。
体を洗って出ようとしたとき、そこの家のおばあさんが晩酌を飲み過ぎて、乱暴をやりだした。酒乱らしかったのです。女だてらに、そこらにある物を取って投げ付けるという騒ぎをやりだしたのです。表には人がいっぱいに立って見物している。私は子供心にも気の毒でたまらなかったから、見物している人たちに向かって、そこに立ってはいけないと言って返してやった。
これが東京へ出てくる動機となったのだから、運命というものは面白いじゃありませんか。油屋の主人は私のさばきを見て感心した。そこで私の親に向かってお宅のお坊さん──貧乏でも侍だから商家からはお坊さんと言われるのです──お宅のお坊さんは学校でも評判だ。田舎で撃剣を習わせておく子供じゃない。ひとつ東京へやってはどうだ。失礼ながら費用は私が出す。幸い東京には渋沢栄一さんという偉いお方がおられ、そことご親類だそうだから、それへ頼んで学校へやったらどうかと、しきりに勧めてくれたのです。
その結果、私が東京へ出るようになり、そのときは荷物をすっかりこしらえ、小遣いまでも持たせて東京へ出してくれました。